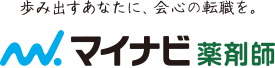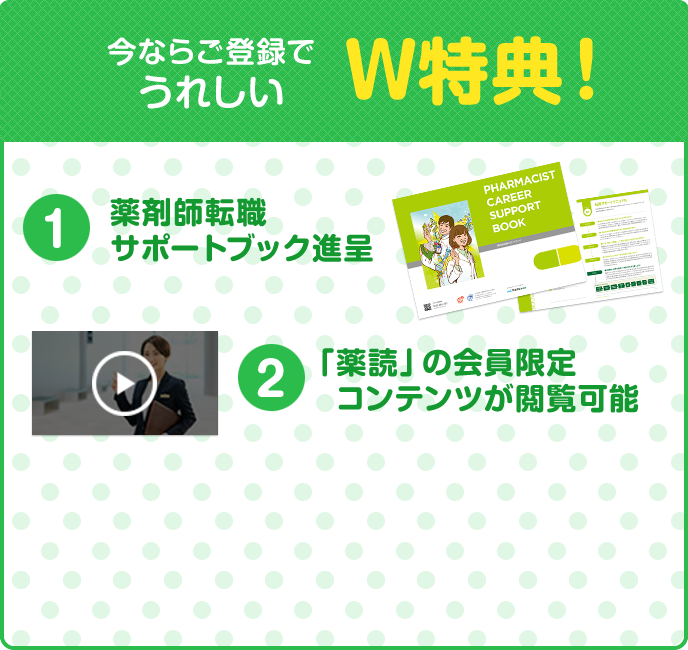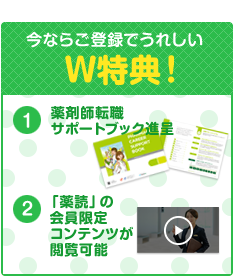【最新版】薬剤師は不足している?転職の際に気を付けるべきポイントも解説

転職を考えている薬剤師にとって、業界における薬剤師の充足率は転職活動に大きな影響を与える要因になります。
これまでの薬剤師の転職市場においては、「薬剤師不足」の状況が続いてきましたが、その一方で、薬剤師の総数が増えていることから、いずれは薬剤師が過剰になるだろうといった意見もあります。
また、将来的に人工知能(AI)や海外で導入されているファーマシーテクニシャン(調剤助手、調剤技師)が調剤業務に参入してくる可能性を考えると、薬剤師の需要と供給のバランスが今後どうなっていくのか気になるところです。
今回は、薬剤師の過不足に関する現状や、将来の展望、そして最新の転職市場の動向についてまとめました。
薬剤師が転職するときに気を付けるべきポイントも合わせて解説しますので、参考にしてみてください。
目次
1.薬剤師は本当に不足している?現状は?
薬剤師の転職市場では、長らく「薬剤師が不足している」との声が続いていましたが、現状はどうなのでしょうか? 厚生労働省が毎月発表している有効求人倍率のデータを基に、薬剤師の雇用状況について見てみましょう。また、施設別・年齢別の薬剤師の人数も確認していきます。
1-1.薬剤師の有効求人倍率
薬剤師の有効求人倍率は、令和5年3月現在で2.17倍でした。有効求人倍率とは、企業からの求人数(有効求人数)を求職者(有効求職者数)で割った値のことで、雇用動向を示す指標の一つです。令和5年3月の値は2倍を超えているため、求職している薬剤師1人に対して、2件以上の求人が出ているという状況が示されており、このデータから「まだまだ薬剤師は不足している」という状況がうかがえます。
また、薬剤師の有効求人倍率と国内の全職種の有効求人倍率を比較すると、国内の全職種の有効求人倍率における平均は1.32倍であるため、薬剤師の有効求人倍率は全体平均よりもかなり高いことが分かります。
参照元:厚生労働省/一般職業紹介状況(令和5年3月分)について 職業別一般職業紹介状況[実数](常用(含パート))
1-2.施設別の薬剤師の数
施設別の薬剤師の人数を見ていきましょう。令和2年12月31日現在における全国の届出薬剤師数は、321,982人です。施設別で見ると、「薬局の従事者」は188,982人(総数の58.7%)、「医療施設の従事者」は61,603人(総数の19.1%)、「病院の従事者」は55,948人(総数の17.4%)、「診療所の従事者」は5,655人(総数の1.8%)、「大学の従事者」は5,111人(総数の1.6%)、「医薬品関係企業の従事者」は39,044人(総数の12.1%)、「衛生行政機関または保健衛生施設の従事者」は6,776人(総数の2.1%)となっています。
| 施設 | 薬剤師数 |
|---|---|
| 薬局の従事者 | 188,982人(総数の58.7%) |
| 医療施設の従事者 | 61,603人(総数の19.1%) |
| 病院の従事者 | 55,948人(総数の17.4%) |
| 診療所の従事者 | 5,655人(総数の1.8%) |
| 大学の従事者 | 5,111人(総数の1.6%) |
| 医薬品関係企業の従事者 | 39,044人(総数の12.1%) |
| 衛生行政機関または保健衛生施設の従事者 | 6,776人(総数の2.1%) |
前回の平成30年の届出数と比較すると、全体の届出数は10,693 人(3.4%)増加し、増加率の高い施設として「薬局」が8,567 人(4.7%増)、「医療施設」が1,647人(2.7%増)が挙げられます。特に、平成6年頃から「薬局」が年々大幅に増加しているのが特徴です。
参照元:厚生労働省/医師・歯科医師・薬剤師数、構成割合及び平均年齢,性・年齢階級、施設・業務の種別
1-3.年齢別の薬剤師の数
年齢別の薬剤師の人数を見ていきましょう。令和2年12月31日現在における全国の届出薬剤師数は、321,982人です。年齢別でみると、「30~39歳」が 82,378 人(25.6%)と最も多く、次いで「40~49歳」73,305人(22.8%)、「50~59歳」63,575人(19.7%)、「60~69歳」44,162人(13.7%)、「29歳以下」39,980人(12.4%)、「70歳以上」18,582人(5.8%)となっています。
| 年齢 | 薬剤師数 |
|---|---|
| 29歳以下 | 39,980人(12.4%) |
| 30~39歳 | 82,378 人(25.6%) |
| 40~49歳 | 73,305人(22.8%) |
| 50~59歳 | 63,575人(19.7%) |
| 60~69歳 | 44,162人(13.7%) |
| 70歳以上 | 18,582人(5.8%) |
前回の平成30年の届出数と比較すると、全体の届出数は10,693 人(3.4%)増加し、増加率の高い年齢として「70歳以上」が1,811人(10.8%増)、次いで「60~69歳」が2,725人(6.6%増)が挙げられます。60歳以上の構成割合は総数に対して高くないものの、増加率は上がっていることから、薬剤師の高齢化が進んでいることがうかがえます。
参照元:厚生労働省/統計表3 医師・歯科医師・薬剤師数の年次推移,年齢階級、性別
2.都道府県別の薬剤師の数はどれくらい?
薬剤師の雇用状況は地域により差があるため、都道府県別に見ると、薬剤師の数が多い都道府県と少ない都道府県があります。
「都道府県(従業地)別にみた薬局・医療施設に従事する人口10万人あたりの薬剤師数(令和2年12月31日現在)」を基に都道府県別の薬剤師の数を確認していきましょう。参考として、令和2年の調査では全国平均は198.6人でした。
2-1.薬剤師の数が多い都道府県
| 薬剤師の数が多い都道府県 ベスト5 | |
|---|---|
| 1 | 徳島県 238.6人 |
| 2 | 東京都 234.9人 |
| 3 | 兵庫県 233.9人 |
| 4 | 広島県 221.2人 |
| 5 | 香川県 216.4人 |
薬剤師の数が全国平均よりを上回っている都道府県は12都府県でした。多い順に、徳島県(238.6人)、東京都(234.9人)、兵庫県、広島県、香川県、大阪府、高知県、山口県、神奈川県、福岡県、佐賀県、和歌山県です。比較的、東日本より西日本のほうが薬剤師は充足していることがうかがえます。
2-2.薬剤師の数が少ない都道府県
| 薬剤師の数が少ない都道府県 ベスト5 | |
|---|---|
| 1 | 沖縄県 148.3人 |
| 2 | 福井県 157.0人 |
| 3 | 青森県 161.2人 |
| 4 | 山形県 167.8人 |
| 5 | 福島県 171.0人 |
薬剤師の数が全国平均よりも下回っている都道府県は35道府県でした。全国平均である198.6人を大幅に下回り、170人台までの県を少ない順に列挙すると、沖縄県(148.3人)、福井県(157.0人)、青森県、山形県、福島県、岐阜県、三重県、新潟県、富山県、愛知県、群馬県、岩手県です。比較的、東北や北陸で薬剤師不足が進んでいる傾向があります。
3.薬剤師が不足していると言われる原因
薬剤師の人数は経年的に増加しているものの、なぜ「薬剤師不足」といわれるのでしょうか。ここでは、代表的な3つの理由をご紹介します。
3-1.薬局が増加傾向にあるため
薬局が増加することにより、薬剤師の勤務地が分散し、結果的に薬剤師不足を招いています。全国の薬局数は年々増加傾向にあり、令和3年の届出数は61,791になりました。薬局で働く薬剤師も年々増加する一方、1店舗における1日当たりの勤務薬剤師数に差が出ています。1店舗における1日当たりの勤務薬剤師数は平均で2.58人ですが、その回答の内訳を見ると「1.1~2人」の割合が最も多く、平均を下回る店舗が多く存在しているため、薬剤師不足を感じている薬局が多いことが懸念されます。
3-2.女性の割合が多いため
女性の薬剤師が多いため、家事や育児を理由に仕事を離れる方も多く、薬剤師不足を招いています。令和2年12月31日現在の薬剤師数は321,982 人で、そのうち、女性は197,740人であり、全体の61.4%を占めています。また、令和2年の人口動態によると、女性の初婚年齢は29.4歳、出生数に対する母の年齢(5歳階級)は30~34歳が36%と最も多く、次いで、35~39歳が23.3%です。薬剤師数が最も多い30代は、女性にとって出産や育児を迎える時期でもあり、薬剤師の職から離れる方も少なくありません。女性が半数以上を占める薬剤師は潜在資格者になりやすく、薬剤師不足を招く要因になります。
3-3.資格を必要としない仕事に就職したため
薬剤師の資格を取得した人が全てが、薬剤師の仕事についているというわけではありません。薬剤師の働き方は多様にあるため、薬剤師としての知識を生かして一般企業へ就職したり、講師やライターなどとして働いたりすることも可能です。もちろん薬剤師とは関係がない異業種へ転職する方もいるでしょう。そのため、薬剤師国家試験の合格者は年々輩出されるものの、潜在資格者も増加することから、薬剤師不足を招いていると言えます。
4.薬剤師不足の今後は?
このような薬剤師不足の状況は、今後どのように推移するのでしょうか? 薬剤師不足の今後について4つの傾向を解説します。
4-1.長期的には供給が需要を上回ると予想されている
「薬剤師の需給動向の予測に関する研究(平成30年度)」によると、「今後数年間は薬剤師の需要と供給のバランスが均衡している状況がしばらく続くものの、長期的には薬剤師が過剰になるだろう」と予測されています。
この薬剤師の需給動向の予測は、厚生労働省研究事業による研究報告で、平成30年度から平成55年度の25年間を推計期間としています。需要予測は今後の処方箋枚数や病床数などから算出し、供給予測は薬剤師国家試験の合格者数の動向などから算出されています。
つまり、薬局や医療機関での薬剤師の働き方が当時と変わらない場合は、薬剤師の供給過多が見込まれると予測しているのです。
4-2.薬剤師業界の市場は今後も拡大傾向にある?
高齢化社会が急速に進んでいる今、薬剤師業界全体の市場が今後も短中期的には、拡大を続けるということも考えられます。需要と供給のバランスでは、長期的にみて、需要よりも供給が上回ると予測される一方、令和3年現在では、全国の薬局数も61,791軒となり、年々その数は増えているからです。
参照元:厚生労働省/厚生労働統計 第2編 81表(令和3年データ、最新)
さらに調剤併設のドラッグストアも近年では当たり前となり、ドラッグストアも新規参入を続けているため、それに伴い新たに薬剤師を確保する必要があるためです。
4-3.AIやテクニシャンによる影響
調剤薬局業務へのAIまたはファーマシーテクニシャンの活用による影響も考えていかなくてはなりません。
AIは、すでに製造業をはじめとするさまざまな産業において、膨大な量のデータ処理、統計処理、在庫管理システムなど、事務的で正確性を求められる業務に活用され始めています。
医学・薬学の分野も例外ではなく、画像診断や手術支援などの診療活動の一部ではすでにAIの導入が始まっており、その存在感は高まる一方です。
薬剤師が担う業務の中でも、調剤に係る計算や計量、薬歴管理などは今後AIにシフトしていく可能性がありますが、服薬指導や患者さんからの相談対応業務など、薬剤師としての経験と豊かな対人スキルが求められる業務に関してはAIが参入する余地はありません。
AIの参入をマイナスに捉えるよりも、AIはむしろ薬局の事務系タスクを軽減し、一人一人の薬剤師が専門知識とコミュニケーションスキルを発揮することに専念できる環境を作ってくれるものだとプラスに捉えると良いでしょう。
一方、ファーマシーテクニシャンは、薬剤師の指示の下、医薬品の調達や患者さんとの連絡などを含む調剤業務の一部を担う専門スタッフのことで、欧米諸国ではすでに導入が始まっています。
今後日本でも同様の専門職が導入される可能性があり、その動向が注目されています。
しかしながら、ファーマシーテクニシャンの裁量は限定的で、全ての業務は薬剤師の指示の下で行われます。
決して薬剤師に替わるものではないため、ファーマシーテクニシャンの登場によって薬剤師が余ってしまうという状況は起こり得ないはずです。
AIと同じく、ファーマシーテクニシャンを活用することで、薬剤師の労働負担が減り、より働きやすい環境を整えてくれるものとして捉えると良いでしょう。
ロボット調剤導入のメリットなどについては、こちらの記事をご覧ください。
4-4.在宅医療薬剤師やかかりつけ薬剤師の重要性
今後は在宅医療薬剤師やかかりつけ薬剤師の重要性がさらに高まります。AIやファーマシーテクニシャンの導入を踏まえたとき、これからの薬剤師に求められることは、対物業務から対人業務への移行、専門家としてのより豊かな経験と知識を備え、患者さんが頼れる相談役としての能力です。
とくに後期高齢者の割合が増加する地域では、患者さんとより近い距離で専門的なサービスを提供することのできる薬剤師の存在が重要になっていきます。
そのため、下記の2つが注目されています。
- 在宅で療養している患者さん宅を訪問し、さまざまな相談に応じる「在宅療養支援認定薬剤師」いわゆる在宅医療薬剤師
- 患者さん選任の薬剤師として、一人の患者さんを継続的にサポートするかかりつけ薬剤師
薬剤の調剤や交付、病歴管理などのベーシックな業務だけでなく、患者さん一人一人の健康をサポートするこれらの役割は、医療チームの一員としても期待を集めています。
在宅医療薬剤師の役割を知りたい方は、こちらをご覧ください。
かかりつけ薬剤師やかかりつけ薬局に関する内容は、こちらをご覧ください。
5.薬剤師の転職で気を付けるべきこととは?
5年、10年前と比較すると、薬剤師の有効求人倍率は年々低くなっていますが、現在の状況としては有効求人倍率2倍台を維持していることから、数字で見ると薬剤師業界は「売り手市場」であると言えます。
売り手市場の場合、求人件数が求職者数を上回っているので、複数の職場から内定をもらえるという状況が起こり得ます。しかし、実際の転職市場としては数年前とは変わってきており、近年の診療報酬改定などの影響により経営難に伴う採用ハードルが上がっていることもあります。
売り手市場は、転職を考えている薬剤師にとっては一見好ましい状況に思われますが、実際に転職するに当たっては、気を付けなくてはならない点があります。
まず職場探しでは、自分自身のライフプランに合った働き方ができるかどうか、自分が望む働き方ができるかどうかを見極めることが大切です。
もともと育児や家族との時間を大切にしながら働けるようにと転職を決めたにもかかわらず、給与面の良さに惹かれて本来の希望とは異なる求人に飛びついてしまうと、思った以上の激務に追われ、再び転職を考えなくてはならなくなるといった事態も起こり得ます。
職場探しの段階では、このようなギャップが起きないように、「自分は薬剤師としてどうありたいか」というブレない軸を持っておくことが大切です。
また、希望の条件に合った転職先が複数見つかった場合、その中から最終的にたった一つの職場を選ぶという判断力が求められます。
単により高収入が得られる職場を目標に転職するのなら、迷うことはないのかもしれませんが、職場の人間関係や雰囲気、休暇の取りやすさなど、求人情報を見ただけでは分からない内部事情を考慮するとなると、想像以上に難しいものです。
売り手市場においては、求人情報に記載されている給与・勤務条件だけにとらわれて安易に転職してしまうことがないよう、より慎重にリサーチすることが重要です。
転職活動をする際には、自身のキャリアの棚卸や履歴書・面接対策など、しっかりと準備をした上で、転職を希望する理由や目的を明確化し、優先順位付けしていくことが大切になります。
6.薬剤師の市場価値を高める事が重要
現状としては薬剤師不足が続いている薬剤師の転職市場ですが、社会全体の有効求人倍率の低下と連動し、いつかは薬剤師不足の解消によって薬剤師の有効求人倍率が低下し、将来的に転職が難しくなっていくことも考えらえます。
万が一、薬剤師が過剰になったとしても、企業から「選ばれる」存在として活躍し続けるためには、自らの薬剤師としての市場価値を高めておくことが重要です。
特に後期高齢者が増加するこれからの社会では、在宅医療薬剤師やかかりつけ薬剤師といった専門資格を持つ薬剤師は、全国チェーンの薬局であっても、個人経営の薬局であっても、かけがえのない人員としてますます需要が高まることが予想されます。
もちろん、在宅医療薬剤師やかかりつけ薬剤師などの専門資格を得るためには、定められた実務経験を積む、あるいは研修や試験を受けるなどの自己投資が不可欠です。
薬剤師としての将来の市場価値を高めるためにも、自信のキャリアアップ、スキルアップを目標に、今できることから準備を始めましょう。
7.薬剤師の転職には転職エージェントの活用がおすすめ
薬剤師としてこれから転職を考えているなら、薬剤師に特化した転職エージェント「マイナビ薬剤師」を活用することをおすすめします。
マイナビ薬剤師は、転職を検討している薬剤師が無料で登録できる転職支援サービスで、自分に合った求人探しから応募書類の書き方、面接のコツに関するアドバイス、面接の日程調整や労働条件の交渉など、転職に必要なプロセスの全てを専門のスタッフが支援してくれます。
中でも大きな強みは、扱っている求人情報の量と、マッチングの精度の高さです。
プロのキャリアアドバイザーとの面談で、一人一人の希望条件や強みを棚卸することで、膨大な数の求人の中からその人に合った職場をマッチングしてくれます。
サービス内容についてより詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
求人情報からは読み取れない転職先の内部事情や雰囲気などの情報もおおよそ把握して提供してくれるので、転職してから「こんなはずじゃなかった」といった失敗を避けることができます。
また、今すぐ転職する予定がなくても、将来に備えたキャリアプランの相談に乗ってもらうことも可能です。転職に興味のある人はマイナビ薬剤師に登録しておきましょう。
8.まとめ
薬剤師の求人有効倍率は徐々に低下しているものの、現在もなお薬剤師が不足している転職市場。特に都市部以外の地域では、薬剤師不足の状況は今後もしばらく続きそうです。
しかし近い将来、調剤業務へのAIやファーマシーテクニシャンが導入されれば、薬剤師の雇用状況は大きく変化し、より専門的な知識やスキルを持った薬剤師に需要が集中することが予想されます。
いかなる状況においても、企業から「選ばれる薬剤師」になるには、自らの市場価値を高めておくことが大切です。
各地域の雇用状況を注視しつつ、冷静な判断力を持って、自分に合った職場を見つけていきましょう。マイナビ薬剤師は、皆さんの転職を応援しています。
毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報
おすすめの薬剤師求人一覧
転職準備のQ&A
求人応募のQ&A
面接対策のQ&A
薬剤師の転職の準備に関するその他の記事
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554