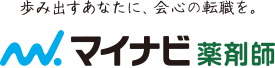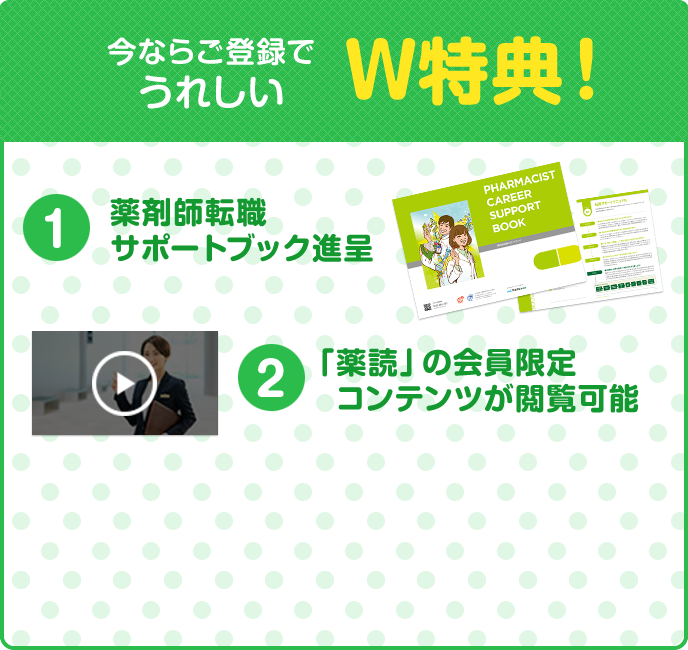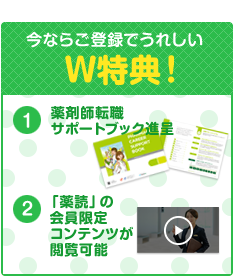MR職に将来性はある?現状や新たに求められている役割について

MR認定センターの「2024年版MR白書」によれば、MRの数は2013年の約6万6千人をピークに10年連続で減り続け、2023年には約4万7千人まで減少しています。
かつては、「医師への接待攻勢と、昼夜を問わない営業活動で製薬会社の売上に貢献する営業マン」というイメージがあったMR職ですが、2012年に医師への接待が原則禁止となったほか、2019年には情報提供活動の規制も厳格化。以降は、本来の役割である情報提供活動の内容が問われるようになりました。
今回は、そんなMRの現状と、今後求められる役割について解説します。
目次
1. MR職の現状や将来が不安と言われている理由
先に紹介したように、2012年4月からMRによる医師の接待が原則禁止になっています。
それまでのMRの仕事は、「接待がメイン」と思われるほどでしたが、接待がなくなったことで病院以外で医師と接する機会は激減しました。また、医療業界にデジタルマーケティングやオンライン面談が普及したことで、病院を訪問する機会はさらに減っています。
そして、思うように活動できない現状にあることから、将来的を不安視するMRも少なくありません。
では、MRの将来が不安視される理由について、もう少し詳しく見ていきましょう。
1-1. MR職が飽和している
デジタルツールの導入による効率化が進んだ結果、MRの数は飽和状態となり、製薬各社では支店の廃止や希望退職・早期退職を募るなど、MR職の業務体制に関する見直しが進みました。
ちなみに、2013年のピーク時には65,752人のMRが活躍してましたが、その後は年々数が減少。2023年には46,719人となり、10年間で19,033人も減っています。
1-2. 医師がMRを必要としなくなってきている
製薬企会社による接待が原則禁止となった2012年以降、ディオバン事件や三重大病院事件のような世間を騒がせる不正が次々と明らかになり、MRと距離を置くようになった医師も少なくありません。
さらに、インターネットやスマートフォンの普及によって、営業やマーケティングの手法がデジタル化しており、伝統的なMRの営業スタイルに違和感を覚える医師も増えています。
特にコロナ禍以降は、オンラインでの医薬品情報の提供が進み、現在はウェブ経由で情報を入手する医師が相当数存在します。こうした社会的な状況の変化も、医師にMRの必要性を感じさせなくなった要因と言えるでしょう。
1-3. 営業規制が厳しくなってきている
2012年以降、医師と製薬企会社の癒着が大々的に報じられたことで、製薬業界に対するコンプライアンス強化を求める声が高まりました。
一方、接待が禁止されたことで、MRによる行きすぎた情報提供活動(誇大説明、他社製品を誹謗中傷など)が目立つようになり、2019年4月には厚生労働省から「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインについて」が明示されるに至りました。
加えて、コロナ禍ではMRの訪問がほぼ禁止になり、それ以降、事前アポイント制や面談時間の制限などを求められるケースが増えています。
このようにMRの営業規制は厳しさを増しており、必然的に「MRにできること」も減っています。つまり、以前ほどMRの数を確保する必要がなくなっているわけです。
1-4. 薬価の引き下げ強化や研究開発費確保の問題
日本の薬価は、欧米と比較して高めに設定されていましたが、近年は外圧などの影響により、薬価見直しのたびに5~8%ずつ引き下げられてきました。さらに、2018年以降は政府による薬価引き下げ圧力も強まり、2021年からは価格乖離の大きな品目について、薬価改定を実施する中間年改訂が行われることになりました。
また、研究開発費の高騰により、大規模な開発がしにくくなっている点も、製薬会社を取り巻く課題の一つです。新薬開発には1000億円以上の莫大な費用がかかる上に、基礎研究に対する政府の援助は決して手厚いとは言えず、オプジーボのような画期的新薬=「ピカ新」が、生まれにくい状況にあるのです。
そのため、製薬会社にとっては利益の確保が難しい状況となっており、国内市場は縮小傾向にあります。
以上のことから、多くの製薬会社が必要なときだけCSO(医薬品販売業務受託機関)にMRを派遣してもらうスタイルに移行しており、将来に不安を募らせているメーカーMRは少なくありません。
2. MRとして働いていくには
医師との面談が仕事であるMRにとって、現在は「働きにくい環境」にあると言えます。ただし、このような状況でも、MRが不要になるわけではありません。
市場の状況にかかわらず、新薬の研究・開発は常に行われています。そして、医薬品が開発された際は、その情報を広く伝えることが必要です。
その点において、医療用医薬品情報のスペシャリストであるMRは、製薬会社と医師の双方にとって必要な存在であり、MRという職種がなくなることはないでしょう。
以下では、これからもMRとして働いていくために必要不可欠な、職場選びのポイントについて考えていきます。
2-1. 資本力と承認実績のある会社で働く
MRである以上、ピカ新であれゾロ新(改良型新医薬品)であれ、承認数の多い企業を選びたいものです。
その観点からすると、新薬を生み出すための研究開発費が多い国内の大手製薬会社に注目すべきですが、中には研究開発予算を抑えつつ、一定数の新薬承認を得ている企業もあります。
そのため、職場選びをするにあたっては、資本力と承認実績の両面から評価するのが得策でしょう。
ドラスティックな人員削減などは気になりますが、資本力と承認実績という点では、実績のある外資系企業も選択肢の一つです。
2-2. CSOで働く
医薬品の営業やマーケティング活動を受託するCSO(医薬品販売業務受託機関)に所属し、CMR(コントラクトMR)として勤務するのも一つの方法です。
CMRは、製薬会社にMRの欠員が出たときの補充や、注力製品のMR力強化などに対応するために雇用されるMRで、派遣MRとも呼ばれます。
製薬会社の人員削減が進む現在、雇用が発生せず効率的な人員の運用ができるCMRの存在は、製薬会社にとって大きなメリットとなります。一方、CMRの側にも、さまざまな分野の医薬品を手掛けられる、複数の企業を掛け持ちできるなどのメリットがあり、スキルアップ・キャリアアップにもつながるでしょう。
CSOには未経験からの転職組が多いため、メーカーのMRから転職すると収入が減ってしまう可能性はありますが、人員削減の対象になるリスクは避けられます。そうしたことから、「CSO=MRとして長く働くための選択肢」となっており、近年はメーカーからCSOに転職するMRも増えています。
3. 新たにMRに求められる役割
製薬業界では新薬の上市が少ない反面、ジェネリック薬品は増加の一途をたどり、新薬メーカーの経営を圧迫しています。
一方で、高齢者の主要な医療現場は病院から在宅へと移行し、地域包括ケアシステムの推進と多職種連携が急務となっています。
このように、社会と医療の関わりが急速に変化している現状を踏まえれば、MRに変革が求められることは、必然と言えるのかもしれません。
これまでMRは自社の新薬と、担当する医師の専門分野に特化した情報提供を行ってきました。しかし、医療が在宅中心となり、患者さんごとにオーダーメイド化されていく中では、個別の臨床に対して情報提供を行っていく必要があるでしょう。
担当する医師とともに患者さんとの接点を持ち、個々の患者さん向けの処方について情報提供を行う。今後のMRには、そうした新たな役割が求められるわけです。
4. MRの考えられるキャリアとは
薬価の引き下げ、新薬リリースの減少、ジェネリック薬品の拡大、そしてコンプライアンスの強化と医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進。近年はこれらの影響で、MRのニーズが減少傾向にあります。
しかし、MRという職種がなくなることはなく、これからは旧来型の業務スタイルとデジタル時代の業務スタイルを融合させた、ハイブリッド型MRに収れんしていくと考えられています。
ここでは、現在厳しい状況にあるMRが、今後目指すべきキャリアパスについて考えてみましょう。
4-1. 管理職を目指す
メーカーMRの場合は、CSOやほかの職種への転身を検討する、MRとして管理職を目指すなどの選択肢があります。「いきなり転職に踏み切るのは不安」という方は、最初にキャリアパスの王道とも言うべき、管理職への道を検討してみてはどうでしょうか。
これまで培ってきた経験を武器に、営業所長やエリアマネージャー、さらには本部の管理職へと昇進できれば、MRとしてのキャリアは成功と言えるでしょう。ただし、そこには営業所自体の業績や、同僚との競争なども関係してくるため、険しい道のりであることは間違いありません。
職場の状況と自身の適性をよく見極めた上で、キャリア設計を行いましょう。
4-2. 現在の職場でのキャリアチェンジを考えてみる
人事異動の希望が出せる職場であれば、転職せずに社内でキャリアチェンジを目指してみるのもいいでしょう。
キャリアチェンジの場合、業界の知識と営業力を生かしてマーケティング部門を目指す方が多いようですが、専門性を磨いてファーマコビジランス(医薬品安全性監視)やMSL(メディカル・サイエンス・リエゾン:最新の医学情報を医療従事者に提供する職種)を目指す道もあります。
ファーマコビジランスは、MRと連携して医薬品の情報を収集したり、記録・評価を行ったりするため、MRとして働いている人にとっては、なじみ深い職種ではないでしょうか。
ちなみに、ファーマコビジランスの仕事はMRよりも開発寄りで、医薬品だけでなく疾患についても調べる必要があるため、開発部門の中にファーマコビジランスを置く企業もあります。
ファーマコビジランスの詳細は、こちらの記事をご覧ください。
一方、MSLはディオバン事件以降、急速に普及したメディカルアフェアーズ部門の専門職です。
「医師に対して、医薬品の情報を提供する」という点ではMRと同じですが、MSLの場合は自社医薬品の販促活動を行いません。MSLの主な業務は、製薬会社と臨床現場との中立的な立場から、最新の医学情報を提供することであり、処方を誘導するようなプロモーション活動は禁止されています。
また、情報提供にあたって、学会や論文などから最先端の医療情報を集めたり、勉強会を企画・運営したりするのも、MSLの大事な業務です。
MSLの詳細は、こちらの記事をご覧ください。
4-3. 薬剤師への転職を検討してみる

MRの仕事では、患者さんと接する機会がほとんどありません。しかし、営業活動の中で身につけた高いコミュニケーション能力と情報収集力、そして医薬品に関する知識は、薬剤師の業務にも十分生かせる強みとなります。
そのため、メーカーMRの中には薬剤師への転職を目指す方が少なくありません。
薬剤師は、調剤薬局やドラッグストア、病院といった幅広い選択肢から職場が選べるほか、MRと違って残業・転勤がほとんどないというメリットもあります。
薬剤師への転職を検討しているMRの方は、ぜひこちらもご覧ください。
4-4. 思い切って他業種へ転職してみる
MRとして身につけた営業力と医療に関する知識を活用して、他業種への転職を考えてみるのもいいでしょう。
MRに近い職種として挙げられるのは、医療機器メーカーの営業職やMS(Marketing Specialist:医薬品卸販売担当者)です。
医薬品と医療機器の両方を手掛ける企業の中には、営業職全員にMRの認定資格取得を課しているところもあるため、MRとしての知識やスキル、経験が生かしやすいでしょう。
ほかにも、医療や医薬品に特化した広告代理店や調査会社、医療系IT企業など、MRの経験が生かせる職場は少なくありません。また、医療の場が病院から在宅へと移る中、MRが地域医療で果たすべき役割も大きくなっています。
MRから他業種への転職は大きな飛躍のきっかけとなる可能性もあるため、転職エージェントを活用するなどして、より自分に合った職場を探してみましょう。
5. まとめ
ここ数年は、AIを使用したチャットボットなど、「MR支援」を名目としたデジタルサポートが多く見られるようになりました。しかし、医療業界におけるDX化が進んだ結果、MRの数を確保する必要がなくなっていることも事実です。
デジタル化以外にも、薬価の引き下げ強化やコンプライアンス強化など、MRを取り巻く環境にはネガティブな要因が多く、その将来性は不安定さを増しています。
そうした中でMRとして生き残るためには、専門分野において突出した知識や経験、スキルを身につけることと、自分の特性に合った職場で働くことが大事です。
現在転職を検討している、あるいは近い将来転職したいという希望を持っている方は、医療業界に精通し、公開・非公開を含めた豊富な求職情報を提供してくれる転職エージェントを活用してはいかがでしょうか。
薬剤師専門の転職エージェント「マイナビ薬剤師」では、経験豊富なキャリアアドバイザーが、あなたのキャリアや魅力を客観的に分析し、希望に合った転職先を案内します。
さらに、選考に通りやすい書類の書き方や面接に関するアドバイス、面接の日程調整、条件交渉などのサポートも行っているため、働きながらでもスムーズに転職活動が進められるでしょう。
毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報
おすすめの薬剤師求人一覧
転職準備のQ&A
薬剤師の転職の準備に関するその他の記事
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554