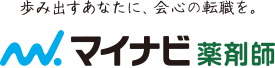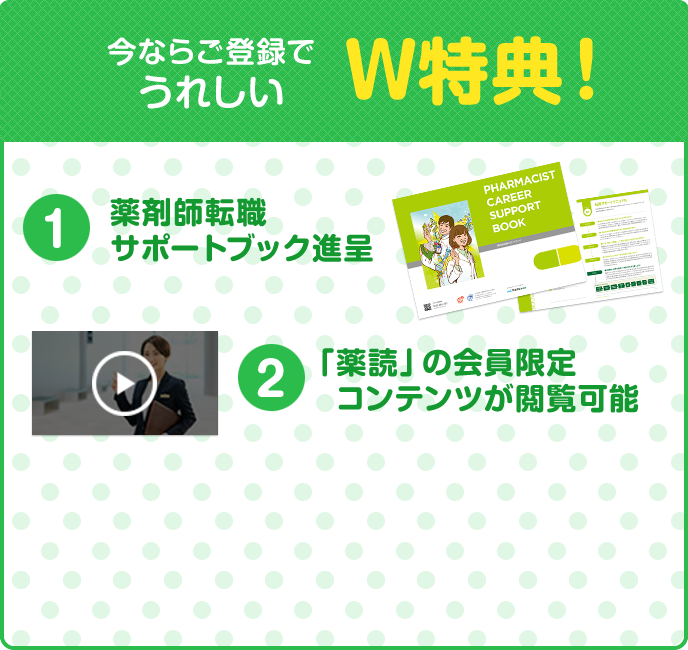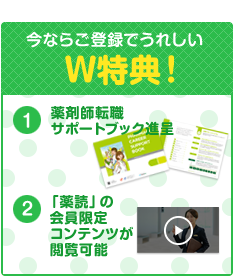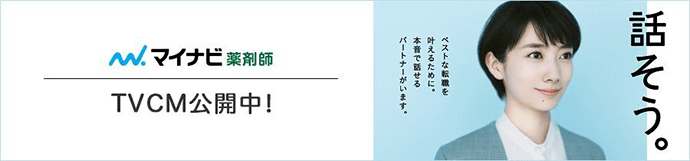公務員薬剤師の仕事内容やメリットとは?給与や転職方法についても徹底解説

省庁や保健所、市町村役場で働く公務員薬剤師は高待遇・高年収・安定というイメージもあり、人気のある業種の一つです。
しかし、公務員薬剤師と言っても、国家公務員薬剤師と地方公務員薬剤師があり、その働き方は千差万別です。転職するとなると、具体的にどうすれば公務員薬剤師になれるのか、どのような仕事をしているのかを理解している薬剤師は少ないのではないでしょうか。
今回は、職場ごとに異なる公務員薬剤師の仕事内容やメリット、転職するための方法などについてご紹介します。
目次
1.公務員薬剤師とは?
公務員薬剤師とは、国または、都道府県や市区町村など地方自治体の行政機関に勤務する薬剤師のことで、大きく「国家公務員薬剤師」と「地方公務員薬剤師」に分けられます。
国家公務員薬剤師は、厚生労働省などの国の機関に所属する薬系技官、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部に所属する麻薬取締官、自衛隊で薬剤官として勤務する自衛隊薬剤師、刑務所で法務技官として勤務する刑務所薬剤師があります。
一方、地方公務員薬剤師は、地方自治体の都道府県庁や保健所、公立病院、衛生研究所などさまざまな勤務先により、仕事の内容も異なります。
2.公務員薬剤師の職場や主な仕事内容
公務員薬剤師の職場や主な仕事内容を、詳しく紹介していきましょう。
2-1.国家公務員薬剤師
国家公務員薬剤師が薬系技官として働く職場は、仕事内容の分野別に、厚生労働省に多くの部署があります。また、厚生労働省にとどまらず、他の省庁や国際機関への出向もあります。例えば、内閣官房の健康・医療戦略室や国家安全保障局、内閣府の食品安全委員会事務局、消費者庁や環境省のほか、地方行政施設や在日外国大使館、国立医薬品食品衛生研究所などの国の機関などがあり、民間企業や大学への出向もあります。
国家公務員薬剤師の仕事内容は、所属する職場により、さまざまな分野・領域があります。それでは、主な分野の仕事内容を紹介していきましょう。
参照元:厚生労働省/総合職 薬系技官
参照元:厚生労働省/薬系技官 採用情報
参照元:厚生労働省/薬系技官 採用情報 主な配属先
2-1-1.研究開発分野
研究開発分野において、企業や大学が医薬品を開発しやすい環境を整えたり、研究予算を確保したりします。具体的には、医薬品の研究開発の促進、医療系ベンチャー企業の支援などを行います。
2-1-2.薬事分野
薬事分野の仕事内容は、医薬品の品質、有効性、安全性などが保を保つための法律に基づき、医薬品メーカーなどに対して、医薬品の製造管理および品質管理の監視・指導などを行います。そのほか、非合法薬物などの取り締まりや献血の推進、医薬品の販売制度、薬剤師国家試験などにも携わります。近年では、令和4年薬機法の改訂や新型コロナウイルス感染症に対する薬事上の対応、緊急時の薬事承認なども担当しました。
参照元:厚生労働省/総合職 薬系技官 令和4年薬機法等一部改正の内容
2-1-3.食品安全分野
食品安全分野の仕事内容は、食品添加物の指定や規格基準の策定、食品のリスク評価、農薬の残留基準、器具・包装容器などの規格基準などを管理し、食品衛生法などに基づいて、流通している食品の安心安全を守る仕事です。
2-1-4.化学物質分野
化学物質分野の仕事内容は、国民の健康にかかわる化学物質の安全対策をおこなう仕事です。新しい化学物質はもちろん、既存の化学物質においてもリスク評価や、毒物・劇物の取り扱いの取り締まりを行います。
2-1-5.保健医療分野
保健医療分野の仕事内容は、診療報酬・調剤報酬のあり方を検討し、定期的な改定に携わったり、適正な医薬品価格の設定や見直し、後発医薬品の使用促進などを行ったりする仕事です。薬剤師の職能発揮のための取り組みなどの仕事もあります。
2-2.地方公務員薬剤師
地方公務員薬剤師の職場は、県庁や市区町村役場の薬務課や保健所、県立や市立などの公立病院、衛生研究所などです。どの部署に配属されるかは辞令次第ですが、いずれの配属先でも、地域に密着して地域住民の健康を守る仕事です。
各職場の仕事内容について紹介します。
2-2-1.薬務課
各都道府県庁の薬務課では、地域における診療報酬の管理、新規薬局の開設許可、医薬品製造業の認可、毒物・劇物の製造業・販売業の登録、立ち入り検査、監査などを行います。各々の場所で適切な業務が行われ、安全な医薬品の供給ができるかなどを調べます。
2-2-2.保健所
保健所は、地域保健法において設置義務が定められている施設で、地域の医療施設などが適正に運営されるよう保健・衛生の管理監督業務をおこなう機関です。具体的な仕事内容は所属する部署によって異なりますが、主に以下のような業務が挙げられます。
●薬事衛生
薬局・店舗販売業・卸売販売業・医療機器販売業・毒物劇物一般販売業等に対しての許可・監視・指導等の対応を行います。
●食品衛生
食品製造業者・飲食店などに対する許可・監視・指導等の対応を行います。
●環境衛生
上下水道や旅館・ホテルといった宿泊施設、温泉や銭湯といった公衆浴場、クリーニング店、理容室・美容室などサービス業に対する環境衛生施設の新規開設許可や、立入検査を行います。
保健所への転職を考えている方は、以下のページも参考にしてください。
2-2-3.公立病院
地方公務員薬剤師の職場の一つに、県立病院や市立病院などの公立病院の薬剤部があります。その仕事内容は、一般病院の病院薬剤師と同じです。公立病院に入院している患者さまの内服および注射調剤、服薬指導、医薬品情報管理、医薬品管理のほか、病棟薬剤師は医療チームの一員としての役割もあります。
2-2-4.衛生研究所
衛生研究所は、都道府県や指定都市などに設置されている、地域の衛生行政の中核機関で、地方公務員薬剤師の職場のひとつです。衛生研究所勤務の薬剤師は、病原体の解析などの感染症予防の研究、有害物質の検出など環境衛生や公衆衛生の監視・管理、医薬品の衛生管理、食品衛生の管理などに携わります。
参照元:地方衛生研究所ネットワーク/地方衛生研究所の機能強化について
参照元:千葉県/衛生研究所は、どのような仕事をしているのですか。
2-3.麻薬取締官
麻薬取締官は、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部に所属する国家公務員であり、その職場は、全国12ヵ所に配置されている地方厚生局麻薬取締部です。
麻薬取締官の仕事内容は、麻薬や覚醒剤、大麻、向精神薬、あへん、危険ドラッグを含む指定薬物といった薬物の乱用を防止するため、非合法薬物の不正使用者や密売人を摘発したり、医療用の向精神薬などの不正流通防止のための指導・監督をしたりするなど多岐にわたります。麻薬取締官には、特別司法警察職員としての権限がある点で、一般の国家公務員薬剤師とは異なります。
参照元:職業情報提供サイト/麻薬取締官
麻薬取締官の仕事内容や資格の取得の詳細については、以下のページも参考にしてください。
3.公務員薬剤師の給与はどれくらい?
国家公務員の給与は、国家公務員の一般職に対して、人事院の給与勧告が適用になります。国家公務員薬剤師は、医療職俸給表(二)の区分で、人事院の実態調査によると、令和4年4月現在の平均給与月額は、357,805円(平均年齢46.5歳)でした。
地方公務員の給与は、5年毎に実態調査が行われています。自治体や職場によって異なりますが、職種や自治体などによらず、薬剤師全体の令和3年の平均基本給月額は、388,685円でした。
地方公務員の一般職員の平均基本給月額の340,177円と比較すると、国家公務員薬剤師も地方公務員薬剤師も、高めと言えます。
参照元:人事院/国家公務員給与の実態
参照元:人事院/令和4年国家公務員給与等実態調査の結果
参照元:総務省/職種別職員の平均給与額
4.公務員薬剤師のメリット
公務員薬剤師には、民間で薬剤師として働くことに比べ、大きく5つのメリットがあります。
4-1.ワークライフバランスが実現しやすい
公務員薬剤師のメリットとして、ワークライフバランスを実現させるための制度が整っているということがあります。厚生労働省は元より、地方自治体も働き方改革を推進・実現させる役割があるためです。
例えば、産前産後の休暇や育児休業、育児短時間勤務、男性職員の育児休業の取得などがあります。また、子どもの看護や親の介護にかかわる支援もあり、ライフステージに合わせた働き方で、仕事を続けられる環境が整っているため、キャリアを積むことが可能です。
4-2.安定した収入を得られる
公務員薬剤師の大きなメリットの一つとして、収入や働き方が安定しているということがあります。薬剤師は国家資格のため、他の職業と比べて安定していると考えられますが、民間の薬局やドラッグストアの場合には、業績の悪化などによって勤務先が倒産したり解雇されたりする可能性があります。
その点、公務員であればその心配はありません。また、昇給やボーナスの支給も安定しており、勤続年数や役職に応じて収入が上がっていくので、安心して働き続けることができます。
4-3.福利厚生が充実している
公務員の場合、福利厚生が充実しているのも、大きなメリットです。
公務員の福利厚生が充実しているのは、国家公務員も地方公務員も各共済組合法に基づく共済組合の共済制度があるからです。ケガや病気、被災の際の給付金や見舞金、育児や介護に関わる休業手当などが手厚くなっています。
また、住宅については、公務員住宅が用意されている自治体があります。住居を新築、購入、売却時に割引を受けられるのは、金額が大きいだけに魅力的です。その際の引っ越し料金の割引などもあるようです。
レクリエーションの部分では、保養所や契約施設、指定のホテルの宿泊料金の割引や、旅行代金の割引などもあります。その他、国家公務員共済組合では、生命保険などの保険の掛け金、資金の貸付制度、財形貯蓄などは、市中より優遇されているようです。
参照元:総務省/福利厚生施策の在り方に関する研究会報告書
参照元:広島県/【福利厚生制度】 制度概要
参照元:厚生労働省/共済のしおり
4-4.仕事の幅が広がる
国家公務員薬剤師は、前述のとおり、出向という形でさまざまな分野に活躍の場があります。
また、いずれの分野も相互に関係があるものの、基本的には2~3年で異動し、違う業務を担当します。薬学の専門性を活かしながら、さまざまな分野の業務に就く機会があるため、仕事の幅が広がるのがメリットです。
さらに、地方公務員薬剤師は、配属される職場により、大きく仕事内容が異なります。公立病院などで薬剤師として調剤や服薬指導に当たる場合もありますが、保健所や衛生研究所では、薬学で培った専門性を活かしながら、さまざまな仕事に携わることができます。
4-5.社会貢献を実感できる
厚生労働省で働く国家公務員薬剤師も地方公務員薬剤師も、一言でいえば薬学的専門性を活かしながら、国民や地域の住民の健康増進や安全を守るために働く仕事のため、社会貢献を実感できる仕事と言えます。
例えば、国家公務員薬剤師は、政策立案やその運用、保険制度の改革など、国民の健康に対して俯瞰した立場で貢献しているといえます。
また、地方公務員薬剤師は、地域に密着した形で直接地域住民の保健、衛生に関わるため、社会貢献を実感することが多い仕事です。
5.公務員薬剤師のデメリットとは?
公務員薬剤師にデメリットはあるのでしょうか。公務員薬剤師のデメリットについて考えていきましょう。
5-1.初任給が低い
公務員薬剤師のメリットに安定した収入がある一方、初任給は低く、デメリットの一つとしてあげられます。初任給低他業種からの転職となれば経験年数を加味したとしても、公務員になった直後は、収入が減少する可能性を想定しておく必要があるでしょう。
とは言え、初任給が低めでも、昇給率が民間とは異なるために、数年で逆転する可能性も高く、役職につくことで基本給も上がります。
住宅ローンのような継続的な支払いの予定がある人にとっては、転職後、数年の我慢が必要になるかもしれません。
5-2.異動移動や転勤がある
公務員薬剤師の業務におけるデメリットとして、2~3年周期で部署異動が行われることが挙げられます。
公務員は分野におけるスペシャリストを目指すのではなく、どんな業務にも対応できるジェネラリストを理想としています。そのため、基本的には、さまざまな部署を経験することになります。
部署異動は同じ施設内とは限らず、場合によっては転勤になってしまうこともあるでしょう。
地方公務員であれば、転勤になっても勤務している地域内でおさまりますが、国家公務員の場合は、全国規模で転勤の可能性があります。転勤が難しいという方は、地方公務員薬剤師を目指すのがいいでしょう。
5-3.公務員薬剤師の副業・兼業は可能?
公務員薬剤師は、地方公務員法や国家公務員法によって副業をおこなうことが禁止されています。それは、「国の奉仕者として公益性のために全力を尽くすため」です。しかし、2019年、一定の条件を満たす場合には、限定的ではありますが兼業が可能となりました。
例えば、国家公務員では、許可を得る必要がありますが、勤務時間外に非営利団体において責任者以外であれば兼業が可能です。また、地方公務員も、営利を目的とせず、公益性が高く、地域に貢献できる仕事であれば兼業できる自治体もあるようです。しかしながら、民間企業では、副業が認められる場合もありますので、その点では収入面などに影響が生じるといえるかもしれません。
6.公務員薬剤師に転職する方法
ここでは、薬剤師の方が、現在の仕事から公務員薬剤師に転職する方法について説明していきましょう。基本的には、国家公務員試験もしくは、地方公務員試験に合格する必要があります。
転職したい職種や勤務先によって、受けるべき試験や年齢制限、勤務経験が必要な場合など募集要項が異なるため、事前にしっかり準備を行いましょう。
6-1.国家公務員薬剤師の場合
国家公務員薬剤師、つまり薬系技官になるには、厚生労働省に入省するための国家公務員採用試験に合格しなければいけません。
受験するのは、国家公務員総合職試験(化学・生物・薬学)で、令和5年度の場合、3月1日から20日が受験申込期間でした。
例年、4月中に筆記試験の一次試験がおこなわれます。一次試験に合格すると5月に面接と論文の二次試験があります。その後、二次試験の合格者を対象として、6月に官庁訪問が実施されます。官庁訪問では、業務見学や職員との面接・グループディスカッションなどがおこなわれ、10月に最終合格発表、内定となります。
例年、採用人数は7~9人と狭き門で、非常に難易度が高い試験と言えます。
また、国家公務員薬剤師への転職の選択肢として、厚生労働省では、若干名の経験者を募集していることがあります。国の機関の係長級以上の官職で、主に厚生労働行政分野における、政策の企画・立案、施行などに係る行政事務に関わる仕事です。
薬剤師が応募するための要件は、薬剤師免許取得者で、大学卒業後、民間企業、官公庁、研究機関などにおいて、学歴に応じて次の勤務経験が必要です。
- 4年制大学卒業者・・・10年以上の勤務経験
- 6年制大学卒業者または大学院修士課程修了者・・・8年以上の勤務経験
- 大学院博士課程修了者・・・5年以上の勤務経験
ただし、採用予定日に60歳未満でなければ応募することができません。選考方法は一次試験が書類選考と論文提出、二次試験が面接です。
随時募集ですが、令和5年の場合、応募期限が5月8日、採用予定日が7月1日と非常にタイトなスケジュールとなっています。常に募集のアンテナを張っている必要があることや、採用が若干名であることから、転職としては難易度が高いと言えます。
参照元:人事院/総合職試験(院卒者・大卒程度)
参照元:厚生労働省/総合職 薬系技官 採用までのプロセスについて教えてください。
参照元:人事院/採用予定府省からのメッセージ
参照元:厚生労働省/厚生労働省薬系技官募集要領
6-2.地方公務員薬剤師の場合
地方公務員薬剤師に転職するためには、都道府県や市町村が実施する公務員試験に合格しなければいけません。この試験の内容や受験日程は、実施される自治体によって異なるため、希望している自治体の募集要項をチェックしておきましょう。
例えば令和5年の募集では、5~6月に自治体職員(薬剤師)として募集があります。令和6年に新卒で薬剤師資格取得見込みの学生と一緒に、経験者も応募することが可能です。
自治体の薬剤師募集の選考は、公務員試験のうち教養試験は廃止の傾向です。7月頃に、公務員として必要な見識、判断力、思考力などについての論文試験があり、9月頃に薬剤師や公務員としての適格性をみる面接、適性試験などの薬剤師選考試験および資格調査がおこなわれることが多いようです。合格すると「採用候補者名簿」に名前が掲載され、内定が出され、転職が可能となります。新卒者が令和6年4月採用なのに対し、転職の場合は年内に採用されることもあるようです。
公務員薬剤師の経験者の中途採用は必ずしもあるわけはないこと、年齢制限が自治体ごとに異なること、募集があっても人数は若干名であることから、狭き門であることは確かです。
また、公立病院が直接、病院職員として若干名の薬剤師を募集していることがあります。その場合、病院独自の採用試験となることもあります。公立病院勤務ですが、待遇は「地方公務員に準ずる」とされ、給与は病院の給与基準に基づくようです。
参照元:栃木県/栃木県職員採用選考候補者選定試験〔歯科技工士〕案内
参照元:大阪市/大阪市職員(薬剤師)採用試験要綱
参照元:石川県/令和6年度採用薬剤師選考試験案内
参照元:長野市/令和5年度採用 長野市職員採用試験受験案内
参照元:神奈川県/過去の試験・選考実施結果
6-3.麻薬取締官の場合
薬剤師が麻薬取締官に転職する場合、6月中旬~下旬に、現住所が管轄する麻薬取締部に、薬学系採用選考試験の受験を申し込みます。ただし、29歳以下でなければ受験することができないので注意が必要です。
一次試験は、各麻薬取締部ごとに日程は異なりますが、7月中旬~下旬にかけて、論文試験、適性検査及び面接試験がおこなわれます。その後、8月中旬に一次試験の合格者は関東信越厚生局麻薬取締部で実施される最終試験(面接)を受験し、採用予定者が決まります。配属は、申し込みの麻薬取締部の管轄でないこともあり、採用後は、一定の実務経験を積んだ後、麻薬取締官研修を修了すると、麻薬取締官に任命されます。
全国の麻薬取締部が、毎年、薬学系の麻薬取締官を募集するわけではありません。各年度の採用者数は男女合わせて、2020年10人、2021年9人、2022年10人と非常に難易度が高いことがわかります。
参照元:厚生労働省/麻薬取締部
参照元:厚生労働省 麻薬取締部/令和5年度麻薬取締官採用試験(薬学系選考採用試験)について
参照元:職業情報提供サイト/麻薬取締官
参照元:厚生労働省 麻薬取締部/採用内定者数一覧
7.公務員薬剤師に転職する際のポイントや注意点
公務員薬剤師への転職を検討するにあたっては、以下の2点に注意する必要があります。
7-1.年齢制限がある
公務員薬剤師への転職を検討する場合、年齢制限がある職種があるので、注意が必要です。年齢制限は国家公務員試験の場合が30歳まで、地方公務員は20代後半~30代前半と各自治体によってばらつきがあるので、受験する自治体の受験資格を確認しておきましょう。公務員薬剤師への転職を希望するなら、早めに活動を始める必要があるということです。
7-2.募集人数が少ない
公務員薬剤師は、民間とは異なり、そもそも募集人数が多くありません。
例として、平成28年度から令和3年度までにおける厚生労働省の薬系技官の採用実績は各年度8~9名程度です。狭き門になることは覚悟しておいたほうがいいでしょう。
7-3.転職エージェントを活用する
公務員薬剤師に転職を検討する時のポイントとして、転職エージェントを活用することをおすすめします。それは、公務員薬剤師に転職するには、いくつものハードルがあるからです。
例えば、公務員試験を受ける必要があるため、応募の時期が限られていることや、応募要項には年齢制限や、経験年数が必要なケースがあることです。
また、もともと募集人員が非常に限られており、公務員薬剤師に転職するには、高いアンテナを張っている必要があるのです。薬剤師として日々働いている方が、常にアンテナを張っているのは難しいかもしれません。
転職エージェントは、一般の転職先も含めてあらゆる薬剤師の募集の情報を持っています。公務員薬剤師の募集時期や職種など、タイミング良く紹介してくれることは間違いありません。
転職を検討したら、ひとりで考えずに、マイナビ薬剤師のキャリアアドバイザーに相談してみましょう。
8.まとめ
ここまで紹介してきたように、公務員薬剤師、特に国家公務員薬剤師は国家公務員試験という難関があり、その後も一般の薬剤師とは全く異なったキャリアを重ねていくことになるため、転職の選択肢としては難しいと言えるかもしれません。
一方、地方公務員薬剤師は、薬学の専門知識や大学で習得した技術などを活かして、自治体の薬務課、保健所、衛生研究所への転職の可能性は、少なからずあるといえるのではないでしょうか。
公務員薬剤師への転職は、いつでも良いというわけではありません。転職の選択肢として、公務員薬剤師を検討する場合には、早めに決断する必要と、情報収集やアドバイスを受けるためにも、転職エージェントへの相談をおすすめします。
毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報
転職準備のQ&A
薬剤師の職場のことに関するその他の記事
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554