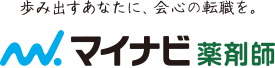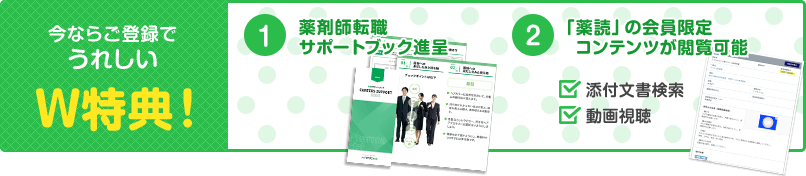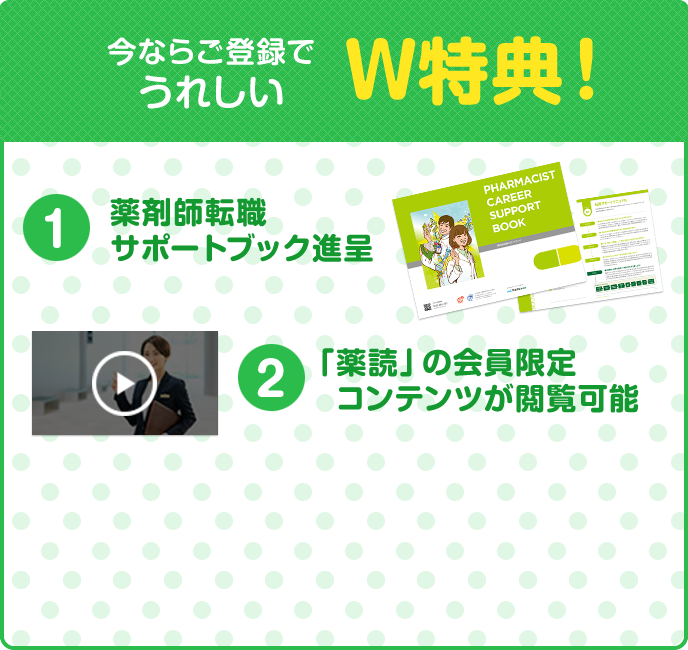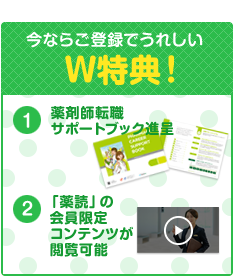【最新版】登録販売者は難しい?合格率や試験の難易度、資格取得のポイントもご紹介

登録販売者とは、風邪薬や鎮痛薬などの一般用医薬品(第2類・第3類)を販売するための資格です。
2009年に誕生した比較的新しい資格で、ドラッグストアなどでは登録販売者を配置することで薬剤師がいなくても一般用医薬品(第2類・第3類)を販売できるようになるため、業界内で高い需要があります。
そのため、時給UPや年収UPを目指しやすい資格であり、実務経験がなくても受験が可能なので、ここ最近人気が高まってきています。
今回はその登録販売者の資格試験の内容や資格を取得するうえでのポイントをご紹介します。
1.登録販売者試験の難易度は?
登録販売者は薬局・ドラッグストア業界で働くにはプラスになる資格の一つですが、資格取得の難易度はどうなのでしょうか。同じ業界で働く薬剤師や調剤事務管理士の資格とも比較しながら、難易度をご説明します。
1.1.登録販売者試験の合格基準
登録販売者になるには、各都道府県で年1回行われている試験に合格する必要があります。この試験の合格基準は、「受験者の上位何%までが合格」と決められているわけではなく、試験問題のうち全体の70%以上を正答し、かつ各試験項目で都道府県知事が定める一定割合以上を正答すれば合格となります。この基準は都道府県ごとに異なりますが、35%~40%程度が目安です。
以前は「医薬品販売の実務経験が1年以上」など、受験要件が定められていましたが、2015年にその決まりが撤廃され、実務経験や学歴を問わず、誰でも受験できるようになりました。
1.2.薬剤師との難易度の違い
薬剤師は、医師の処方箋をもとに「医療用医薬品」の調剤を行うほか、薬局やドラッグストアで売っている「一般用医薬品」(使用に注意を要する第1類を含む)全品目を扱わなければなりません。
一方、登録販売者は調剤は行えず、「一般用医薬品」も比較的安全性の高い第2類と第3類のみを扱います。
扱う医薬品の品目数だけで考えても、登録販売者は薬剤師の10分の1以下であるため、薬剤師と比較すると登録販売者の方が試験の難易度は低いといえるでしょう。
しかも、薬剤師の国家試験を受けるためには、まず薬科大学もしくは総合大学の薬学部に入学し、6年間勉強や研究、実務実習を行い、卒業後に薬剤師国家試験に合格しなければなりません。
一方、登録販売者の試験は学歴や実務経験を問わず誰でも受けられますから、受験資格を手に入れるまでの時間、学費などの費用、勉強量などのハードルは、薬剤師と比較すると登録販売者の方が低いといえます。
1.3.調剤事務管理士との難易度の違い
調剤事務管理士の試験では、登録販売者同様、特別な受験資格は求められません。試験内容は、医療保険制度や調剤報酬点数の算定、薬剤用語の知識などを問う学科試験と、レセプトの作成・点検のために必要な知識を問う実技試験の2部構成です。
調剤事務管理士の試験は、新型コロナウイルスの感染拡大以降は、一般会場試験ではなく在宅試験となっています。自宅で資料を参考にしながら答案を作成することができるので、暗記を問われることはありませんし、独学で合格することも可能です。
在宅試験は、毎月第4土曜日翌日の日曜日に実施されています。年に12回も受験のチャンスがあり、合格率も60%を程度であることを考えると、登録販売者の資格の方が難易度は高いといえるでしょう。
1.4.登録販売者は取得しやすい資格
登録販売者は、厚生労働省が定める国の資格制度の中では比較的取得しやすい資格です。1番のポイントは受験資格を必要としないことです。医師や薬剤師のように6年間の大学生活を勉強に費やし、巨額の学費を投資しなくても受験することができます。
登録販売者試験の合格率は全国平均で40%程度ですが、しっかりと試験対策をすれば合格は可能です。その後のキャリアにも活かしやすいので、登録販売者人口が増えすぎる前に資格を取得することをおすすめします。
これから登録販売者になろうと検討している方で、登録販売者の基本情報が知りたいのであれば、まずはこちらの記事もチェックしてみてもよいでしょう。
正式な登録販売者として働くためには、試験に合格するのはもちろん、実務経験が直近5年の間に2年以上であること等、必ずチェックしておきたい情報を紹介しています。
その他、登録販売者として働く際の就職先も紹介しているので参考にしてみて下さい。
2.登録販売者試験の合格率はどのくらい?
登録販売者試験の合格率は、全国平均でみると常に40%台で推移しています。しかし、都道府県別にみると20~60%前後と非常にばらつきが大きく、一概に40%とは言いがたいのが実情です。
2017~2022年 登録販売者試験合格率
| 試験実施年 | 平均合格率 | 最低合格率 | 最高合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 44.4% | 29.8% | 59.3% |
| 2021年 | 49.3% | 32.7% | 68.8% |
| 2020年 | 41.5% | 30.1% | 58.1% |
| 2019年 | 43.4% | 23.4% | 64.3% |
| 2018年 | 41.3% | 19.5% | 58.6% |
| 2017年 | 43.5% | 26.7% | 62.4% |
▼出典
参照元:厚生労働省/これまでの登録販売者試験実施状況等について
2.1.合格率の推移と今後の受験者数
受験資格が緩和される前年の2014年は、受験者数31,362人、全国平均合格率は43.5%でした。
ですが2015年に受験資格が緩和されると、受験者数は一気に約5万人まで急増しました。このときの全国平均合格率は45.9%を記録しています。
その後も受験者数は約5.3万人、約6.1万人、約6.5万人と年を追うごとに増え続けましたが、近年は2019年度をピークにやや減少傾向にあるようです。
2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための移動制限の施策を受けて、他の都道府県からの受験を制限した自治体があったことや、試験日程の延期などがあり、2019年度と比べ受験者数は約1.2万人減少し約5.3万人となりました。
2021年度は、2020年度と同様、在住、在勤、または通学している自治体での受験がすすめられていましたが、受験者数は約6万人と2020年度よりも約8,000人 増加しました。しかし、2022年は受験者数約5.5万人と、前年よりも約5,000人 減少しています。
とはいえ、新型コロナウイルスの感染拡大以降ドラッグストア業界は市場規模が拡大し続けており、薬の専門家である登録販売者の需要も高まっています。さらに近年は、ドラッグストアや薬局で一般用薬品を購入して自分の健康を管理するセルフメディケーションも広がっています。医療用から一般薬へのスイッチOTC薬も増えているため、今後は登録販売者の活躍の場より広がっていくと考えられます。
2023年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために他の都道府県からの受験を制限する自治体はほとんど見られなくなっていますので、受験者数も増えていくのではないでしょうか。
2017~2022年登録販売者試験受験者数と合格率
| 年代 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 55,606 | 24,707 | 44.4% |
| 2021年 | 61,070 | 30,082 | 49.3% |
| 2020年 | 52,959 | 21,953 | 41.5% |
| 2019年 | 65,288 | 28,328 | 43.4% |
| 2018年 | 65,500 | 27,022 | 41.3% |
| 2017年 | 61,126 | 26,606 | 43.5% |
2.2.都道府県別の合格率
合格率を都道府県別にみると、以前は北海道と東北6県が上位を占めることが多かったのですが、近年は実施年度によってばらつきが見られるようになっています。
2020年度は前述の通り特殊な状況下での試験となった影響もあってか、前半の8~9月に試験が行われた東北各県および関西広域連合(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県)の合格率が低くなりました。また後半の試験日程は12月に集中しましたが、前半に比べると高い合格率となりました。
2021年度はこれまで上位に入ることが多かった秋田県が最下位となり、中国・四国地区の合格率が高くなっています。また、2022年度は、九州・沖縄のすべての県が全国平均を上回る結果となるなど、実施年度によって合格率の順位も変動していることがわかります。
2017~2022年度 登録販売者試験 都道府県別合格率
| 都道府県 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 52.0% | 42.4% | 47.4% | 64.3% | 58.6% | 62.4% |
| 青森県 | 48.8% | 39.4% | 43.1% | 61.0% | 49.8% | 54.2% |
| 岩手県 | 41.6% | 41.3% | 50.1% | 56.9% | 50.6% | 57.4% |
| 宮城県 | 49.4% | 43.4% | 44.2% | 61.9% | 56.6% | 62.1% |
| 秋田県 | 40.7% | 32.7% | 39.1% | 57.0% | 49.0% | 60.5% |
| 山形県 | 43.3% | 38.5% | 44.4% | 60.0% | 52.8% | 58.0% |
| 福島県 | 42.0% | 35.4% | 34.1% | 59.2% | 47.5% | 56.7% |
| 茨城県 | 48.3% | 47.8% | 44.0% | 35.5% | 37.3% | 33.7% |
| 栃木県 | 43.4% | 42.8% | 43.1% | 32.1% | 35.6% | 30.5% |
| 群馬県 | 57.1% | 50.9% | 46.6% | 34.6% | 36.0% | 32.4% |
| 埼玉県 | 40.1% | 40.8% | 30.1% | 23.4% | 32.0% | 38.4% |
| 千葉県 | 39.8% | 41.4% | 34.4% | 24.8% | 36.0% | 40.5% |
| 東京都 | 41.5% | 43.2% | 33.0% | 26.0% | 35.4% | 42.7% |
| 神奈川県 | 44.6% | 48.8% | 38.7% | 28.2% | 39.4% | 46.7% |
| 新潟県 | 50.4% | 46.2% | 37.6% | 35.8% | 41.8% | 33.3% |
| 山梨県 | 56.1% | 44.5% | 32.1% | 38.4% | 37.2% | 32.6% |
| 長野県 | 50.0% | 46.1% | 31.8% | 31.9% | 37.5% | 30.1% |
| 富山県 | 40.8% | 53.3% | 43.5% | 43.7% | 35.5% | 49.1% |
| 石川県 | 40.5% | 51.9% | 43.1% | 37.1% | 34.6% | 44.0% |
| 福井県 | 30.6% | 48.8% | 34.8% | 40.7% | 19.5% | 37.4% |
| 岐阜県 | 40.5% | 53.0% | 46.2% | 42.3% | 37.2% | 47.7% |
| 静岡県 | 46.1% | 57.0% | 50.4% | 53.2% | 47.4% | 56.4% |
| 愛知県 | 43.5% | 59.1% | 56.0% | 48.4% | 42.0% | 50.3% |
| 三重県 | 44.8% | 52.2% | 53.1% | 47.5% | 44.2% | 51.4% |
| 滋賀県 | 35.1%* | 56.3%* | 39.7% * | 58.8% * | 29.3% | 41.6% |
| 京都府 | 35.1%* | 56.3%* | 39.7% * | 58.8% * | 38.6% | 51.7% |
| 大阪府 | 35.1%* | 56.3%* | 39.7% * | 58.8% * | 48.4% | 49.7% |
| 兵庫県 | 35.1%* | 56.3%* | 39.7% * | 58.8% * | 36.2% | 51.3% |
| 奈良県 | 47.8% | 48.9% | 35.5% | 57.5% | 41.6% | 51.7% |
| 和歌山県 | 35.1%* | 56.3%* | 39.7% * | 58.8% * | 30.9% | 38.9% |
| 鳥取県 | 37.3% | 60.4% | 38.5% | 29.6% | 28.5% | 27.1% |
| 島根県 | 33.8% | 57.4% | 50.0% | 39.6% | 30.6% | 31.3% |
| 岡山県 | 39.3% | 64.9% | 49.4% | 34.3% | 28.4% | 27.5% |
| 広島県 | 42.7% | 66.7% | 58.1% | 46.6% | 34.4% | 36.9% |
| 山口県 | 43.9% | 68.8% | 54.0% | 37.1% | 30.6% | 27.1% |
| 徳島県 | 35.1%* | 56.3%* | 39.7% * | 58.8% * | 32.5% | 44.7% |
| 香川県 | 43.7% | 63.6% | 50.6% | 31.7% | 38.7% | 45.0% |
| 愛媛県 | 38.7% | 64.6% | 48.2% | 34.0% | 36.0% | 39.5% |
| 高知県 | 29.8% | 52.4% | 39.7% | 25.0% | 34.7% | 33.6% |
| 福岡県 | 58.3% | 48.6% | 43.5% | 44.2% | 52.7% | 33.5% |
| 佐賀県 | 59.3% | 39.4% | 39.7% | 42.1% | 48.8% | 29.7% |
| 長崎県 | 55.2% | 44.0% | 41.8% | 48.2% | 55.5% | 33.0% |
| 熊本県 | 54.2% | 43.9% | 43.2% | 40.9% | 57.0% | 34.0% |
| 大分県 | 58.1% | 43.4% | 46.8% | 46.2% | 51.1% | 34.8% |
| 宮崎県 | 53.3% | 42.9% | 35.3% | 39.3% | 46.1% | 34.1% |
| 鹿児島県 | 50.7% | 35.1% | 36.5% | 35.4% | 43.9% | 32.1% |
| 沖縄県 | 44.6% | 37.0% | 35.9% | 30.9% | 46.1% | 26.7% |
▼出典
参照元:厚生労働省/これまでの登録販売者試験実施状況等について
2-3.都道府県で合格率が高い地域、低い地域
数年前までは、合格率が高い地域といえば北海道と東北6県でした。特に北海道は数年間1位の座を守り続けていましたが、2020年度以降はベスト5にも入っていません。2021年にはこれまで上位に入ることが多かった秋田県が47位、福島県が45位、山形県が43位という結果となっています。2022年度はやや持ち直していますが、合格率が高い地域とはいえなくなってきている状況です。
近畿関西地区は、2019年に関西広域連合として統一試験を実施するや6位に急浮上、合格率は58.8%に跳ね上がりました。しかし、2022年度は44位となっており、こちらも合格率が高い地域とは言い切れません。
合格率ベスト5
| 年代 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐賀県59.3% | 山口県68.8% | 広島県 58.1% | 北海道 64.3% | 北海道 58.6% |
| 2位 | 福岡県58.3% | 広島県66.7% | 愛知県 56.0% | 宮城県 61.9% | 熊本県 57.0% |
| 3位 | 大分県58.1% | 岡山県64.9% | 山口県 54.0% | 青森県 61.0% | 宮城県 56.6% |
| 4位 | 群馬県57.1% | 愛媛県64.6% | 三重県 53.1% | 山形県 60.0% | 長崎県 55.5% |
| 5位 | 山梨県56.1% | 香川県63.6% | 香川県 50.6% | 福島県 59.2% | 山形県 52.8% |
合格率ワースト5
| 年代 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47位 | 高知県29.8% | 秋田県32.7% | 埼玉県 30.1% | 埼玉県 23.4% | 福井県 19.5% |
| 46位 | 福井県30.6% | 鹿児島県35.1% | 長野県 31.8% | 千葉県 24.8% | 岡山県 28.4% |
| 45位 | 島根県33.8% | 福島県35.4% | 山梨県 32.1% | 高知県 25.0% | 鳥取県 28.5% |
| 44位 | 関西広域連合35.1% | 沖縄県37.0% | 東京都 33.0% | 東京都 26.0% | 滋賀県 29.3% |
| 43位 | 鳥取県37.3% | 山形県38.5% | 福島県 34.1% | 神奈川県 28.2% | 島根県 30.6% |
関東地区の合格率は、近年緩やかに上昇しているようです。2019年と2020年に2年連続でワースト5入りとなった東京都と埼玉県も、2021年以降は合格率40%を超えています。
また、2021年度は四国・中国地区が、2022年度は九州・沖縄の合格率が特に高くなっています。このように、実施年度によってまったく違う順位となっているため、一概に「合格率が高い・低い地域はここ」とはいえないのが現状です。
登録販売者試験の問題は厚生労働省が発行する「試験問題の作成に関する手引き」をもとに各都道府県が作成します。この手引きは必要に応じて年に1回改訂されており、2023年7月時点では令和5年4月版が最新となっています。
改定が行われると、その前年までのテキストや問題集が使用できなくなり、新たに改訂されたテキストで学習しなおさなければならなくなるので、注意が必要です。
受験に際しては、自分が受験する都道府県のウェブサイトに掲載されている過去問題を解いておくことで、その自治体の出題傾向が把握できます。しかし、大幅な改定後は過去問が役に立たなくなる可能性がありますので、やはり厚生労働省のウェブサイトに掲載されている最新の「試験問題の作成に関する手引き」を活用して勉強することをおすすめします。
3.登録販売者試験の概要
登録販売者試験の出題範囲や今後の試験日について詳しくご紹介します。
3.1.試験の申込方法
登録販売者試験を受験するには、受験願書(受験申請書という自治体もある)を各自治体から入手し、決められた手順に則り期日までに受験手数料を納付し申請を済ませます。
3.1.1.申請書の入手方法
各自治体によって異なるので注意が必要です。大きく分けて、次のようなパターンがあります。
1)各自治体のホームページからダウンロード
2)郵送で取り寄せ
3)指定場所で受け取り
近年は電子申請を受け付けている自治体もあります。電子申請の場合は紙の申込書は不要ですので、重複しないように注意しましょう。
3.1.2.試験の公示時期
試験の公示時期は毎年変わるので、登録販売者の受験を考えたら、受験する自治体のホームページを確認しましょう。
2023年度の場合、東日本では5月初旬~中旬(千葉県は5月2日) 以降に試験の実施が公示され、申請書の配布と申請受付は6月初旬~下旬頃まで行われていました 。2023年の試験日は北海道・東北が8月30日、関東・甲信越は8月29日または9月10日、東海・北陸は9月6日に実施される予定です(福井県のみ8月27日)。
西日本の公示日は中国・四国が6月2日、近畿・関西広域連合は5~6月、九州・沖縄は5月~6月中旬でした。試験日は関西広域連合が8月27日、奈良県は9月24日、中国・四国は10月17日、九州・沖縄が12月10日です。
3.1.3.受付期間と方法
申請(願書)の受付期間も自治体によって異なります。10日~2週間程度としている自治体が多いですが、静岡県の受付期間は月曜日から金曜日までの5日間のみとしており、提出方法も持参のみで郵送は受け付けていません。
一方で、受付は簡易書留による郵送のみとしている自治体や、電子申請が可能な自治体もあります。
提出書類に不備や不足があると受け付けてもらえない可能性がありますので、受験する自治体の受験案内をよく読み、指定された手順で時間に余裕をもって申請するようにしましょう。また、受験する年の4月になったら、受験を希望する自治体のホームページをこまめにチェックするようにしましょう。
3.1.4.受験手数料
受験手数料も各都道府県によって異なりますので、事前に調べておくと良いでしょう。ちなみに、北海道と東北6県の受験手数料は他の都府県に比べて高額で、北海道18,200円、青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島の各県は17,600円となっています。最も安いのは関西広域連合で、12,800円です。
3.2.出題範囲
登録販売者試験の出題範囲は全部で5章に分かれています。
第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」
「医薬品とは何なのか?」にはじまり、成分の効き方や安全性に影響する要因、薬害の歴史なども出題されます。一般常識で答えられるような問題が出ることもあります。
第2章「人体の動きと医薬品」
人間の体の構造や働き、薬が体内で働く仕組み、副作用の症状に関する知識について出題されます。
第3章「主な医薬品とその作用」
一般用医薬品で用いられる主な有効成分についての知識や購入者に情報提供すべきことなど、実践的な知識が問われる問題が出題されます。
一番問題数が多く覚える量も他の章に比べて多いので、この分野でどれだけ得点できるかが合格の鍵になってきます。
第4章「薬事関連法規・制度」
医薬品販売業の許可、医薬品の取り扱い、リスク分類、販売に関する法令などについて出題されます。他の章と比べてイメージがつきにくい分野です。法律の名称など漢字の羅列が大半なので、医薬品には興味があってもこの分野は苦手だと感じる人も多いです。
第5章「医薬品の適正使用・安全対策」
添付文書の読み方や医薬品副作用被害救済制度などについて問われます。より実務的な問題になっているので、3章や4章の知識が頭に入ってからは取り組みやすい分野といえます。
▼参照元
登録販売者試験実施要領
3.3.試験内容・試験時間
試験の概要について説明します。
3.3.1.試験方法
登録販売者試験はマークシートを使用した選択式の試験で、休憩をはさんで60問/120分ずつに分けて行われます。午前と午後に分ける自治体もあれば、午後から夕方にかけて前半・後半に分けて行う自治体もあります。
また、試験科目は前述の通り、第1章から第5章まで5つありますが、試験はこの順番通りに行われるとは限りません。どの項目を前半・後半で行うかは自治体によって異なりますので、当日のスケジュールはしっかり確認しておきましょう。
試験科目ごとの問題数と試験時間は以下の通りです。
3.3.2.試験時間
- 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問/40分
- 人体の働きと医薬品:20問/40分
- 主な医薬品とその作用:40問/80分
- 薬事関係法規・制度:20問/40分
- 医薬品の適正使用・安全対策:20問/40分
- 合計 120問 /240分
3.3.3.合格基準
厚生労働省が公示している「登録販売者試験実施要領」では合格基準は以下の通りです。
- 総出題数に対して7割程度の正答率であること
- 試験項目ごとに都道府県知事が定める一定割合以上の正答があること
としていますが、 「都道府県知事が定める一定割合以上の正答」については、おおむね「35~40%以上の正答」が基準とされているようです。
3.4.2023年の試験日程と2024年以降の試験について
2022年度までは新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、受験者を在住、通勤または通学している人に限定する自治体もありましたが、2023年度はそのような受験制限を設けている自治体は見られません。滑り止めとして複数の県で試験を受けることもできます。
2023年度の登録販売者試験は、以下の通り実施されます。なお、九州・沖縄の受付期間と合格発表については、7月~8月頃に公表される予定です。
また、2024年度以降の試験については、該当年度の自治体からの発表をお待ちください。
2023年度登録販売者試験実施状況
| 都道府県 | 試験日時 | 受付期間 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 令和5年8月30日(水) | 令和5年6月6日(火)~6月27日(火) | 令和5年10月3日(火) |
| 青森県 | 令和5年8月30日(水) | 令和5年6月21日(水)~6月27日(火) | 令和5年10月3日(火) |
| 岩手県 | 令和5年8月30日(水) | 令和5年6月14日(水)~6月27日(火) | 令和5年10月3日(火) |
| 宮城県 | 令和5年8月30日(水) | 令和5年6月5日(月)~6月27日(火) | 令和5年10月3日(火) |
| 秋田県 | 令和5年8月30日(水) | 令和5年6月6日(火)~6月27日(火) | 令和5年10月3日(火) |
| 山形県 | 令和5年8月30日(水) | 令和5年6月6日(火)~6月27日(火) | 令和5年10月3日(火) |
| 福島県 | 令和5年8月30日(水) | 令和5年5月30日(火)~6月27日(火) | 令和5年10月3日(火) |
| 茨城県 | 令和5年8月29日(火) | 令和5年6月7日(水)~6月20日(火) | 令和5年10月6日(金) |
| 栃木県 | 令和5年8月29日(火) | 令和5年6月12日(月)~6月21日(水) | 令和5年10月6日(金) |
| 群馬県 | 令和5年8月29日(火) | 令和5年5月25日(木)~6月8日(木) | 令和5年10月6日(金) |
| 埼玉県 | 令和5年9月10日(日) | 令和5年5月23日(火)~6月2日(金) | 令和5年10月20日(金) |
| 千葉県 | 令和5年9月10日(日) | 令和5年5月22日(月)~6月9日(金) | 令和5年10月20日(金) |
| 東京都 | 令和5年9月10日(日) | 令和5年5月22日(月)~6月9日(金) | 令和5年10月20日(金) |
| 神奈川県 | 令和5年9月10日(日) | 令和5年5月22日(月)~6月9日(金) | 令和5年10月20日(金) |
| 新潟県 | 令和5年8月29日(火) | 令和5年6月1日(木)~6月15日(木) | 令和5年10月6日(金) |
| 山梨県 | 令和5年8月29日(火) | 令和5年6月5日(月)~6月16日(金) | 令和5年10月6日(金) |
| 長野県 | 令和5年8月29日(火) | 令和5年5月22日(月)~6月2日(金) | 令和5年10月6日(金) |
| 富山県 | 令和5年9月6日(水) | 令和5年6月5日(月)~6月16日(金) | 令和5年10月20日(金) |
| 石川県 | 令和5年9月6日(水) | 令和5年6月5日(月)~6月16日(金) | 令和5年10月20日(金) |
| 岐阜県 | 令和5年9月6日(水) | 令和5年6月5日(月)~6月16日(金) | 令和5年10月20日(金) |
| 静岡県 | 令和5年9月6日(水) | 令和5年6月5日(月)~6月9日(金) | 令和5年10月20日(金) |
| 愛知県 | 令和5年9月6日(水) | 令和5年6月12日(月)~6月16日(金) | 令和5年10月20日(金) |
| 三重県 | 令和5年9月6日(水) | 令和5年6月12日(月)~6月23日(金) | 令和5年10月20日(金) |
| 福井県 | 令和5年8月27日(日) | 令和5年5月29日(月)~6月12日(月) | 令和5年10月2日(月) |
| 奈良県 | 令和5年9月24日(日) | 令和5年6月8日(木)~6月14日(水) | 令和5年11月21日(火) |
| 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県 | 令和5年8月27日(日) | 令和5年5月29日(月)~6月12日(月) | 令和5年10月2日(月) |
| 鳥取県 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年7月10日(月)~7月24日(月) | 令和5年11月28日(火) |
| 島根県 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年7月10日(月)~7月24日(月) | 令和5年11月28日(火) |
| 岡山県 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年7月10日(月)~7月24日(月) | 令和5年11月28日(火) |
| 広島県 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年7月10日(月)~7月24日(月) | 令和5年11月28日(火) |
| 山口県 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年7月10日(月)~7月24日(月) | 令和5年11月28日(火) |
| 香川県 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年7月10日(月)~7月24日(月) | 令和5年11月28日(火) |
| 愛媛県 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年7月10日(月)~7月24日(月) | 令和5年11月28日(火) |
| 高知県 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年7月10日(月)~7月24日(月) | 令和5年11月28日(火) |
| 福岡県 | 令和5年12月10日(日) | ※公表前 | ※公表前 |
| 佐賀県 | 令和5年12月10日(日) | ※公表前 | ※公表前 |
| 長崎県 | 令和5年12月10日(日) | ※公表前 | ※公表前 |
| 熊本県 | 令和5年12月10日(日) | ※公表前 | ※公表前 |
| 大分県 | 令和5年12月10日(日) | ※公表前 | ※公表前 |
| 宮崎県 | 令和5年12月10日(日) | ※公表前 | ※公表前 |
| 鹿児島県 | 令和5年12月10日(日) | ※公表前 | ※公表前 |
| 沖縄県 | 令和5年12月10日(日) | ※公表前 | ※公表前 |
4.資格取得にあたってのポイント
登録販売者の資格を取得したいと考えても、「働きながらだと勉強できないのではないか」「スクールに通う費用が気になる」という不安を抱えている方もいるかと思います。
しかし、登録販売者試験は働きながらでも対策講座を受講しやすいですし、独学でも合格することは可能です。働きながら独学など、資格取得する際のポイントをご紹介します。
4.1.働きながらの取得は可能か?
登録販売者は、働きながらでも取得することが可能です。試験日は都道府県によさまざまで、平日の場合も土日の場合もあります。日程は早い段階で確認ができますし、1日で終わる試験のため、働いている方でも取得しやすいと思います。
また、登録販売者試験の受験対策講座を受講する場合は、受講日は土日に設けられていることが多いです。
平日に働いている方にとっては、土日に講座を受けられるので登録販売者試験の勉強に集中することができます。
4.2.独学でも取得可能?
登録販売者の資格は、独学でも取得することが可能です。市販のテキストや過去問題集があるので、しっかりとポイントを押さえておけば特別なスクールに通わなくても試験に合格できます。
余計な費用を掛けたくない、自分で勉強のスケジュールを立てたいという方には独学がおすすめです。
独学で合格を目指すなら、まずはこちらの記事で勉強方法を把握してみましょう。
登録販売者の試験は暗記中心ですが、出題範囲も広いため勉強方法にも工夫が必要になります。
あらかじめ出題傾向や出題範囲について把握しておきましょう。
4.3.振替受講の制度を知っておく
受験対策講座を受ける場合、仕事や急な予定により授業に出席できない日があると思います。
その場合、無料で他のクラスへの振り返えができるスクールもあります。仕事や家庭の両立などで忙しい方にもうれしい制度です。受験対策講座を受講する場合は事前に振替受講の制度も確認しましょう。
5.登録販売者の資格勉強する際のコツ
登録販売者試験に合格するために、どんな勉強法が良いのでしょうか。効率的に勉強するコツを紹介します。
5.1.受験地のブロックに合わせた対策
登録販売者試験は、基本的にはブロックごとに同じ試験問題となっています。自分が受けようと思う都道府県が、どのブロックなのか調べてみましょう。ブロックごとに難易度や問題の傾向、合格率も違います。受験地予定のブロックの問題の傾向を知り、過去問を使うことが効率的な勉強につながります。
5.2.苦手な分野を克服する
合格基準は配点を各問1点とし、以下の2つの基準の両方を満たす場合です。
1.総出題数(120問)に対する正答率が7割以上(84点以上)
2.試験項目ごとの出題数に対する正答率が、都道府県知事が定める一定割合(35%~40%)以上
つまり、全体で7割以上取っていても、苦手な分野が35%~40%に満たない場合、不合格になります。過去問で苦手な分野を見つけて、力を入れて克服しておきましょう。
5.3.改訂部分に気を付ける
出題範囲は、厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題されます。改訂がある場合には、間違って覚えてしまうと失敗につながるので、最初にチェックすることが大切です。
5.4.受験予定ブロックの過去問を徹底的に解く
最初からテキストを読んでも、なかなか頭に入らないことも多いでしょう。過去問を解いて答えを覚えることを繰り返します。何度繰り返しても、間違えてしまう自分の傾向を知り、その部分を集中的に勉強することも効率的です。
受験直前になったら、過去問を利用して、受験時間内で解く練習もしましょう。
5.5.時間を上手に使って効率を上げる
どんな勉強でも同じですが、効率的に時間を使うことが大切です。通勤・通学の時間や早起きが得意な方は朝、夜型の方は夜寝る前のすき間時間など、日常生活の一部として無理なく毎日取り組むことが勉強を続けるコツです。
5.6.身近な薬や体の情報の積み重ね
薬のパッケージや添付文書には、成分の効能・効果や副作用などが、分かりやすく書いてあるので、注意して見るようにしましょう。また、病気や体の情報にもアンテナを張って、身近な生活の中から知識を増やすことが大切です。
例えば家族の体調や病気について興味のあるものを調べてみるのも良いでしょう。身近な情報の積み重ねが、テキストや過去問に向き合った時につながります。
6.試験当日に気をつけることは?
試験当日の注意点をまとめました。
6.1.持参するもの
試験当日に持参するものについては、受験案内の留意(注意)事項の欄に書かれていることが多いので、あらかじめよく読んでおきましょう。
必ず忘れてはいけないのが、受験票と筆記用具です。筆記用具は、シャープペンシルも可としている自治体もあれば、「HBの黒鉛筆」と指定している自治体もありますので注意しましょう。消しゴムも忘れずに持参してください。
そのほか、自治体によっては時計(翻訳や計算、メール機能などが無いもの)や、「大きな靴音がしない靴」と履き物が指定されていることもあります。
また、「具合が悪いときはマスク着用をお願いすることもある」と記載のある自治体もありますので、念のためにマスクも持参しておくと安心です。
6.2.体調管理
2023年度は、試験当日に風邪の症状(発熱、咳など)、倦怠感(強いだるさ)、呼吸困難(息苦しい)などの症状がある場合には受験を控えるよう呼び掛けている自治体が多く見られます。試験会場で検温をされる場合や、マスクの着用をお願いされることもあるかもしれません。受験する自治体のウェブサイトや受験案内をよく読み、試験当日の留意(注意)事項を確認しておきましょう。
周囲の人にウイルスや風をうつさないためにも、試験前の体調管理はいつも以上に注意深くする必要があります。
6.3.その他
自家用車やバイクなどで会場に行き、違法駐車などの迷惑行為が発覚した場合には、受験資格や合格の取り消しとなる場合があります。会場へは公共交通機関を使用し、時間に余裕をもって出発しましょう。
2021年以降の試験も新型コロナウイルスの感染再拡大や、大雨、台風などで試験が延期や中止となる場合があります。出発前に自治体のウェブサイトなどで試験の開催を確認しておくことをおすすめします。
7.まとめ
登録販売者の資格は、薬剤師と比較すると難易度は低く、比較的取得しやすい資格という事が分かりました。また、合格率は40%程度ですが、準備をしっかりと行えば合格も可能です。
資格取得のポイントや勉強のコツを踏まえ、スクールや独学で試験の傾向や対策を進めていくことが大切です。
登録販売者に関するその他の記事
登録販売者の求人一覧
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554