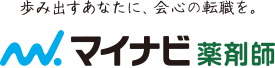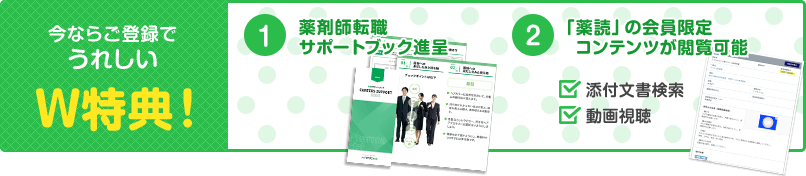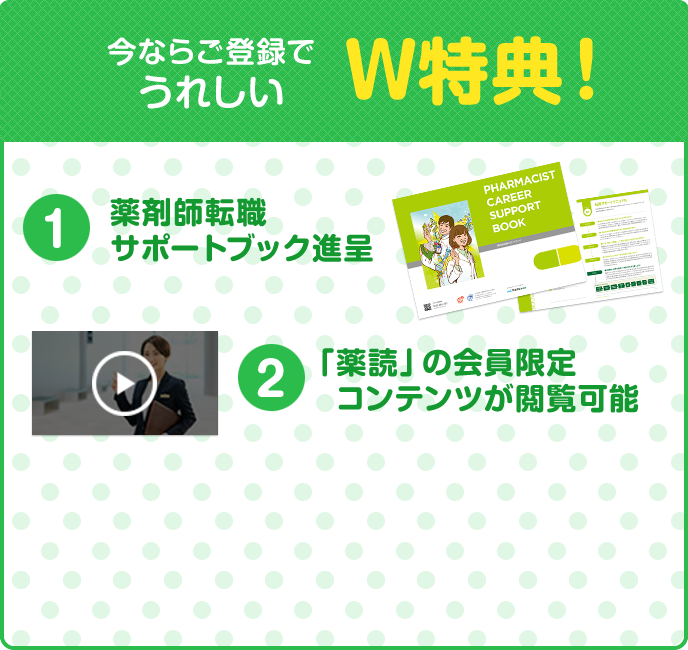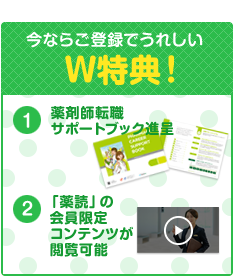登録販売者は実務経験が必要?昔と現在の変化や雇用形態とは

登録販売者になるためには、まず年に1回実施される登録販売者試験に合格しなければなりません。しかし、登録販売者として実際に就業するためには、実務経験や登録の手続きなどが必要です。
ここでは、登録販売者として働くために必要な実務経験の内容、「販売従事登録」の手続きなどを詳しく解説します。
<訂正:2023年10月>
本記事において、登録販売者を国家資格とする表記がございました。お詫びして訂正いたします。
目次
1.登録販売者の「実務経験」の必要性
登録販売者として従事するためには「実務経験」が必要ですが、平成26年の「薬事法の一部を改正する法律」の施行以前と現在では、その意味するところが異なります。
1-1. 平成26年度以前は実務経験が受験資格に必要だった
平成26年度までの登録販売者試験では、「高校卒業以上で、1年以上一般用医薬品の販売などに関する実務に従事した者」という受験資格が設けられていました。つまり、実務経験は、登録販売者の受験資格として必要だったのです。
1-2. 現在では就業のために必要
平成26年の制度改正により登録販売者試験の受験資格は廃止になりましたが、合格後に正規の登録販売者として就業するためには、実務経験が必要になります。具体的には、以下の3つの要件のうちのいずれかを満たさなければなりません。
- 直近5年間のうちに通算2年以上の実務経験がある。
-
直近5年間のうちに通算1年以上の実務経験があり、
かつ
継続的研修並びに追加的研修を修了している。 -
通算1年以上の実務経験があり、
かつ
過去に店舗管理者などとして業務に従事した経験がある。
参照元:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(PDF)
ここで求められる実務経験とは、薬剤師または登録販売者(管理者要件を満たした者)の管理・指導のもとで医薬品販売の業務に従事した経験のことです。
登録販売者試験に合格すると、「登録販売者(研修中)」という扱いとなります。その後実務経験を積み、まずは上記3つのうち1または2の要件をクリアすることで、正規の登録販売者として就業できるようになります。なお、就業時間の累計は1,920時間以上でなくてはなりません。
これまでは、正規の登録販売者として認められるためには、直近5年間のうち「通算2年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験が必要でしたが、令和5年に登録販売者制度が改正され、実務経験が「通算1年以上」でも正規の登録販売者になれる要件が追加されました。
この背景には、パートタイムやフレックス制など、多様な働き方が広がっていることが影響しています。
ちなみに、途中にブランクがあっても、「直近5年間のうちに通算して1年以上、かつ累計1,920時間以上の実務経験」があれば、必要な実務経験は積んだものと認められます。
ただし、従事期間が1年以上2年未満の場合は、前述の通り継続的研修並びに追加的研修を受講しなければなりません。
これから試験を受験される方は、こちらの記事で試験概要を把握しつつ勉強方法も確認してみてもよいでしょう。
登録販売者の試験は暗記中心ということもあり、独学で合格することも十分可能です。
とは言え、出題範囲も広いため勉強方法にも工夫が必要になりますので、あらかじめ出題傾向についても下記の記事で把握しておきましょう。
1-3. 登録販売者の経過措置について
平成26年に登録販売者試験の受験要件が廃止され、代わりに正規の登録販売者になるための実務要件が設けられたことで、それ以前に試験を合格した登録販売者は、要件を満たすことができず、登録販売者として就業できなくなる恐れがありました。
そのため、平成26年度以前の旧試験合格登録販売者に対しては、旧制度から現行制度への時限的な経過措置(そのまま登録販売者として就業することを認めるとする措置)が設けられていましたが、令和3年8月にこれも期限を迎えました。
この経過措置が設けられた当時は、期限を令和2年3月までと定めていましたが、令和2年に管理者要件の緩和とともに、経過措置の延長を発表していたのです。
現在は、「通算5年以上の実務経験があり、かつ法律に定められた研修を通算5年以上受講した場合は正規の登録販売者とみなす」という経過措置が設けられています。
ただし、この場合は月単位で従事期間を計算し、1か月に80時間以上従事している必要があります。
この経過措置については、令和5年7月時点で終了期限は決まっていません。
2. 就業のために必要な実務経験
登録販売者として就業するために必要な直近5年間に1年以上または2年以上の実務経験とは、以下のような条件を満たす場合をいいます。
(ア) 一般従事者として、薬剤師または登録販売者の管理・指導の下で、通算して1年以上または2年以上従事していること。間にブランクがあっても、直近5年の間であればよい。
(イ) 従事期間が1年以上2年未満の場合は、従事期間は月単位で計算し、1か月に160時間以上従事していること。
(ウ) (イ)を満たさない場合でも、直近5年間のうちに、月当たりの時間数に関わらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、累計1,920時間以上従事していること。
参照元:【厚生労働省】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規(PDF)
次に、すでに実務経験がある場合とない場合に分けて、具体的にどのような条件が当てはまるのか解説します。
2-1. 合格以前に実務経験がある場合
合格以前の直近5年間に通算して2年以上、かつ累計1,920時間以上の実務経験があれば、すぐに正規の登録販売者として就業することができます。
従事期間が1年以上2年未満なら、法律に定められている継続的研修、並びに店舗または区域の管理及び法令順守に関する追加的な研修を修了する必要があります。
研修では、ガバナンスや法規、コンプライアンスなどの基本的な知識や、現場で求められるコミュニケーションなどを学びます。
2-2. 実務経験の間が空いている・足りていない場合
合格以前に実務経験はあるものの退職してブランク期間がある、あるいは実務経験があるもののまだ基準に満たないという場合は、合格後に研修中の登録販売者として実務経験を積み、その期間と以前の実務経験を合算して、直近5年間で通算1年以上または2年以上、かつ累計1,920時間以上の実務経験という要件を満たす必要があります。
ただし、実務経験のカウントに際しては、月単位で計算するなどの条件があるため注意が必要です。例えば、2年以上登録販売者としての勤務実績があると思っていても、月の途中で転職したケースなどでは、実務経験としてカウントできないこともあります。
ブランクをお持ちの方は、詳しく確認しておくとよいでしょう。
また、合格前後の実務経験の合計が1年以上2年未満の場合は、前述の通り必要な研修を修了しなければ、正規の登録販売者として就業することはできません。
2-3. 実務経験が全くない場合
実務経験が全くない方が販売登録者試験に合格した場合は、まず、勤務先の店舗を管轄する都道府県で、登録販売者販売従事登録の申請を行い、販売従事登録証を発行してもらいます。
その後、研修中の登録販売者としての勤務がスタートします。正規の登録販売者として認められるためには、「1年以上かつ累計1,920時間以上の実務経験を積み、かつ必要な研修を修了する」か、「2年以上かつ累計1,920時間以上の実務経験を積む」のいずれかの条件をクリアする必要があります。
3. 実務経験として求められる雇用形態とは?
登録販売者の実務経験として認められるために重要なのは、薬剤師または登録販売者(店舗管理者・管理代行者の要件を満たした者)の指導を受けて働いたかどうかです。雇用形態は正社員に限らず、アルバイトやパートであっても構いません。
直近5年間のうちに、一般用医薬品を取り扱っているドラッグストアや薬局、コンビニエンスストア、調剤薬局などで、薬剤師や登録販売者の指導の下に働いた経験が、「実務経験」となります。
繰り返しになりますが、直近5年間の実務経験が2年以上あればすぐに正規の登録販売者として働くことができますが、1年以上2年未満なら、継続研修並びに追加的研修を修了する必要があります。
4. 実務期間を終えたら、「実務・業務従事証明書」を発行してもらう
実務期間の要件を満たした場合は、それを証明する「実務・業務従事証明書」を勤務先に発行してもらいましょう。以下に述べる「販売従事登録」が済んでいても、1人で医薬品が販売できるようになるには、この実務・業務従事証明書が必要となります。
企業側には、証明を求められた場合には速やかに証明書を発行し、記録を保存する義務があります。用紙も企業側が手配してくれる場合が多いとは思いますが、もし用紙を持参するように言われたら、各都道府県のホームページから入手しましょう。
すでに退職している場合でも、過去5年間にさかのぼって実務経験がある場合は、その職場に実務・業務従事証明書の発行を申し出ることができます。
実務・業務従事証明書は、これまでの実績を証明する大切な書類ですので、必ず発行してもらいましょう。
参照元:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
4-1. 実際に働くには「販売従事登録」が必要
実際に登録販売者として働くためには、勤務先の都道府県で「販売従事登録」を行う必要があります。
登録の申請にあたっては、以下の書類が必要です。
- 販売従事登録申請書:各都道府県の公式ホームページからダウンロードするほか、保健所でも配布しています
- 登録販売者試験の合格通知書
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうち、いずれか一点(発行6か月以内のもの)
- 医師による診断書(発行3か月以内のもの):機能の障害、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者ではないことを証明するために必要です
- 使用関係を示す書類:雇用証明書など(※申請者が薬局開設者または医薬品の販売業者でないとき)
- 登録手数料:各都道府県によって異なります(令和5年7月現在、7,100円~10,300円)
令和3年8月1日より、申請様式が変更になっています。旧様式では販売従事登録を行うことができませんので、必ず最新の様式を使用するようにしましょう。
申請書類などの提出方法は、郵送もしくは直接持ち込みです。都道府県によって異なりますので、各都道府県の公式ホームページで確認しましょう。販売従事登録証の交付は、窓口での受け取り、または郵送です。即日交付ではなく、通常、申請から2週間ほどで入手できます。
なお、異動などで勤務先が変わった場合でも再登録の必要はありません。異動先が他の都道府県であっても、再登録は不要です。本籍地、氏名、生年月日など、登録証の記載内容に変更があった場合は、書換え交付の申請が必要となります。
5. 実務経験は転職に影響ある?
医薬品販売業の転職市場では、一般用医薬品を販売することができる登録販売者のニーズが高まっています。
もちろん、実務経験を積んだ登録販売者であれば、入社後すぐに戦力として就業できるほか、1人でも一般医薬品を扱うことができるため、当然実務経験のない登録販売者(研修中)の人よりも有利な立場で転職活動を進めることができます。
実際、「実務経験が2年以上歓迎」と記載している求人や、採用の条件として「登録販売者の実務経験2年以上」と設定している求人もあります。
前述の通り、令和5年に正規の登録販売者となるための要件が「2年以上の実務経験」から「1年以上の実務経験」に緩和されました。
直近5年間の実務経験が1年以上2年未満の場合は必要な研修を受講しなければなりませんが、今後は実務経験が1年以上あれば転職しやすくなっていくのではないでしょうか。
6. 登録販売者は、店舗管理者にもなれる可能性も!
登録販売者になると、単独で売り場に立つことができるだけでなく、店舗管理者になることもできます。では、店舗管理者の業務や店舗管理者になるための条件などを見ていきましょう。
6-1. 店舗管理者とは?
店舗管理者とは、文字通り、店舗の管理を担う者で、具体的には以下のような業務を行います。また、医薬品を扱う店舗では、必ず店舗管理者を1人設置しなければなりません。
- 店舗に勤務している薬剤師・登録販売者、その他すべての従業員の監督
- 店舗の構造設備、医薬品、その他の物品管理、業務に必要とされるものについての注意喚起
- 保健衛生上の支障が生じないよう、店舗販売業者に対して必要とされる意見を述べる
参照元:厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行等について
6-2. 店舗管理者のメリット
店舗管理者になることで期待できるメリットにはどのようなものがあるでしょうか。まず、大きなメリットの一つは、会社から店の運営を任せてもらえるようになり、専門職としてのキャリアアップができることです。
医薬品の販売やカウンセリングなどの登録販売者としての業務以外にも、店舗の運営や商品の発注、お金の管理、他の登録販売者や一般従事者の指導やシフト管理など、直接経営に関わる業務に携わることができるようになります。そのような立場で働いてみると、これまで以上にやりがいを感じることができるようになり、社会人としての経験も積むことができます。
さらに給与面でもメリットが期待できます。責任ある立場である店舗管理者には、基本給にプラスして「手当」が付くことが少なくありません。店舗管理者になることで、年間の収入アップが見込めます。
6-3. 店舗管理者になるには?
先ほど、登録販売者として就業するための3つの要件を紹介しましたが、このいずれかを満たしていれば、店舗管理者になることができます。
なお、一般用医薬品のうち、第2類・第3類医薬品を販売する店舗の管理者は登録販売者でよいのですが、第1類医薬品を販売する店舗の管理者は薬剤師でなければなりません。
薬剤師が店舗管理者になれない場合、過去5年間のうち第1類医薬品を販売する店舗で登録販売者としての実務経験が3年以上、かつ合計2,880時間以上あれば、登録販売者でも店舗管理者になることができます。ただし、管理者の補佐として薬剤師を置くことが定められています。
7. まとめ
令和5年に登録販売者制度が改正され、正規の登録販売者として働く要件が「実務経験1年以上かつ累計1,920時間以上」に緩和されました。追加で研修を受講するなどの条件はありますが、これまでよりも格段に要件をクリアしやすくなったため、今後登録販売者の活躍の場はより広がっていくのではないでしょうか。
正規の登録販売者の要件を満たせば、店舗管理者になることもできるため、転職市場でも有利な立場で職場探しを進めることができます。実務経験を積み、キャリアアップや収入アップを目指しましょう。