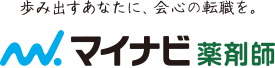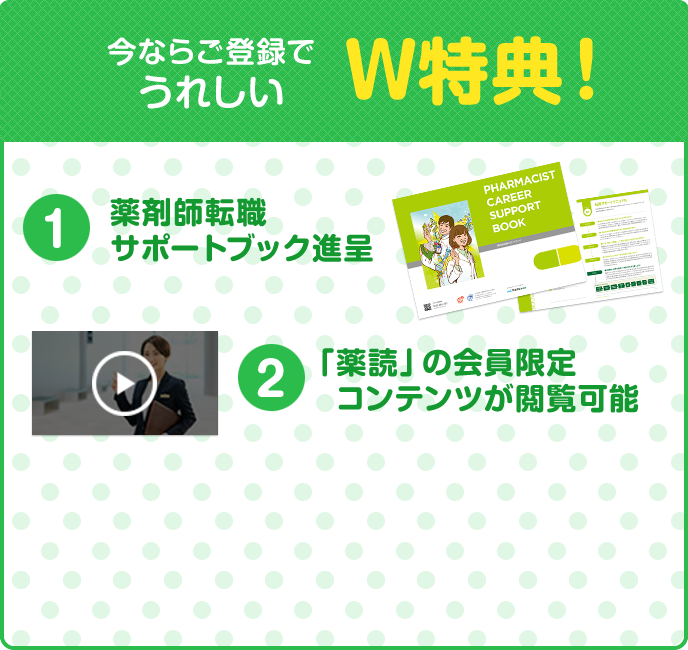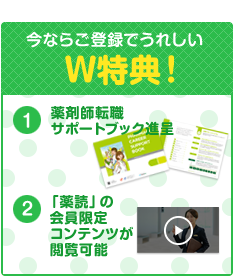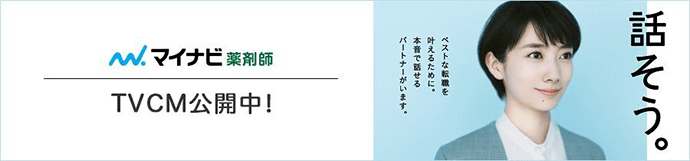薬剤師が博士号をとる必要性とは?大学院に行くメリットについても解説

薬剤師のキャリアアップ方法の一つとして大学院へ進学する選択肢があります。大学院は研究者を目指す人が進学するイメージを持たれる方も多いのではないでしょうか。
実は、薬剤師として臨床で働くキャリアを選択する方の中にも大学院へ進学する方は少なくないのです。
ここでは、薬剤師が博士号を取得する必要性、大学院へ行くメリットやデメリットなどについてご紹介します。
目次
1.博士号とは
博士号は、博士課程を修了した人が得られる学位です。ただ学士号や修士号と比較すると取得者が少ないため、学士や修士と何が違うのかご存じない方もいるのではないでしょうか。
そこで社会的評価や就職の違いなどを軸に学士・修士・博士の違いについてご説明します。
1-1.学士・修士・博士の違い
学士は大学を卒業した方に与えられる学位です。社会人になるための基礎的な能力や一般教養があるとみなされます。
6年制薬学部も卒業すると学士号が与えられますが、実習をこなしながら研究活動もおこなうため、企業によっては修士相当とみなされるところも多くあります。
修士は大学を卒業後、2年制の大学院の修士課程を修了することで与えられる学位です。
学士よりも一歩踏み込んだ専門性があるとみなされ、薬学部では企業の研究職や開発職にも応募できるようになります。
博士は大学院の修士課程修了もしくは6年制の大学卒業後に3年ないし4年制の博士課程を修了することで授かる学位です。
研究者として自立しており、高度な専門性を有するとみなされます。アカデミアや企業の研究職に自分の専門性を売り込んだ応募ができるようになります。
病院などの公的機関において高度な科学的知識を要求される仕事に就くこともできます。
2.薬剤師の博士号「薬学博士」
大学院によって呼称が少し異なることもありますが、一般的には6年制の薬学部を卒業後、多くは薬剤師の資格を取得した上で博士課程(4年)に進学し、修了することで「薬学博士」あるいは「博士(薬学)」を授かります。
また4年制の薬学部を卒業後、大学院で修士課程(2年)を経て、博士課程(3年)を修了すると「薬科学博士」あるいは「博士(薬科学)」を授かります。
薬学博士と薬科学博士には学位としての違いはありませんが、薬学博士は薬剤師免許を所有することができるため、薬剤師の養成に力を入れている薬学部のポストに応募する場合、教育的な側面から有利になる可能性があります。
大学院に進学するべきか就職(転職)するべきか迷っている薬剤師の方は、マイナビ薬剤師に無料登録して相談するのもおすすめです。
マイナビ薬剤師は、薬剤師の転職サポートサービスですが、登録したら必ず転職しなくてはいけないという訳ではありません。
薬剤師専任のキャリアアドバイザーと面談をして、あなたの将来を見据えたキャリアを一緒に考えます。最新の転職市場の情報もお伝えできますのでお気軽にご相談ください。
3.薬剤師が博士号をとる必要はある?
薬剤師として薬局や病院で働く分には博士号は必要ありません。
しかし、科学者としての側面も大きい薬剤師の業務では、大学院で研究をした経験が活きてくる場面も多いでしょう。また、キャリアアップなどにつながることも期待できます。
3-1.自身の能力の証明になる
一般的に薬学系の大学院では、授業を受けて所定の単位を取得することも必要とされていますが、主に研究をおこなって学術論文を世の中に出すことで修了要件を満たします。
そのため、大学院を修了して博士号を取得することは、一連の研究活動を通じて課題を発見し、それを解決する能力を身に付けた証明になるのです。
多くの場合、査読制度のある雑誌に学術論文を投稿し受理されることまで求められていますので、自身の研究が一つの仕事として世の中に認められた証明にもなります。
3-2.給与アップにつながる
博士号を取得することで、製薬会社の研究職などにも応募しやすくなります。その結果、薬剤師として働く場合に比べて給与アップが期待できるかもしれません。
また、薬剤師業務に必要な論文を読む力や、論理的に考える力があるとみなされ、薬剤師として働く場合でも、企業によっては博士号取得者に対して通常の給与額よりも高めに設定されているところもあります。
3-3.キャリアアップにつながる
一部の病院などでは薬剤部長などのポストやDI(ドラッグ・インフォーメーション、医薬品情報)の業務に就くために博士号取得を条件としているところもあるため、薬剤師のキャリアアップにつなげることも期待できます。
最近では、大手のドラッグストアなどでも博士号所持者を積極的に昇進させようとする動きもあります。
また、製薬会社の研究職や研究活動もおこなっている病院では大学院での研究経験を直接活かすことができます。
4.博士号を取得するには大学院に進学する必要がある
博士号を取得するためには大学院に進学する必要があります。薬学部は4年制課程と6年制課程とで進路が異なっており、特にわかりにくくなっています。
ここでは、それぞれの課程で博士号を取得するための進路について具体的に解説します。
参照元:文部科学省/薬学教育制度の概要
4-1.4年制大学
薬学部の4年制課程は「薬科学科、創薬科学科」などと称されることが多く、4年制課程を有する大学は6年制課程を併設しています。
4年制課程を卒業しても薬剤師国家試験を受験することはできませんが、長期実習がないため他学部の大学院と同じように大学院生活の大部分を研究に割くことができます。
4年制課程卒業者のほとんどは大学院へ進学しますが、2年制の修士課程を修了し、更に3年制の博士課程を修了することで博士号が取得できます。
4-2.6年制大学
薬学部の6年制課程は「薬学科」と称されることが多く、6年制課程のみの大学と4年制課程も有する大学があります。
6年制課程では薬剤師国家試験受験資格を得ることができます。6年制課程卒業者は学士を取得後、修士課程を経ずに4年制の博士課程に直接進学して修了することで博士号が取得できます。
6年制課程の後半では長期実習があるため研究と両立させるのが大変ではありますが、4年制課程と6年制課程を併設している大学の場合、どちらのコースの出身者であっても同じラボで分け隔てなく研究することが多いです。
薬学部の教育課程や薬剤師の就職先について、詳しくは下記を参考にしてください。
5.大学院に行くメリット
大学院に進学するメリットとして、キャリアの選択肢が広がるほか、研究活動を通じた能力の成長を挙げることができます。
そして、何より自分の興味に従って研究できるのが最大の魅力なのではないでしょうか。大学院に進学するメリットをご紹介します。
5-1.就職・転職の選択肢が広がる
大学院に進学することで、就職や転職の選択肢が広がります。
製薬会社の研究職やMSL(メディカルサイエンスリエゾン)職、DI職などの高度な科学的思考を要求される職種で知識を活かすことができます。
特に、大手の製薬会社などでは博士号取得者を積極的に採用しているところもあるため、博士号を持っていることで応募できる企業も増えます。
また、製薬企業以外にも大学や病院、公的な研究機関などで働くチャンスが広がります。
> DI、学術、MSL、メディカルライターの薬剤師求人を見る
5-2.知識の質を高められる
大学院に進学することで、知識の質を高めることができます。
大学院では、今までは授業や教科書でしか習わなかったような知識を、実際の研究活動を通じて生きた知識として活用する必要があります。
研究活動によって知識の解像度は上がり、今まで見たことのなかった世界に出会うことができます。
5-3.研究職に就職・転職できる
大学院では主に研究をおこないますので、大学院に進学することで、研究職への就職や転職がしやすくなります。
特に、博士課程を修了することで、自立した研究者の卵として認められます。修士卒と比べてより高い専門性があるとして、官民問わず研究職に応募できるようになります。
特に大手の製薬会社では修士卒よりも専門性の高い博士卒の学生を積極採用する傾向があるため、大手製薬会社の研究職に就きたい場合は博士号の方が活躍しやすいでしょう。
5-4.大学教員になることもできる
大学院に進学することで、大学教員のポストも狙うことができるようになります。
大学教員は研究の他に教育活動もおこなうため、研究と教育が好きな方におすすめします。
特に、薬剤師免許を持っている薬学博士の場合は、国家試験対策を学生に教えることができるとみなされるため、薬剤師養成に力を入れている薬学部では公募で有利になる可能性があります。
6.大学院へ行くデメリット
大学院に進学する前に、そのデメリットも把握しておきましょう。大学院は大学卒業後に通うため、学費が高額になりがちです。
勉強にかかる時間も大学と比べて長くなることも覚悟しておきましょう。研究・勉強時間を確保するには通学時間に気を配る必要も出てきます。
6-1.学費がかかる
大学院を卒業すると学部卒に比べて学費がかかってしまいます。
ただ、お金がないからといってアルバイトにばかり精を出していると研究や勉強に支障が出てしまいます。
そこで、厳しい選考を勝ち抜く必要はあるものの、日本学術振興会の特別研究員制度や卓越大学院プログラムなどを利用することで、支援を受けられる場合があります。
また、薬剤師免許を所有していれば薬剤師としてアルバイトができるため、ドラッグストアなどでは比較的高いお給料で働くことができます。
参照元:文部科学省/卓越大学院プログラム
6-2.勉強に時間がかかる
大学院では研究活動が中心となりますが、研究のために多くのことを勉強する必要があります。
新しい分野を研究し始めるときは膨大な勉強量が必要ですし、自分の専門から離れた実験をする際にも勉強が必要です。
教科書はもちろんのこと、分野を代表する論文を何十報と読む必要も出てきます。
研究室にいる時間に勉強ばかりしていては研究が進まなくなってしまうため、大学院生は主に平日の夜や土日に勉強をしている方もいます。周りの社会人が遊ぶ中、土日も勉強に費やす覚悟が必要です。
6-3.通学の時間
研究や勉強に集中するためには大学院へ通う時間も無視できません。通学に時間がかかればその分プライベートの時間も削られてしまいます。
研究が本格的に進んでいる間は夜間も研究室に行くことが多くなるため、通勤時間や生活サイクルなどを考慮して、住む場所を検討してみるのもよいでしょう。
また、実家から通える範囲に行きたい大学院があれば、家賃の節約にもつながりますし、通学時間も短くできて一石二鳥です。
7.働きながらでも大学院に通うことは可能?
社会人でも通えるコースを設定している大学院があるため、働きながらでも大学院に通うことは可能です。
また、一般的な大学院でも授業をオンラインで受講できるのであれば、教授の理解を得たうえで社会人大学院生として進学可能です。
社会人大学院生は研究時間が極端に限られているため、近くの大学院に通えない場合はPCなどによる解析を主にした研究も選択肢の一つとして考えてみるのもよいでしょう。
また、修士までの成果で論文化が可能であれば、その成果で博士課程の研究を効率良くおこなうこともできます。
働きながら大学院に通う場合は、トラブルを避けるためにあらかじめ会社と大学院によく話を通しておくようにしましょう。
8.まとめ
薬学系の大学院についてご紹介しました。薬剤師が博士号を取得することで、高度な専門性が必要とされる職種へのキャリアアップなどにつながります。
研究職などに興味のある方は、大学院への進学を検討してみてはいかがでしょうか。
「薬学系大学院修了後の就職先が欲しい」、「博士課程で培った専門的知識をきちんとアピールしたい」という方は、薬剤師や登録販売者を専門に扱う転職エージェント「マイナビ薬剤師」にご相談ください。
マイナビ薬剤師に登録すれば、経験豊富な薬剤師専任のキャリアアドバイザーが大学院を修了した方に向けて転職市場の動向などの最新情報を詳しくお伝えします。
また、履歴書の添削や面接対策なども無料で受けられるので、企業担当者に伝わりやすいように伝え方を工夫することもできます。
まずは、マイナビ薬剤師への登録をして、専門性の高いキャリア形成の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報
おすすめの薬剤師求人一覧
転職準備のQ&A
薬剤師の転職の準備に関するその他の記事
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554