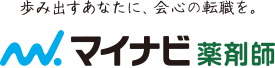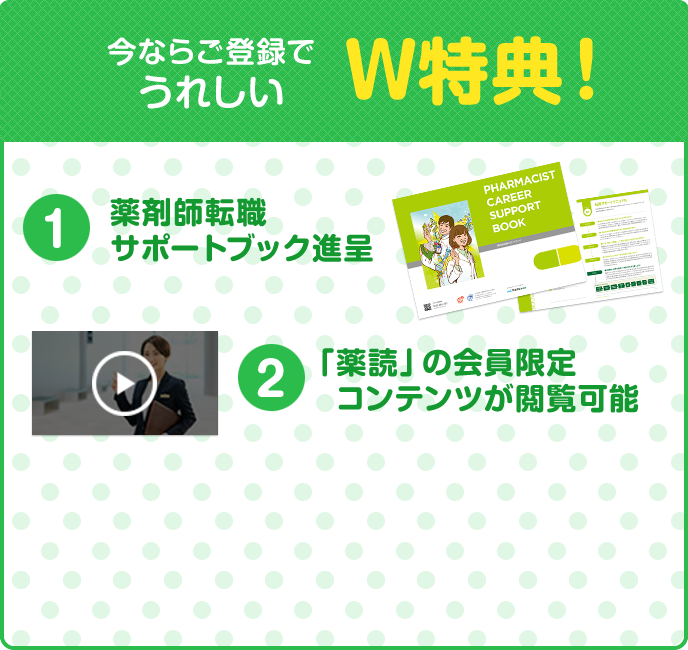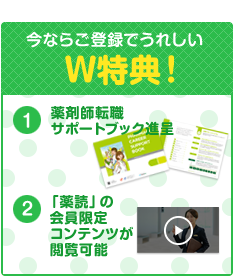薬剤師外来とは?病院の取り組みや今後の薬剤師について

医療技術の進歩や薬物療法の高度化により、近年は抗がん剤治療、緩和薬物治療などを外来でおこなえるようになりました。
通院で治療を継続できるのは、患者さまのメリットになるだけでなく、医師の負担軽減にもつながります。他職種と連携する機会が増えることで、薬剤師のやりがいも大きくなるでしょう。しかし、一方で服薬アドヒアランス、コンプライアンスの維持などに課題が残ることも事実です。
そうした背景を受けて、薬物療法の有効性・安全性を高めるために取り入れられたのが、病院薬剤師による薬剤師外来です。
薬剤師外来に関心が集まるようになったのは、2014 年度の診療報酬改定によって「がん患者指導管理料3(※)」が新設されたことがきっかけでした。それによって、病院薬剤師が外来患者さんの服薬管理に介入することの重要性が注目され、地域の中核病院における薬剤師外来の導入が進んだのです。
※「医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明をおこなった場合」に算定できます。
ただし、薬剤師外来は全国すべての病院に設置されているわけではなく、世間的な認知度という面でも、まだ高いとはいえません。そこで今回は、今後さらなる広がりが期待される薬剤師外来を取り上げ、その概要や業務内容、将来的な展望などを解説します。
目次
1.薬剤師外来とは
薬剤師外来とは、外来患者に対して最適な薬物療法を提供するため、薬剤師が薬学的管理、服薬指導などを通じて治療に携わる取り組みを指します。
患者さまに、治療に対する知識や理解を得てもらうとともに、不安や心配を軽減し治療効果の向上を目指すのが、薬剤師外来の目的の一つです。
ここでは、薬剤師が外来診療に加わる重要性について解説します。
参照元:一般社団法人 日本病院薬剤師会/外来患者への薬剤師業務の進め方と具体的実践事例
1-1.薬剤師外来の重要性
超高齢社会の日本では、外来患者の抱えるさまざまな問題に対して、薬剤師の参画が期待されています。
以下では、薬剤師の参画によって期待される4つの役割を紹介しましょう。
まず1つ目は、高齢者に対する薬物治療の安全性の確保です。
診療科が細分化された現代の薬物治療では、多剤併用・重複投薬といったポリファーマシーが問題視されています。
薬剤師が介入することで、医師への処方整理の提案や患者さまへの指導が充実すれば、高齢者に対する薬物治療は、より適切かつ安全なものになるでしょう。
2つ目は、アドヒアランスの向上です。薬剤師が患者さまと面談し、納得して治療を受けてもらうことで、服薬アドヒアランスの向上が期待できます。特に抗がん剤、吸入薬、自己注射など、使用するにあたって注意が必要な薬剤については、薬剤師の参画が効果的です。
地域包括ケアシステムが推進され、在宅での治療が増えていけば、患者さまのアドヒアランス向上は、薬物治療の有効性や安全性を高めるうえでますます重要になるでしょう。
3つ目は医師の負担軽減です。2022年度の診療報酬改定でも提言されているように、医療の質を高めていくためには、医師の負担を軽減することが不可欠です。特に外来診療は医師1人が問診、診断、処方をおこなう場合がほとんどで、1日に何人もの患者さまを診察しなければなりません。
一方、薬剤師外来を導入すれば、医師の業務のうち、薬物治療に関することを薬剤師にタスクシフトできます。
参照元:厚生労働省/令和4年度診療報酬改定について
参照元:全国保険医療団体連合会/2022年度診療報酬改定特集
4つ目は入院・外来のシームレスな薬学管理です。
地域包括ケアシステムにおいては、病院と地域の薬局、診療所との連携が不可欠であり、薬剤師外来を設置すれば、病院と地域を結ぶ窓口の役割が果たせます。特に手術前の内服薬確認、休薬指示は、安全な周術期管理において大変重要です。
2.薬剤師外来のメリット・デメリット
ここまで、薬剤師が外来患者に関わることの重要性について解説してきました。続いては、薬剤師外来を設置することで、薬剤師にどういったメリット・デメリットがあるのかを考察していきましょう。
2-1.メリット
- 入院前から患者情報がわかる
- 患者さまと長く関われる
薬剤師外来によって、入院前に患者情報を把握することは、入院後のスムーズな指導につながります。事前に患者情報がない状態での入院は、持参薬・既往歴・副作用歴・アドヒアランス状況など、さまざまな情報を把握するところからはじまります。そこから入院中に禁忌薬が使われる恐れがないか、病態に応じた特殊な対応は必要かなどを検討していくと、多くの時間がかかってしまうでしょう。
しかし、事前に患者さまの情報が把握できていれば、入院するまでに薬剤部内や他職種間で協議し、方針を決めておくことができます。イレギュラーなことは、医療ミスや業務圧迫の原因にもなるため、前もって準備できるのは、薬剤師にとって大きなメリットです。
以前の病院薬剤師は、入院患者の対応がメインで、入院期間にしかその患者さまと関わることができませんでした。しかし、薬剤師外来ができたことで、より長く深く患者さまと関わることができます。
特に、がん化学療法を受ける患者さまとは長い時間をともにすることになり、薬剤師として貴重な体験になるでしょう。がん化学療法に特化した知識が身につくのはもちろん、薬剤師外来を通じて患者さまのQOLの向上、治療効果の向上などに貢献することは、薬剤師にとって大きな財産となります。
2-2.デメリット
- インセンティブが少ない
- 人員が足りていない
2024年診療報酬改定では、「ベースアップ評価料」「薬剤業務向上加算」「がん薬物療法体制充実加算」などが新設されました。しかし、薬剤師外来に対する診療報酬のインセンティブはまだ少なく、抗がん剤治療や自己注射の導入時などに限定されています。
病院薬剤師の業務は年々多様化・複雑化していますが、人員が充足している病院はまれです。人手が足りていないなかで外来担当薬剤師を置くと、他の業務に影響が出てしまうため、薬剤師外来の設置が難しい病院も少なくありません。
3.薬剤師外来の業務内容や流れ
ここからは薬剤師外来の業務内容や、業務の流れの一例を紹介します。
薬剤師外来の業務は、治療の開始前・開始時と開始後にわけられ、さらに医師の診察前と診察後にわけられます。
参照元:一般社団法人 日本病院薬剤師会/外来患者への薬剤師業務の進め方と 具体的実践事例
3-1.治療開始前の診察
3-1-1.診察前・診察時
- 事前情報を収集・評価
- 診察前面談による情報の収集・評価
- 患者さまへの指導
- 医師などへの情報提供と対応策の協議・立案
服薬状況やアレルギー歴、副作用歴などを確認します。また、チームカンファレンスがあれば参加し、他職種と治療方針や情報を共有します。
事前情報を踏まえたうえで、服薬状況や服薬効果、アレルギー、副作用歴などの最新情報を聞き取ります。また、それらの情報を薬学的に評価し、患者さまに最適な処方設計を医師に提案します。処方設計に際しては、治療効果や服薬アドヒアランス、薬物間相互作用、臓器機能などを考慮した提案をおこなうことが大事です。
必要に応じて服薬指導をおこないます。周術期の対応を目的とした術前外来の場合は、院内ルールに従って、周術期管理に影響をおよぼす可能性のある薬剤の使用を確認・評価し、対応方法を指導します。
診察時に必要な情報は、すみやかに医師や他職種に提供します。開始予定の薬剤について検討すべき点がある場合は、その旨と代替案も医師に報告します。また、PBPM(プロトコルに基づく薬物治療管理)が適応可能な場合には、院内ルールに従って実践します。
3-1-2.診察後
- 診察内容の確認
- 処方内容の確認
- 指導の実施
- 薬学的評価計画の立案
- 医師などへの情報提供と対応策の協議
- 他の保険医療機関や保険薬局などとの連携
医師による治療方針や処方薬の説明に対する、患者さまの理解度を確認します。
事前情報や検査結果、診察内容などを総合的に判断し、処方内容の妥当性を判断します。もし問題があれば、医師に疑義照会をおこないます。
診察などの情報を踏まえて、服薬指導や生活習慣指導をおこないます。吸入薬や自己注射の薬剤が処方された場合は手技指導もおこないます。
薬学的評価に必要な臨床検査値については、次回診察時の採血項目から漏れないように医師と協議します。また、患者さまの帰宅後も薬学的評価が必要な場合は、症状日誌や電話連絡などにより、薬物治療のモニタリングをおこないます。
面談内容を他職種と共有し、次回診察時の対応を協議します。
事前情報の確認や患者面談をおこなっても、患者さまが使用中の医薬品の情報が不明確な場合、調剤をおこなった他の保険医療機関や保険薬局から情報を収集します。術前外来の場合は、周術期管理に影響をおよぼす可能性のある薬剤の情報を、他の保険医療機関や薬局に提供します。
また、院内・院外の連携がスムーズにおこなえるように、指導手順や情報伝達ツールについて他の医療機関や薬局と研修会をおこなう場合もあります。
参照元:一般社団法人 日本病院薬剤師会/外来患者への薬剤師業務の進め方と 具体的実践事例
3-2.治療開始後の診察
3-2-1.診察前
- 事前情報を収集・内容確認
- 診察前面談の実施
- 診察前面談により抽出された問題への対応
- 医師などへの情報提供と対応策の協議・立案
前回までで抽出された問題点、対応策を確認します。当日の検査値などがわかる場合は、それについても確認・評価します。
診察前に患者さまと面談をおこない、効果や副作用、アドヒアランス、治療開始後のQOLを確認・評価します。
処方薬の服用方法や手技に問題がある場合は、あらためて説明・指導します。指導による効果が期待できない場合は、治療方針の変更も含めて医師などと協議します。
必要な情報を医師や他職種と共有します。副作用管理のために支持療法の追加が必要な場合は、その処方内容を提案し、確認が必要な臨床検査項目がある場合には、検査オーダーを依頼します。
治療薬の効果や副作用、アドヒアランスの状況によっては、処方内容や治療薬の変更を提案する場合もあります。また、PBPMが適応可能な場合には、院内ルールに従って実践します。
3-2-2.診察後
- 診察内容の確認
- 処方内容の確認
- 服薬指導の実施
- 薬学的評価計画の立案
- 医師などへの情報提供と対応策の協議
- 他の保険医療機関や保険薬局などとの連携
医師による治療方針や処方薬の説明に対する、患者さまの理解度を確認します。
医師との協議内容が、処方に反映されているかを確認します。
患者さまの理解不足による服薬アドヒアランス不良が疑われる場合、服薬の意義を含めて、再度服薬指導を実施します。
薬学的評価に必要な臨床検査値については、次回診察時の採血項目から漏れないように医師と協議します。また、患者さまの帰宅後のフォローアップや、次回以降の診察前面談が必要かどうかの判断もおこないます。
診察時に必要な情報や、処方内容に影響する可能性のある事項は、医師や他職種と情報を共有します。また、事前に作成・合意したPBPMが適応可能な場合には、院内ルールに従って実践します。
お薬手帳や薬剤情報提供書などを活用し、他の保険医療機関や薬局の薬剤師と情報を共有します。必要があれば、他の保険医療機関や薬局との勉強会をおこない、薬物療法モニタリングや指導の内容についても整理・統一します。
参照元:一般社団法人 日本病院薬剤師会/外来患者への薬剤師業務の進め方と 具体的実践事例
4.薬剤師外来にはどんなものがある?
実際に病院でおこなわれている薬剤師外来には、以下のようなものがあります。
- がん化学療法外来
- 吸入指導外来
- 自己注射指導
- 術前外来
抗がん剤治療患者を対象に、抗がん剤の説明や生活習慣・臓器機能・併用薬のチェック、投与量・投与スケジュール・副作用の確認などをおこないます。
気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患などの吸入薬が必要な患者さまに対して、手技を含めた説明・指導をおこないます。患者さまの状態に適したデバイスや補助具の選定もおこない、医師と協議します。
インスリン、骨粗しょう症治療薬、生物学的製剤などの自己注射が必要な患者さまに対して、手技指導をおこないます。自己注射の手技は煩雑なものが多く、患者さまによっては導入が難しいケースもあります。そうした点も含めて薬剤師が評価し、安心して治療を継続できるようにサポートします。
現在の服用薬剤、アレルギー歴、副作用歴、既往歴などを確認します。そのうえで、周術期の治療において使用できない薬剤はないか、休薬が必要な薬剤がないかを確認し、患者さまに説明・指導します。
参照元:社会医療法人 誠光会 淡海医療センター/薬剤部長あいさつ
参照元:一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院/薬剤師外来
参照元:名城大学薬学部病態解析学Ⅰ 教授 野田幸裕/医薬連携における薬剤師外来:吸入指導
5.病院での取り組みや事例を紹介
ここからは、実際の薬剤師外来の取り組みについて、がん化学療法外来の事例を挙げながら解説します。
5-1.治療開始前・開始時におこなうこと
治療開始前・開始時におこなう主な業務は、以下のとおりです。
- 多職種カンファレンスなどで、治療方針を確認する。
- 医師が処方した内容について、患者情報をもとにレジメン・投与量のダブルチェックをおこなう。
- 治療に先立ち、薬の効果・スケジュール・起こりえる副作用などについて患者さまに説明する。
- かかりつけの薬局に診療情報提供書を発行し、治療内容を通知する。
- 必要に応じてテレフォンフォローアップなど、帰宅後の支援もおこなう。
- 診察内容を踏まえて次回以降のケアプランを策定し、カンファレンスなどで共有する。
5-2.治療開始後におこなうこと
治療開始後におこなう主な業務は、以下のとおりです。
- 前回の診察後からの情報を確認する(かかりつけ薬局からのトレーシングレポート、テレフォンフォローアップの内容など)。
- 診察前面談として、患者さまに副作用発現状況、アドヒアランスなどを確認する。
- 面談の情報を診察前に医師、がん化学療法担当の看護師などに共有する。
- お薬手帳などを用いて、再度かかりつけ薬局に情報を共有し、治療を継続する。
このように、外来薬剤師は院内の他職種だけでなく、かかりつけ薬局との連携も欠かせません。現在は、内服の抗がん剤も増え、薬薬連携の意義はこれまで以上に大きくなっています。
参照元:一般社団法人 日本病院薬剤師会/外来患者への薬剤師業務の進め方と 具体的実践事例
6.薬剤師外来の現状や今後について
かつて、院内における調剤が中心だった病院薬剤師の業務は、院外処方の普及によって大きく変化。病棟に出向いて入院患者に服薬指導をおこなうほか、多職種と連携してチーム医療に携わったり、外来患者の治療に関わったりと幅広い業務を担うようになりました。
そして現在、高度な化学療法などをおこなう外来治療は確実に増えており、薬剤師外来を設ける医療機関も増加傾向にあります。また、超高齢化が進むなか、高齢者のアドヒランス不良やポリファーマシーといった課題が浮き彫りになり、薬剤師外来にかかる期待も高まっています。
そうした背景を踏まえるなら、薬剤師外来はさらに重要度を増し、薬剤師の活躍の場はさらに広がっていくでしょう。事実、2年ごとにおこなわれる診療報酬改正においても、そうした流れがみて取れます。 たとえば、2024年の診療報酬改定で新設された「がん薬物療法体制充実加算」は、その代表的な施策といえるでしょう。がん薬物療法体制充実加算というのは、外来化学療法を受けるがん患者に対して、薬剤師が診察前に服薬状況や副作用などを聞き取り、医師に情報提供、処方提案をおこなうことで算定できる報酬のこと。つまり、「医師の診察前の薬剤師外来が点数化されたもの」といえるわけです。 ただし、前述したように、地方にある病院や中小病院の多くは人材不足に直面しており、業務を広げたくても広げられないのが実情です。 同じく2024年の診療報酬改定では「薬剤業務向上加算」が新設され、地域の基幹病院から人材不足の病院へ薬剤師を出向させる動きが生まれていますが、こうした流れが定着すれば、薬剤師外来はより充実したものになるでしょう。 今回は、薬剤師外来の業務内容や、具体的な業務事例について解説しました。現在、薬剤師外来は、超高齢社会が抱える外来診療の課題(アドヒランス不良、ポリファーマシーなど)を解決する糸口として、重要な役割を担っています。 また、地域包括ケアシステムの構築が進み、治療の場が病院から地域へと移り変わっていけば、 薬物治療の安全性と有効性が高めるためにも、多職種が連携して地域医療を支えるためにも、今後は全国各地の病院に薬剤師外来が広まっていくことが望まれます。7.まとめ
「病院と地域の架け橋」となる役割も期待されるでしょう。
毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報
おすすめの薬剤師求人一覧
転職準備のQ&A
薬剤師の職場のことに関するその他の記事
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554