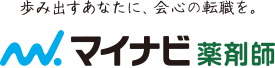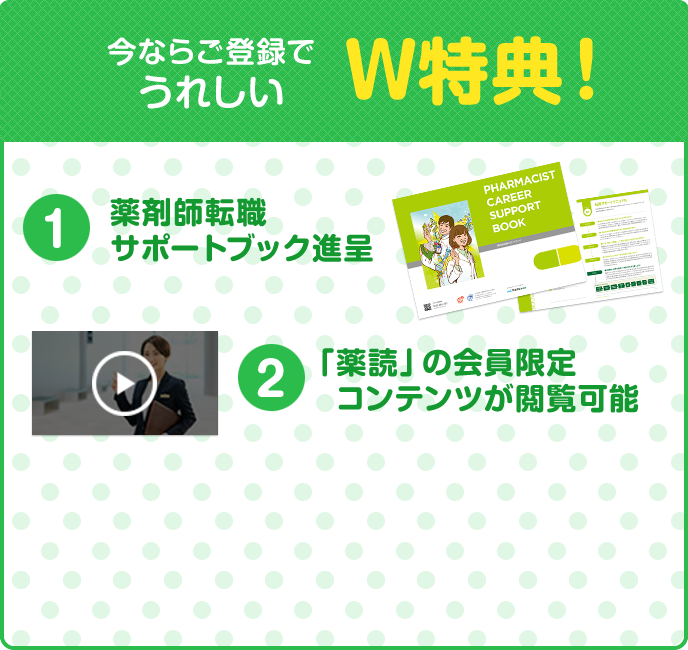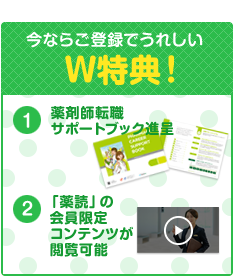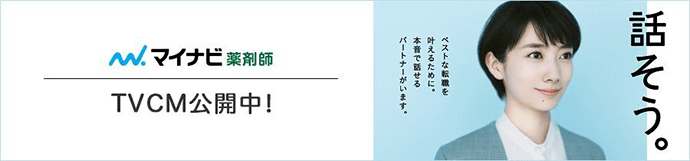臨床薬剤師とは?主な業務内容や今後の展望について

1990代にアメリカで生まれ、日本でも増え始めている臨床薬剤師。新しい医薬品が次々と生まれ複雑化する薬物療法のスペシャリストとして、臨床の現場で患者さんと向き合い治療に直接に関与する薬剤師です。
チーム医療に欠かせない新しい薬剤師像である臨床薬剤師の主な業務内容を紹介し、今後の展望について考察します。
目次
1. 臨床薬剤師とは
病院薬剤師のなかでも、調剤中心に業務を行う従来の薬剤師と異なり、医師や看護師と共に病棟での医療チームに加わり、患者さんの治療に直接関わるのが臨床薬剤師の役割です。
「疾病を対象とする薬剤の専門家」という立場から一歩進んで「疾病を持つ個々の患者さんを対象とした薬物療法」を実践する薬剤師を指します。
1-1. 臨床薬剤師の概要
臨床薬剤師は1990年代にアメリカで生まれた医療職ですが、日本では2000年代に入ってから徐々に普及が始まりました。アメリカには調剤を専門に行うファーマシー・テクニシャンという職種があるので、薬剤師の仕事は調剤よりも患者さんと向き合うことに重きが置かれます。ドラッグストアや薬局では医薬品に関することだけでなく、健康上の相談に乗ったり予防接種を行ったりもします。
病院では医師の処方が適正かどうかを判断し、服薬を一元的に管理する役割を担います。患者さんに対して薬歴管理や服薬指導を行うだけでなく、回診に同行し、医師による疾患の診断を基に処方や投薬設計のアドバイスを行います。こうしたアメリカでのクリニカル・ファーマシストをモデルに、病棟で医療チームの一員として患者さんに対する薬物治療を担うべく、日本でも臨床薬剤師が誕生しました。
臨床薬剤師は患者さんの薬歴や臨床データを収集し、体格や年齢など個人の特性に応じた薬物動態の計算を行い、効果予測や投与設計に活かします。また、患者さんには薬剤や治療についての説明や服薬指導を行い、医師に対しては処方提案、投薬設計のサポートなどを行います。
1-2. 病院薬剤師との関係性
臨床薬剤師は病院薬剤師のなかでも「薬剤管理指導業務」を行う医薬品のスペシャリストです。
薬剤管理指導業務は2012年に新設され、「100点業務」と呼ばれた「入院調剤技術基本料」から発展してきたもので、病院における医薬分業を推進し、臨床薬剤師を生み出すきっかけともなりました。
病院薬剤師が行う調剤と投与以外に、薬歴管理と服薬指導を介して病棟におけるチーム医療の一員として機能することが求められます。また、病院における医薬品情報管理室(DI室)の担当薬剤師とも連携、協働して業務を進めます。
2. 臨床薬剤師の主な業務内容

臨床薬剤師が行う薬剤管理指導業務は、直接服薬指導、服薬支援のほか、処方された薬剤の投与量、投与方法、投与速度、相互作用、重複投薬、配合変化、配合禁忌などに関する確認と、患者さんの状態から投薬の効果や副作用の発現などを把握し、医師にフィードバックやアドバイスを行います。
2-1. 服用する医薬品のデータ取得・情報管理
臨床薬剤師は患者さんの薬歴だけでなく効果や副作用についてもデータとして記録し、医師や医療チーム、DI室とのコミュニケーションやカンファレンスを通じて薬物療法が適切に行われるよう情報を共有します。
投薬に際しては添付文書や院内のデータベースだけでなく、国内外の論文を調べるなどして収集した医薬品の情報に実際の治療を通じて得られた情報やデータを加え、今後の治療へと活かします。
2-2. 医薬品の服用方法の指導
病棟では一般的な服薬指導だけでなく、未承認医薬品の処方や添付文書とは異なる投与量や投薬方法をとることもあります。こうした場合、あらかじめ処方の目的と処方薬の情報を十分に把握し、患者さんにわかりやすくお伝えすることが大切です。
また、患者さんの年齢はお子さまから高齢者までと幅広いため、患者さんご本人だけでなくご家族に対してもご理解いただけるような服薬指導が求められます。
2-3. 医薬品の投与設計提案
医師が患者さんの特性と病態をどのように診ているのかを理解し、処方の目的を共有したうえで医薬品の投与設計を行うことも、臨床薬剤師の重要な業務の一つです。体格や年齢、生理機能の状態などから薬物動態を計算し、エビデンスに基づいた薬学的に適切な投与設計を提案します。
未承認医薬品の使用や添付文書と異なる使用法の場合、海外での症例や最新の論文などからデータを集めたり、情報収集したりすることも必要です。
3. 臨床薬剤師を目指すには
1992年に薬剤管理指導業務の報酬が400点に引き上げられ、臨床薬剤師が活躍する土壌はつくられましたが、臨床薬剤師であることを明確に示す資格は今日に至るまで存在していません。
薬学部が6年制となってからは「臨床薬学」が重視されるようになりましたが、臨床薬剤師の専門学科があるわけではなく、臨床薬剤師を目指すには薬剤師レジデント制度を利用するのが最短コースといえるでしょう。
3-1. 薬剤師レジデント制度
1989年にアメリカで提唱されたファーマシューティカル・ケア(Pharmaceutical Care,PC) の概念は、薬物療法による患者さんのQOLの改善を薬剤師の役割としてとらえたもので、1990年代前半にはEUへと拡がり、WHOでも定義されました。PCを薬剤師の行動原理とする米国では、日本の薬剤師資格にあたるPharm.D.取得後1年目のPGY1(Post-Graduate year 1)と2年目のPGY2というレジデント制度が用意されています。
日本では、米国のPGYをモデルとして、2002年に北里大学北里研究所病院が本邦初のレジデント制度を導入しましたが、多くの病院に広がりを見せ始めたのは薬学部が6年制となった2010~2011年ごろからです。
既存の薬剤師研修制度と異なるのは、研修生が研修費を収める旧来の研修制度と違って、レジデント制度ではレジデントになんらかの給与が支払われることです。
また、レジデントの多くは大学や大学院の新卒者ですが、他の病院職員や薬局薬剤師、製薬企業職員などもみられます。2021年現在、全国の28医療施設で薬剤師レジデント制度が実施されています。
4. 臨床薬剤師に必要な能力
臨床薬剤師には、医薬品に関する幅広い知識を個別の病状に当てはめて、適切な治療に結び付ける医療者としての能力が求められることはもちろん、患者さんやご家族から治療に有用な情報を引き出し、医師や看護師らと良好な関係を保ちながらも客観的な視点を失わない、高いコミュニケーションスキルが求められます。
4-1. 医薬品に対する幅広い知識
臨床薬剤師には、医薬品添付文書の内容だけでなく、他の医薬品や食品との相互作用や重複投与などに関する知識を有することはもちろん、年齢、性別、体格、体質、病態、生理機能まで、一人ひとり異なる患者さんの全身状態を見極めたうえで、薬物動態を計算して最適な投与方法を設定できるスキルが求められます。特定薬剤治療管理料の対象とならない場合でも、TDM(治療薬剤モニタリング)の手法に基づいて取り組む姿勢が重要です。
4-2. 患者さんから話を聞く傾聴力
個々の患者さんに適した薬物治療を行うには、症状だけでなく心のありようも含めて、患者さんの全身状態を正しく把握しなければなりません。そのためには、患者さんがなんでも話してくれるよう、薬剤師は存分に傾聴力を発揮する必要があります。
パーソン・センタード・アプローチ(クライエント中心療法)と呼ばれる心理療法では、話し手が自由に安心して話してくれるためには「相手の話を、相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとする」共感的理解が大切であると説いています。職業柄、一方的な医薬品の説明に終始しがちな薬剤師には特に必要なのが傾聴力といえるでしょう。
4-3. 関係者とのコミュニケーション能力
現代の医療では医薬分業とチーム医療の推進から多職種連携が欠かせない体制となっています。医師を中心として看護師、検査技師、栄養士などがチームとなり、そこに臨床薬剤師を始めとする病院薬剤師が加わります。特に、治療のリーダーである医師と、常に患者さんのケアにあたる看護師とのコミュニケーションは治療の成果を左右する、といっても過言ではありません。
医師は患者さんの疾患について診断し、看護師は医師の指示のもと患者さんのケアにあたります。薬剤師は患者さんの薬歴を調べ、医師と協働して処方と投薬にあたるのですが、治療効果の確認や有害事象の発現に対する気づきなどは看護師の担う役割が非常に大きく、この三者の連携は欠かせません。
医師や臨床薬剤師にとって、看護師による患者さん情報の収集は非常に重要であり、薬剤師は効能効果や副作用の予防と対処法など、看護師に対して正しい医薬品の情報を提供し、看護師が治療の効果や有害事象にいち早く気づけるよう配慮します。こうして看護師の気づきによって得られた情報をもとに、医師に対する処方の提案や投薬設計の支援を行います。
臨床薬剤師には、医師や看護師とのあいだに良好な人間関係を築きつつ、薬学に基づいた客観的な視点を失わない高度なコミュニケーション能力が必要なのです。
5. 臨床薬剤師の今後の展望
米国をモデルとした臨床薬剤師が日本で根付き、増えつつある理由はいくつかあります。一つは、本来の薬剤師の業務であった調剤が自動化され、多くを製薬企業が担うようになったこと。調剤業務が減ったことで病院薬剤師は患者さんに向き合うようになりましたが、1992年に薬剤管理指導業務の報酬が400点に引き上げられたことも大きなきっかけとなっています。
もう一つはチーム医療への参加です。例えば海外の調査 では、臨床薬剤師が回診に加わることで不適切な薬物治療が是正された、と報告しています。調査を行った精神科病棟では、薬剤師が回診に加わったことで大量の多剤処方や不適切な処方が是正され、退院後も服薬の遵守率が高かったとしており、チーム医療に医薬品の専門家が加わることは非常に大きな戦力となることを示しています。
そして、臨床薬剤師の需要を押し上げる最大の要因は、超高齢社会の到来でしょう。日本人の死因は1981年以来がんがトップ を占めていますが、この40年のあいだに治療法や治療薬は大きく進歩し、分子標的薬などの新薬が次々と登場しています。また、高齢化に伴う生活習慣病の増加は多様な症状を呈するため多剤併用が日常的に行われています。より高度化、複雑化していく薬物治療を適切に行うには臨床薬剤師の専門知識が欠かせなくなっているのです。
こうした背景があるなかで、臨床薬剤師だけでなくすべての薬剤師の仕事はモノ(薬剤)からヒト(患者さん)へと確実に軸足を移しつつあります。患者さんのQOLを改善するための薬物治療のスペシャリストとして、臨床薬剤師の活躍のフィールドがさらに拡がっていくことは間違いないでしょう。
参照元:厚生労働省/がん対策について
6. まとめ
1989年に臨床薬剤師の原型となるファーマシューティカル・ケアの概念がアメリカで提唱されてから、日本で臨床薬剤師に対する取り組みが始まるまでおよそ10年を必要としました。そして、薬剤師レジデント制度が活発化するまでにさらに10年が過ぎ、さらに次の10年が経過した今、ようやく臨床薬剤師という存在が認知され始めています。その業務はこれまでのモノ(薬剤)中心からヒト(患者さん)中心へと変容し、チーム医療における医薬品のスペシャリストとして積極的に個別の治療に関わることが求められます。
最近になって臨床薬剤師を育成する薬剤師レジデント制度が本格化してきているのは、多職種連携であるチーム医療において薬剤師が不可欠なポジションであることを示しており、臨床薬剤師の需要が増えている証といえるでしょう。将来性のある新しいキャリアアップの選択肢として、臨床薬剤師を検討してみてはいかがでしょうか。
毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報
転職準備のQ&A
薬剤師の職場のことに関するその他の記事
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554