第3回 通院・入院から在宅へ
制度の狭間を埋める在学業務のきめ細かい評価


2024年度調剤報酬改定では、介護報酬との同時改定ということもあり、在宅業務に関して幅広く見直しが行われました。細かい変更点が多いのですが、現場の要望が適切に反映された改定内容だったと評価する声も聞かれます。
第3回目は、在宅業務関連の改定ポイントを詳しく見ていきます。なかでも、在宅業務体制に対する評価として初めて設けられた「在宅薬学総合体制加算」や、新たな役割の評価となる「在宅移行初期管理料」、特別養護老人ホームでの活動に対する「施設連携加算」などを中心に解説していきます。
処方箋交付前の処方提案や夜間・休日の緊急訪問を評価
月8回までの定期訪問の対象に
「注射による麻薬投与が必要な患者」を追加
2024年度調剤報酬改定では、保険薬局の在宅業務において、今まで制度の狭間で評価されていなかった部分にも光が当てられました。現場の声をよく聞いた改定、との感想も聞かれています。
「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」の算定要件の拡大もその一例です。処方箋の交付前に医師に処方提案した場合でも、その内容が処方箋に反映されれば算定可能になりました。在宅現場では、医師とともに患家を訪問し、その場で薬局薬剤師が行った提案が処方見直しにつながるケースも多く、そうした実績が改めて評価された形です。
また、訪問薬剤管理指導の訪問回数についての見直しも行われました。「在宅患者訪問薬剤管理指導料」では、月8回までの定期訪問が算定可能な対象として「注射による麻薬投与が必要な患者」が追加されました(表1)。
表1 要件などが見直された在宅業務関連の点数
※太字が今改定で変更・追加された部分
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 調 剤 報 酬 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 週2回かつ月8回まで算定可: 末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者、中心静脈栄養法の対象患者 |
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1、2 | 原則として月8回まで算定可: 末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者 |
|
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 (※計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合) |
新興感染症等の自宅・施設入所等の患者に対する訪問薬剤管理指導でも算定可 | |
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 ・夜間訪問加算 400点 ・休日訪問加算 600点 ・深夜訪問加算 1,000点 |
保険医の求めにより、開局時間外の休日、夜間、深夜に緊急訪問した場合に加算 対象:末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者 |
|
| 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2 ・残薬調整に係るもの以外 40点 ・残薬調整に係るもの 20点 |
処方箋交付前の処方提案の評価。提案が反映された処方箋を受け付けた場合に算定 | |
| 服薬管理指導料3 | ・介護老人福祉施設(特養)等で(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)を受けている患者でも算定可(月4回まで) | |
| 調剤基本料、薬剤調製料、調剤管理料、服薬管理指導料3、外来服薬支援料2、薬剤料、特定保健医療材料料 | 介護医療院または介護老人保健施設の入所患者について、往診を行う医師が専門的な薬学管理を必要とする薬剤(※)を処方した場合に限り算定可 ※抗悪性腫瘍剤、疼痛コントロールのための医療用麻薬、HIF-PH阻害剤、抗ウイルス剤(B型肝炎、C型肝炎、HIV)など |
|
| 薬剤調製料 無菌製剤処理加算 麻薬 | 麻薬を含む2以上の注射薬の混合(生理食塩水等で希釈する場合を含む)、麻薬の注射薬(原液)の充填 | |
| 介 護 報 酬 |
居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費 ・単一建物居住者が1人 518単位 ・ 〃 2~9人 379単位 ・ 〃 10人以上 342単位 ・情報通信機器を用いた場合 46単位 |
|
| 居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養 管理指導費 ・医療用麻薬持続注射療法加算 250単位 ・在宅中心静脈栄養法加算 150単位 |
・医療用麻薬持続注射療法を行っている患者(オンラインでの服薬指導不可) ・在宅中心静脈栄養法を行っている患者(オンラインでの服薬指導不可) |
医療用麻薬が、がんだけでなく心不全などの患者さんにも用いられていることを踏まえた見直しです。今年度の改定では「調剤後薬剤管理指導料」の対象にも慢性心不全が追加されましたが、高齢化とともに今後地域で関わる機会が増えそうです。
緊急訪問も末期がんなどで
「原則月8回まで」算定可
「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」については、これまで計画的な訪問対象の疾患の急変に伴う「同指導料1」と、それ以外の疾患に伴う「同指導料2」とを合わせて月4回までの算定とされていました。改定後は、「末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者」については「原則として月8回まで」算定が認められました。
なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料とは異なり、中心静脈栄養法はその対象に含まれません。また、「原則として」と入っているように、「特に医療上に必要がある場合で保険医の発行した処方箋に基づくとき」に限っては8回を超えて算定が可能です。
さらに、同指導料1に夜間・休日・深夜訪問の加算も新設されました。加算の対象となるのは、「末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者」で、保険医の求めにより実施した場合です。今改定では、働き方改革の観点から「24時間対応」という表現はなくなりましたが、地域の医薬品供給拠点として夜間・休日・深夜にもしっかりと対応することが求められています。
2024年の診療報酬改定による薬剤師の転職市場の変化が気になる方は、薬剤師専任のキャリアアドバイザーに相談してみませんか?
企業の採用担当にアピールすべきご自身の強みや今後のキャリアが、見つかるかもしれません。
注目の「在宅学宅総合体制加算」と「在宅移行初期管理料」
「在宅薬学総合体制加算」で体制評価へ
無菌調製設備体制などに高配点
改定を経るたびに、在宅業務の存在感は大きくなってきていますが、今回の改定では薬局の体制を評価する調剤基本料の加算として「在宅薬学総合体制加算」が新設されました。同加算は、従来の在宅患者調剤加算(薬剤調製料の加算)をベースにしたものですが、位置づけが見直され、薬局の基本的機能のなかで在宅業務体制が初めて評価されました。
大きく変わったのは、評価が2区分になり、今までと同じ15点の「同加算1」の上に、50点と高配点の「同加算2」が設けられた点です(表2)。
表2 在宅薬学総合体制加算
[調剤基本料]
(新)1 在宅薬学総合体制加算1 15点
2 在宅薬学総合体制加算2 50点
○在宅薬学総合体制加算1
- (1)在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
- (2)在宅薬剤管理の実績24回以上/年
- (3)開局時間外における在宅業務対応
(在宅協力薬局との連携含む) - (4)在宅業務実施体制に係る地域への周知
- (5)在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・ターミナルケア)
及び学会等への参加 - (6)医療材料及び衛生材料の供給体制
- (7)麻薬小売業者の免許の取得
- (1)加算1の施設基準を全て満たしていること
- (2)開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務)
- (3)かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計24回以上/年
- (4)高度管理医療機器販売業の許可
- (5)ア又はイの要件への適合
- ア がん末期などターミナルケア患者に対する体制
- ①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上)
- ②無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備
- イ 小児在宅患者に対する体制(在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児
- 特定加算及び乳幼児加算の算定回数の合計6回以上/年)
同加算2では、直近1年での24回以上のかかりつけ薬剤師指導料等の算定実績に加え、医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上)、高度管理医療機器販売業の許可や無菌調製設備といった、より高度な体制が必要とされています。他の薬局の無菌調製の設備を共同利用している場合は同加算2は算定できず、日常管理や定期的な保守点検などにより、必要時に速やかに無菌調製ができる状態を維持しておくことも求められています。
直近1年間で計24回以上
様々な在宅業務の形を評価
一方で、在宅薬学総合体制加算1、2に共通する施設基準は、在宅患者調剤加算を踏襲したものですが、在宅業務の実績要件については見直されました。
従来、算定回数のカウント対象は在宅患者訪問薬剤管理指導料と、介護保険の(介護予防)居宅療養管理指導費のみでしたが、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急時等共同指導料も追加されました。
加えて、自グループ以外の薬局に在宅協力薬局として連携した場合や、ひと月の算定回数上限を超えて訪問した場合も回数に含めることができるようになりました。
その分、算定回数も直近1年間で計24回以上と引き上げられました。オンラインでの服薬指導管理は以前と同様にカウントの対象外ですが、より幅広く在宅業務が評価された形です。
訪問薬剤管理指導に入る前の
患家訪問で求められていること
今改定では、新たな在宅業務が評価されたことも注目ポイントです。在宅医療に移行予定の患者さんに対し、訪問薬剤管理指導に入る前段階で訪問して必要な情報収集や指導を行うことについて「在宅移行初期管理料」が新設されました(表3)。
表3 在宅移行初期管理料
(新)在宅移行初期管理料 230点(1回に限り)

- (1)対象:ア及びイを満たす患者のうち、薬剤師が患家を訪問して重点的な服薬支援を行う必要性があると判断したもの
- ア 認知症、精神障害者である患者など自己服薬管理が困難な患者、人工呼吸器の装着やその他日常生活で医療を要する状態1)にある18歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期のがん患者、注射による麻薬投与が必要な患者
- イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも単一建物診療患者が1人の場合)に係る医師の指示のある患者
- (2)実施する業務:
- ア 患者・家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報を収集
- イ 患家の残薬の確認・整理、服薬管理方法の検討・調整
- ウ 日常での適切な服薬管理、ポリファーマシーへの対応、服用回数減の観点も踏まえ、必要に応じて医師等と使用薬剤の内容を調整
- エ 在宅療養に必要な情報を在宅療養を担う多職種と共有
- オ 退院直後の場合、入院していた医療機関と連携し、入院中の処方や退院時指導の内容などに関する情報提供文書を活用した服薬支援を行うことが望ましい
- (3)在宅療養を担う医師及び介護支援専門員に対して必要な情報提供を文書で行う
- (4)計画的な訪問薬剤管理指導の実施前であって別の日に患家を訪問して(2)の業務を実施した場合に算定
- (5)在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(単一建物診療患者が1人の場合に限る)の算定した初回算定日の属する月に1回に限り算定
服薬状況や居住環境、同居家族など薬学的管理に関わる情報の収集や、残薬の確認・整理、服薬管理方法の検討・調整、医師との処方内容調整などが算定要件としてあげられています。
対象となるのは、下記のような状態像(ア)と、居住環境(イ)の要件をともに満たした患者さんです。
- ア 認知症や精神障害があるなど自己服薬管理が困難な患者、人工呼吸器の装着やその他日常生活で医療を要する状態1)にある18歳未満の障害児、6歳未満の乳幼児、末期がん患者、注射による麻薬投与が必要な患者
- イ 医師から在宅患者訪問薬剤管理指導料、(介護予防)居宅療養管理指導費の指示のある、単一建物診療患者(単一建物居住者)が1人の場合
なお、「単一建物診療患者(居住者)が1人の場合」についての考え方は、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の要件に準じます。個人在宅で、家族のなかに別に訪問薬剤管理指導を受けている人がいても算定は可能です。
医師のほかケアマネジャーへの
文書での情報提供も要件に
在宅療養への移行は、入院・入所していた医療機関や介護施設からというパターンが多いと思いますが、移行パターンについての要件はなく、外来通院からの切り替えでも対象になります。
ただし、入院前に訪問薬剤管理指導を実施していた患者さんが退院後に自宅に戻る場合など、すでに在宅療養における環境が整っている場合は算定できません。あくまでも、計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前の段階における薬学的管理・指導に対する評価だからです。
また、介護保険の(介護予防)居宅療養管理指導費と同様、医師に加えて介護支援専門員(ケアマネジャー)への文書での情報提供が義務づけられていることもポイントです。この場合、服薬情報等提供料は算定できません。
「服薬情報等提供料2」もそうですが、今改定では薬局からケアマネジャーへの情報提供を盛り込んだ評価が増えました。要支援・要介護の患者さんに対して、外来通院時から薬局と、介護サービスの調整役であるケアマネジャーが連携することで、患者さんに対する切れ目のない支援が期待されています。
介護施設で広がる薬局薬剤師の活動の評価
介護老人保健施設(特養)の
ショートステイでの服薬指導も評価
介護報酬との同時改定ということもあり、介護施設における薬局薬剤師の活動にも改めてスポットが当てられました(表1)。なお、今改定では、特別養護老人ホーム(特養)が「介護老人福祉施設」に、老人保健施設(老健)は「介護老人保健施設」へと表記が改められていますが、表記の違いは根拠法が異なるためで、施設の内容には実質的に変わりはありません。
「服薬管理指導料3」は、介護老人福祉施設(特養)の入所者を対象にした点数ですが、一時的に入所する短期入所生活介護、いわゆるショートステイの患者さんでも算定できることが明確化されました。同時に、服薬管理指導料3については入所者、ショートステイ利用者を問わず、月4回までと算定回数の上限も設けられました。これは、定員29名以下の小規模な地域密着型介護老人福祉施設でも同じです。
施設職員と協働での服薬支援を
「施設連携加算」で評価
介護老人福祉施設(特養)などの職員と協働して、重点的な服薬管理支援の必要な患者さんに対応した場合の評価として、外来服薬支援料2に「施設連携加算」も新設されました。同加算の対象となるのは、以下のいずれかの状況で、施設職員と協働した服薬支援や、これまでとは異なる方法などでの服薬支援が必要と、薬剤師が認めた場合です。
- 入所時、服用薬剤が多い
- 新規の薬剤処方や用法・用量の変更
- 施設職員からの副作用や体調の変化などの相談に基づき、薬剤師が服薬状況等を確認した結果
実施に当たっては、患者さんまたは家族の同意を得て、処方医にその必要性について了解を得ることが必要です。なお、施設職員と協働した服薬管理において薬局薬剤師には、施設における患者さんの療養生活の状態を直接確認するとともに、薬剤の保管や服薬、残薬の状況など必要事項を確認することが義務づけられています(表4)。
表4 施設連携加算
(新)外来服薬支援料2 施設連携加算 50点(月に1回に限り)
[主な算定要件]- (1)患者の服薬状況等に基づき継続的に適切な服薬が行えるよう、特に重点的な服薬管理の支援が必要な以下の場合に限り算定
- ア 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所時であって、服用している薬剤が多く、入所後の服薬管理について当該施設職員と協働した服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合
- イ 新たな薬剤の処方、もしくは薬剤の用法・用量の変更があった患者のうち、これまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合
- ウ 服用薬に関する副作用等の状況、体調の変化等における施設職員からの相談に基づき薬剤師が患者の服薬状況等の確認を行った結果、これまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合
- (3)他の薬局で調剤された薬剤や医療機関で院内投薬された薬剤等の調剤済みの薬剤も含めて一包化等の調製を行う
- (4)施設職員との協働した服薬管理については、施設における患者の療養生活の状態を薬剤師自らが直接確認し、薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診に関する情報、服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)、重複服用、相互作用、実施する服薬支援措置、施設職員が服薬の支援・管理を行う上で留意すべき事項等に関する確認等を行った上で実施する
- (5)単に施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、施設職員に服薬の支援・管理に関する情報共有等を行ったのみの場合は算定できない
介護老人保健施設(老健)や
介護医療院での評価も
一方、薬剤師の配置義務のある介護医療院や介護老人保健施設(老健)においても、保険薬局の薬剤師の活動が一部評価されました。施設の担当医以外の医師による、抗がん剤や医療用麻薬などの処方箋を受けた場合には、調剤基本料や薬剤調製料、服薬管理指導料3などが算定できるようになりました(表5)。
表5 高齢者施設における調剤報酬の取扱いの見直し
| 介護医療院 | 介護老人保健施設 | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
||
|---|---|---|---|---|
| 施設 配置 基準 |
医師 | ○ Ⅰ型:3以上/ 48:1以上 Ⅱ型:1以上/100:1以上 |
○ 1以上 |
○ 必要数(非常勤可) |
| 薬剤師 | ○ Ⅰ型:150:1 以上 Ⅱ型:300:1 以上 |
○ 適当数(300:1) |
× | |
| 薬剤管理の 現状等 |
|
|
||
| 調剤報酬 | 現行 | 交付された処方箋を応需しても算定不可 | 算定可能 | |
| 改定後 | 算定可能※1 | 算定可能 ショートステイの利用者も算定可能 |
||
※1 施設の医師以外の医師が高度な薬学的管理を必要とする薬剤(※2)に係る処方箋を発行した場合に限り、以下の調剤報酬が算定できる
調剤基本料、薬剤調製料、調剤管理料、服薬管理指導料3、外来服薬支援料2、薬剤料、特定保険医療材料料
※2 抗悪性腫瘍剤の費用、HIF-PH阻害剤の費用、疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用、抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用
これらの見直しは、介護施設において薬局薬剤師による薬学的管理や服薬支援などのニーズがあることの表れでもあります。高齢者の増加や高年齢化が進むなかで、医療と介護を同時に必要とする患者さんは、今後暫くの間は増加の一途をたどります。そうした患者さんの薬物療法の効果と安全性の担保のためにも、在宅多職種と連携した薬局薬剤師の活動の広がりが期待されています。
2024年診療報酬改定について、理解が深まったでしょうか?
常に知識を最新化してスキルアップし続けるあなたに、おすすめの薬剤師求人や求人特集をご紹介します。
・エリアマネージャーや幹部候補などハイキャリアを目指す薬剤師求人特集
・未経験OKの管理薬剤師やエリアマネージャー候補の薬剤師求人特集
・在宅業務ありの薬剤師求人一覧
マイナビ薬剤師では、薬剤師専任の転職のプロがあなたの転職を全面サポートします。
まずは将来に向けてのキャリア相談からでも、お気軽にご登録ください。
(参考資料)
◎厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」
◎厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項」
◎厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年度厚生労働省告示第57号)
※本記事は2024年6月11日までの疑義解釈を参考に執筆しています。
医療系出版社勤務後、2000年に独立。薬剤師としての知識を活かしつつ、医療分野・介護分野を中心に取材を行う。
著書『福祉・介護職のための病院・医療の仕組みまるわかりブック』
『イラストで理解するケアマネのための薬図鑑』(共著)など。
マイナビ薬剤師転職サポートの流れ
-

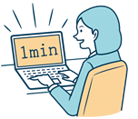
ご登録
ご登録は1分で完了!担当のキャリアアドバイザーからご連絡を差し上げます。
-


求人のご紹介
ご希望に合った求人をご紹介!求人のポイントなど、詳細もご説明いたします。
-

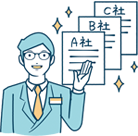
面接・条件交渉
面接対策をアドバイス!また、給与交渉や面接の日程調整等を代行いたします。
-


転職成功!!
入社日の調整や手続きなど、ご入社までサポートいたします。
その他の記事
-
 PICK UP
PICK UP第2回 薬局での管理指導などの要件見直し 評価や要件が区分される傾向に
-
 PICK UP
PICK UP第1回 6年ぶりの介護報酬との同時改定 保険薬局と病院の診療報酬の全体像をつかむ
-
 PICK UP
PICK UP薬薬連携で保険薬局と医療機関に求められているもの
-
 PICK UP
PICK UP地域支援体制加算の算定対象の拡大とリフィル処方箋導入で求められる薬局の役割
-
 PICK UP
PICK UP調剤業務の評価体系と加算の見直しによる影響を考える
-
 PICK UP
PICK UP2022年度診療報酬改定で薬剤師業務はどう変わる? 改定の全体像と背景を読む
-
 PICK UP
PICK UP2020年度診療報酬改定 在宅業務と薬局機能 調剤基本料見直しによる薬局への影響は?
-
 PICK UP
PICK UP常勤要件緩和で病院薬剤師に求められる役割
-
 PICK UP
PICK UP手厚くなった薬局の
「対人業務」評価の背景は? -
 PICK UP
PICK UP医療制度や薬機法との関係は?
“流れ”で考える2020年度診療報酬改定
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554
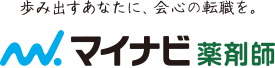





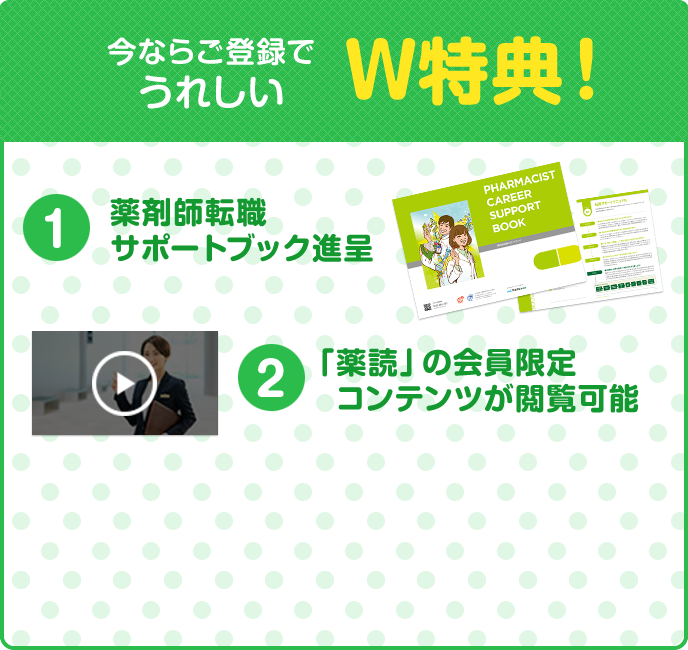
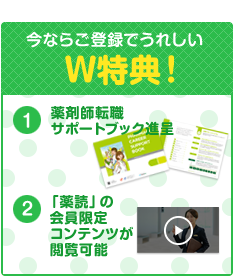
 はじめて転職される方へ
はじめて転職される方へ