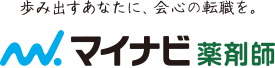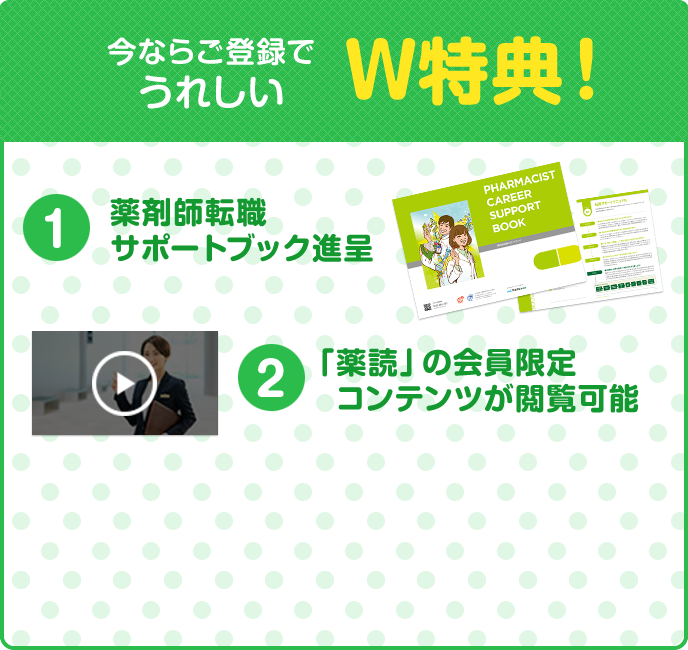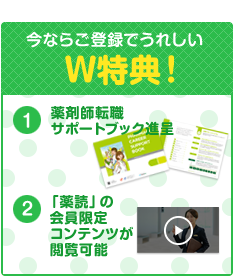コントラクトMRとは?仕事内容や年収・メリットについて解説

MR(医薬情報担当者)という職業には、製薬企業の正社員として業務にあたるMRと、外部のサービス事業者から製薬会社に派遣されるコントラクトMR(派遣MR)があります。ただし、いずれも医薬品の情報を医師や薬剤師に提供して販売につなげる営業職であり、業務内容に大きな違いはありません。
本記事では、近年製薬業界で存在感を増しているコントラクトMRを取り上げ、その特徴や仕事内容、年収、メリットなどを解説します。
目次
1.コントラクトMRとは
コントラクトMRとは、クライアント企業との労働契約に基づいて、医薬情報提供活動を行うMRのことです。仕事の内容は製薬企業のMRと変わりませんが、所属先は製薬企業ではなく、CSO(Contract Sales Organization:医薬品販売業務受託機関)と呼ばれるアウトソーシング企業になります。
つまり、コントラクトMRは、「CSOから製薬企業に派遣されたMR」というわけです。派遣MRとも呼ばれますが、基本的にはCSOに正規雇用された正社員であり、契約社員ではありません。
1-1.MRとの違い
所属する企業が異なるだけで、コントラクトMRと製薬企業のMRの仕事内容に違いはありません。
製薬企業の通常業務に従事するか、新規事業の立ち上げ・新薬リリースなどのプロジェクト単位で請負事業に携わるかによって、契約期間は若干異なりますが、基本的には製薬企業のMRと同じ業務をこなします。
コントラクトMR を含めたMRの業務内容や資格、採用状況などに関する詳しい解説は、「医薬情報担当者(MR)」のページをご覧ください。
1-2.製薬企業とCSOの違い
ひと口に製薬企業といっても、プライマリー領域と呼ばれる一般的な疾患向け医薬品を基幹事業とする企業もあれば、がんや免疫疾患、HIVなど専門性の高いスペシャリティ領域の医薬品に注力している企業もあります。
内資系の大手を例に取ると、本社は研究開発部門と営業部門とに大別され、製造部門である工場は別会社となっているケースが多くみられます。営業部門は担当地域別にわかれており、さらにプライマリー領域やオンコロジーなどのスペシャリティ領域に分類されます。
一方のCSOは、製薬企業の営業部門に特化したアウトソーシングを請け負う企業であり、品質管理や開発などに携わる部門はありません。
また、製薬企業のMRには異動や配置転換があり、希望する勤務地で継続的に働けないケースや、部署・職種が変わるケースもありますが、CSOは経営層や間接部門を除けばほぼ全員がMR。職種が変わることはもちろん、配置転換、転勤などもありません。
1-3.コントラクトMRの雇用状況
MR認定センターが発表した「2024年版 MR白書」によれば、2023年度のMR総数は46,719人で、コントラクトMRの数は3,711人。割合としては、さほど多くありません。労働形態は派遣型が圧倒的に多く、約98%が派遣型、残りわずかが請負型として勤務しています。また、雇用先の規模をみると、中堅規模以上から大企業を中心に派遣されており、500〜999名企業(1,884人)と1000名以上の企業(865人)の合計人数が、約74%を占めています。
今後は、CSO活用企業の増加や、オンコロジーなどのスペシャリティ領域における需要増加が予想されるため、コントラクトMRの活躍の場はさらに広がっていくことでしょう。MSLに対する注目度の高まりも、コントラクトMRの需要を後押しすると考えられます。
2.コントラクトMRの仕事内容
基本的に、コントラクトMRの仕事内容は、派遣先製薬企業のMRに準じます。ただし、アウトソーシングする製薬企業側の目的はさまざまで、従事する業務内容はほぼ同じでも、コントラクトMRに求められる成果と評価はケースバイケースです。
欠員補充ならごく一般的なMR活動となりますが、販売エリアの強化や新規開拓では短期的な売り上げが求められるでしょう。主力製品の営業強化では、チームの一員として活動することもあります。
2-1.派遣先でのMRの業務に従事する
派遣先の製薬企業が求める目的が欠員補充、あるいは通常のエリア営業の増員であれば、一般的なMRの業務に従事することになります。
以下に、一般的なMRの業務例を紹介しましょう。
<一般的なMRの一日>
朝:勤務先によって時間は異なりますが、おおむね7:00~8:00ごろに、自宅から医薬品卸に向けて出発。MS(卸の営業担当)と営業先についての情報交換や、活動報告といった打ち合わせを行います。MRは基本的に直行直帰で、移動には営業車を使用します。卸をまわり終えたらオフィスに出社し、医療機関訪問の準備をします。
昼:午前の外来診療終了後から午後の診療開始までが、医師や薬剤師との1回目の面談時間となります。最近は事前アポイントを必須とする病院が多いため、分刻みの面談となることも珍しくありません。効率よく面談をこなし、午後の診療が始まるころに遅めの昼食を取ります。
夕:午後の外来診療終了後が、2度目の面談タイムです。かつては、医師の出待ちをするMRの姿もみられましたが、現在はほとんどの病院で出待ちが禁止されています。なお、午後の面談では、次の診療がある午前よりも、じっくりと医師との会話に臨めます。その場では答えられない質問や医師からの依頼に対しては、派遣先企業のDI室などに確認します。
夜:チームミーティングや事務処理などがなければ、19:00~20:00くらいに帰宅できます。その日の報告書を作成し、派遣先の上長に提出すれば一日の業務は終了です。
2-2.派遣先の決め方
コントラクトMRの派遣先については、派遣されるMRの希望やスキルと、派遣先の製薬企業が求めるスキル・目的・期間などを比較したうえで決められます。
派遣先から求められるスキルは多様化しており、プライマリーMRやスペシャリティMRだけでなく、地域包括ケアに対応するMR、薬剤師専門に情報提供を行うMRなどが求められるケースもあります。
ちなみに、コントラクトMRが多く活用されている領域は、循環器、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病や中枢神経系となっており、慢性期医療や精神科市場が主な活躍の場といえそうです。
参照元:日本CSO協会/国内CSO事業に関する実態調査 -2022年度版-
2-3.派遣先の変更頻度や一般的な期間
コントラクトMRの派遣期間は2年程度といわれますが、実際は派遣先企業のニーズや、携わるプロジェクトの内容によってさまざまです。当初の契約期間は1~2年だとしても、延長や再契約により長期化することも珍しくありません。
派遣の変更頻度についても、1~2年ごとになるケースが多いようですが、これも一概にはいえません。
なお、派遣契約満了によって、次の派遣開始まで待機期間が生じた場合でも、原則としてCSOの正社員であるコントラクトMRの収入は維持されます。
3. コントラクトMRの平均年収
厚生労働省の職業情報提供サイトによれば、MRの全国平均年収は579.5万円とされています。一方、製薬企業の平均年収ランキングは、トップの外資系企業が約1500万円なのに対し、50位に位置する企業は700万円弱。2倍強の差があります。そのため、派遣される企業やプロジェクト、コントラクトMR自身のスキルや経験値によって、収入に大きな差が出るものと心得ておきましょう。
大手CSOの求人情報を確認すると、MR経験者としてコントラクトMRに転職する場合、年収は500万~700万円台が相場となっており、未経験では400万円程度からのスタートが多いようです。MRの年収はスキルや経験年数によっても変わりますが、営業職であることから、成果による評価が大きいという点を忘れてはなりません。
4.コントラクトMRのメリット
コントラクトMRは、一つの製薬企業に縛られないのが大きな魅力であり、メリットです。コントラクトMRとして働くにあたっては、ほかにも多くのメリットがあるので、以下でそのいくつかを紹介しましょう。
4-1.CSOに所属しながら複数の製薬企業で働ける
CSOに所属しながら、1~2年のスパンで複数の製薬企業で働けるのは、コントラクトMRの最大のメリットです。
製薬企業のMRは、コントラクトMRと違って、自身が所属する製薬企業の製品しか扱うことができません。そのため、活動範囲や対象医療機関、担当製品などが限定的になり、MRとしての経験も狭い領域に限られがちです。一方、プロジェクトによって異なる企業に派遣されるコントラクトMRは、多くの疾患領域や医薬品を経験できる機会に恵まれています。
事実、日本CSO協会所属のCSOに所属するコントラクトMRの場合、51.3%に7領域以上の経験があり、5領域以上の経験者を加えると6割以上を占めています。これからMRを目指すのであれば、コントラクトMRとして多種多様な領域で経験を積み、知識や経験を磨くのもよいでしょう。
加えて、世界的な外資系企業や、内資の大手製薬企業でMRとして働くチャンスがあるのも、コントラクトMRならではの利点です。
参照元:日本CSO協会/国内CSO事業に関する実態調査 -2022年度版-
4-2.製薬企業への転職も視野に入れられる
日本CSO協会の調査によると、コントラクトMRの活用目的を「欠員補充」「産休対応」「社員化」としている製薬企業は、けっして少なくありません。つまり、製薬企業はコントラクトMRの活用を人事戦略の一部(キャリア採用のソース)とみなしており、CSO側もその点を自覚しているといえます。
CSOは派遣業でありながら正社員としてMRを雇用しているわけですから、ある程度経験を積んだ社員の一部を製薬企業に送り出すことで、効率よく社内の新陳代謝が図れます。そうしたシステムの中で活動できるのはCSO、コントラクトMR双方にとってメリットといえるでしょう。
4-3.勤務地の希望が通りやすい場合も
製薬企業は規模が大きくなるほど営業所の数も多くなり、異動や転勤の割合が高まります。近年、製薬企業のMRは減少傾向にあり、欠員が出た場合は遠隔地からの転勤によって補充されることも少なくありません。しかし、一方では働き方改革の推進や女性MRの増加によって、異動や転勤を控える方針の企業もみられます。
そうした状況をうけて、コントラクトMRのニーズは増えており、ニーズに応えるために全国規模で求人を展開するCSOも少なくありません。
基本的に、CSOは希望勤務地でのマッチングを進めてくれるので、製薬MRよりもコントラクトMRのほうが、勤務地の希望は通りやすいといえるでしょう。ただし、未経験からのMR転職の場合、この限りではないようです。
5.まとめ
CSOに所属するコントラクトMRと製薬企業MRを比較した場合、業務内容に関する違いはほとんどありません。ただし、一つの企業に縛られないコントラクトMRのほうが、幅広い経験とキャリア形成が望めるというメリットがあります。
また、未経験からMRとしてのキャリアを積めるのは、CSOに所属する大きな魅力であり、コントラクトMRとして経験を積んだのち、製薬企業に転職するというキャリアプランも夢ではありません。
マイナビ薬剤師では、専任のキャリアアドバイザーがコントラクトMRへの転職をマンツーマンでサポートしていますので、安心して転職活動が進められます。コントラクトMRへの転職を検討する際は、まずマイナビ薬剤師に登録して、キャリアドバイザーの無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
マイナビ薬剤師【営業(MR・MS・その他)の求人一覧】
毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報
おすすめの薬剤師求人一覧
転職準備のQ&A
薬剤師の職場のことに関するその他の記事
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554