第4回 薬薬連携で保険薬局と医療機関に求められているもの


前回の2020年度診療報酬改定では、がんや糖尿病、吸入薬などの領域で医療機関と保険薬局の連携が評価され、関心を集めました。2022年度改定でも、地域包括ケアシステムの構築が進むなかで、外来から入院へ、入院から外来・在宅へと切れ目なく薬学的管理をつなぐために連携が重視され、新たな評価も設けられています。
最終回となる第4回目は薬薬連携をテーマに、薬局にも関連のある医療機関の診療報酬と合わせてポイントを見ていきます。
医療的ケア児への切れ目ない薬学的管理のために
病院から薬局への退院時の情報提供を評価
障害や難病のため、日常的にたん吸引や人工呼吸器による呼吸管理などを必要とする子どもを「医療的ケア児」といいます。以前の記事でも触れましたが、今改定では医療的ケア児に対する薬学的管理の評価が柱の1つとされました。
2019年の成育基本法の施行を受けて、2021年に閣議決定された「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」(以下、成育医療等基本方針)で、医療体制の整備などが掲げられたことが背景にあります。
調剤報酬では「小児特定加算」が新設されました(2回目記事参照)。病院においても、病棟薬剤業務実施加算が算定できる病棟に小児病棟(小児入院医療管理料の算定病棟)が加えられ、医療的ケア児などの退院に際しての服薬指導と薬局への情報提供が「退院時薬剤情報管理指導連携加算」として新たに評価されています(表1)。
表1 小児入院医療管理料 退院時薬剤情報管理指導連携加算
小児入院医療管理料1~5
- (新)退院時薬剤情報管理指導連携加算 150点(退院時1回)
-
小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している
- ・小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者
- ・医療的ケア児である患者
【算定要件】
-
当該保険医療機関の医師又は医師の指示に基づき薬剤師が、小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、当該患者又はその家族等に対し退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行い、当該患者又はその家族等の同意を得て、患者又はその家族等が選択する保険薬局に対して当該患者の調剤に関して必要な情報等を文書により提供した場合に、退院の日に1回に限り算定する。保険薬局への情報提供に当たっては、以下の事項を記載した情報提供文書を作成し、作成した文書の写しを診療録等に添付すること。
- ア 患者の状態に応じた調剤方法
- イ 服用状況に合わせた剤形変更に関する情報
- ウ 服用上の工夫
- エ 入院前の処方薬の変更又は中止に関する情報や変更又は中止後の患者の状態等に関する情報
- 情報文書の交付方法は、患者又はその家族等の選択する保険薬局に直接送付することに代えて、患者又はその家族等に交付し、患者又はその家族等が保険薬局に持参することでも差し支えない。
- 患者1人につき複数の保険薬局に対し情報提供を行った場合においても、1回のみの算定とする。また、死亡退院の場合は算定できない。
薬局への情報提供では、医療機関の医師または薬剤師が、入院中の処方薬の変更・中止に関する情報とともに、その患児の状態に応じた調剤方法や服用上の工夫などを文書で送ることが求められています。日本では小児用製剤が少なく、錠剤の粉砕など調製に工夫を要する場合もあります。加えて、医療的ケア児は状態や病状が多様なため、退院時にこれらの情報を、病院と薬局との間で共有することが重要になります。
先の成育医療等基本方針にも、「小児医療等における専門的な薬学管理に対応するため、医療機関・薬局の医療従事者間の連携を推進する」ことが盛り込まれています。すでに日本薬剤師会では、2021年度から10都府県の薬剤師会で医療的ケア児などの薬物療法に関し、病院・薬局連携のモデル事業を始めています。今回の診療報酬での評価とこれらの施策が、小児薬物療法を担える薬局の増加や、専門領域としての確立のきっかけとなることが期待されます。
周術期の薬剤師業務の評価で
術前から術後まで一貫して介入
今改定で、特に急性期病院の薬剤師に注目されたのは、周術期の薬剤管理の評価です。医師の働き方改革を進めるためのタスクシフト・シェアの観点から、手術室の薬剤師が病棟の薬剤師と連携して薬学的管理を実施した場合に、「麻酔管理料」の「周術期薬剤管理加算」が算定できることになりました(表2)。
表2 周術期の薬学的管理の評価
麻酔管理料(Ⅰ)・麻酔管理料(Ⅱ)
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合
- (新)周術期薬剤管理加算 75点
- 専任の薬剤師が周術期における医療従事者の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する周術期薬剤管理を病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して実施した場合に算定する。
-
周術期薬剤管理とは、次に掲げるものであること。なお、ア及びイについて、その内容を診療録等に記載すること。
- ア 「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について(令和3年9月30日医政発0930第16号)」の3の3)①等に基づき、周術期の薬学的管理等を実施すること。
- イ アについては病棟薬剤師等と連携して実施すること。
-
ウ 時間外、休日及び深夜においても、当直等の薬剤師と連携し、安全な周術期薬剤管理が提供できる体制を整備していること。
また、病棟薬剤師等と連携した周術期薬剤管理の実施に当たっては、「根拠に基づいた周術期患者への薬学的管理ならびに手術室 における薬剤師業務のチェックリスト」(日本病院薬剤師会)等を参考にすること。
【施設基準の概要】
- 当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
- 病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 周術期薬剤管理に関するプロトコルを整備していること。なお、周術期薬剤管理の実施状況を踏まえ、定期的なプロトコルの見直しを行うこと。
- 周術期薬剤管理加算の施設基準における専任の薬剤師、病棟薬剤業務実施加算の施設基準における専任の薬剤師及び医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各薬剤師が周術期薬剤管理を実施するにつき必要な情報が提供されていること。
- 医薬品の安全使用や、重複投与・相互作用・アレルギーのリスクを回避するための手順等を盛り込んだ薬剤の安全使用に関書(マニュアル)を整備し、必要に応じて当直等の薬剤師と連携を行っていること。
手術室への薬剤師の配置は他の病棟などに比べて遅れていましたが、この評価を契機に進むことが予想されます。
周術期関連の業務では、以前から手術予定の患者に対して、入院前に薬剤師が外来で術前休薬の確認・指導を行う取り組みが見られていました。
今回の加算の新設により、術前から術中、術後(病棟業務)まで一貫して薬剤師の関与する流れがつくられたといえるでしょう。そのため、周術期薬剤管理加算では、「病棟薬剤師等との連携」も算定要件とされています。
入院前連携で薬局から
医療機関への情報提供を評価
調剤報酬でも今回、医療機関の求めに応じて、薬局が入院予定の患者の服薬情報を提供した場合に算定できる「服薬情報等提供料3」が新設されました(表3)。
表3 服薬情報等提供料の見直し
- (新)服薬情報等提供料3 50点(3月に1回に限り)
- 入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。
- これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
【保険医療機関の求めについて】
患者が入院を予定している保険医療機関からの求めのほか、患者が受診している他の保険医療機関からの求めを含む。
【一元的に把握する情報】
患者の服用薬等については、当該保険薬局で調剤した薬剤、他の保険薬局で調剤された薬剤、保険医療機関で院内投薬された薬剤等。
【医療機関への情報提供の内容】
- 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
- 服用中の薬剤の一覧
- 患者の服薬状況
- 併用薬剤等の情報
これは入院の際、患者の持参薬を確認するために必要とされる情報を薬局が提供することを促すものです。予定入院は手術や検査を目的としていることが多く、術前の薬学的管理にもつながる連携です。
薬局薬剤師が、入院予定の患者の同意を得て服用薬の情報を一元的に把握し、必要に応じて服用薬の整理を行うとともに、医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に、3カ月に1回算定できます。服用薬の整理が必要かは、患者が持参した薬を見たうえで薬局薬剤師が判断します。薬剤情報の一元的把握をしているかかりつけ薬局であれば、算定したい点数です。
なお、「医療機関からの求め」については、入院する医療機関だけでなく、患者が受診している他の医療機関からの要請であっても対象になります。
提供する情報は、受診中の保険医療機関や診療科等に関する情報、服用中の薬剤の一覧、患者の服薬状況、併用薬剤などです。医療機関にとって把握しにくい他院での処方薬や実際の服薬状況などの情報を、薬局に期待する施設は少なくありません。
図1は、2020年度診療報酬改定の結果検証のための調査結果ですが、医療機関側が持参薬整理の際に必要とする情報として、「他の医療機関への受診状況」「入院前に中止している医薬品」「服用中だが持参していない薬」などが上位にあがっています。
図1 持参薬の整理の際に必要な情報
なお、入院予定の患者に限らず、医療機関から求めがあった場合の情報提供は「服薬情報等提供料1」で、薬局薬剤師が必要性を認めた場合などに行う医療機関への情報提供は「服薬情報等提供料2」で評価され、それぞれ月1回まで算定が可能です。
同じ情報を同じ医療機関に提供するのでなければ、同じ月に服薬情報等提供料3と併行して、1、2を算定することもできます。
外来化学療法での診療報酬見直しと
病院薬剤師への影響
専門医療機関連携薬局の認定もあり、最近、薬薬連携が特に活発化しているのはがん領域です。前回の改定では、外来がん化学療法において病院と薬局の薬薬連携を初めて評価。病院の医師または薬剤師が、薬局などに文書での情報提供や年1回以上の研修会などを実施することに対して「連携充実加算」が創設されました。
それと対をなす形で、薬局がレジメン等に基づいた薬学的管理・指導や、電話での患者への体調などの確認、病院への情報提供などを行うことも「特定薬剤管理指導加算2」で評価されています。
今改定では、薬局に直接的な影響はないものの、病院薬剤師の外来化学療法での患者指導に関わる見直しが行われました。
連携充実加算のベースとなっている、「外来化学療法加算」が改組され、がんの外来化学療法は新設された「外来腫瘍化学療法診療料」で評価されることになったのです。それに伴って連携充実加算の算定には、外来腫瘍化学療法診療料1の届け出が必要になりました。
同診療料は、がん化学療法を安心・安全に実施することを重視した点数です。外来化学療法加算と同様に、注射によるがんの化学療法を評価したものですが、副作用発現時の管理や緊急時の相談対応などの体制も含めて、包括的に評価しているところが異なります。
そのため、専任の医師、看護師、薬剤師のいずれかが院内に常時1人以上配置され、患者からの副作用などの問い合わせや相談に24時間対応できる連絡体制を整備するという、外来化学療法加算にはなかった要件も加えられています(図2)。
代わりに、化学療法を実施していない日でも、副作用などのために受診した患者を診療した場合、通常の再診料などよりも点数の高い「同診療料のロ」を算定できるというメリットもあります。
図2 外来がん化学療法の評価の見直し
現 行
イ 外来化学療法加算1
(1) 抗悪性腫瘍剤を注射した場合- ① 15歳未満 820点
- ② 15歳以上 600点
ロ 外来化学療法加算2
(1) 抗悪性腫瘍剤を注射した場合- ① 15歳未満 740点
- ② 15歳以上 470点
改 定 後
(新)1 外来腫瘍化学療法診療料1
- イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 700点
- ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 4 400点
(新)2 外来腫瘍化学療法診療料2
- イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 570点
- ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 270点
(新)注 15歳未満の小児の場合 200点を加算
【算定要件】
- 悪性腫瘍を主病とする患者で、入院中の患者以外の患者に対して、注射による化学療法の実施及び実施に伴うその他必要な治療管理(副作用等に係る診 療等を含む)を行った場合に、イについては抗悪性腫瘍剤を投与した日に、月3回に限り、ロについては抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な治療管理を 行った場合に週1回に限り算定する。
- ロに規定する点数は、注射による外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間に、当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等で来院した患者に対し、診察(身体診察を含む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものである。
- 患者の心理状態に十分配慮された環境で、抗悪性腫瘍剤の効能・効果、投与計画、副作用の種類とその対策等について文書により説明を行う。
【施設基準】
- 専任の医師又は看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者からの副作用等に係る問い合わせ・相談に24時間対応できる連絡体制が整備されていること。
- 急変時等に当該患者が入院できる体制が確保されていること。
- 外来化学療法を実施するための治療室を有していること。
- 化学療法の経験を有する専任の医師、看護師、薬剤師が勤務していること。
- (外来腫瘍化学療法診療料1のみ)化学療法のレジメンの妥当性を評価・承認する委員会を開催していること。
一方で同診療料には、初診料や再診料などのほか、医師や薬剤師によるがん患者指導料(「がん患者指導管理料ハ」)も内包されています。つまり、同指導料を算定する患者については、薬剤師が外来がん化学療法に伴う患者指導をしても別に指導料は算定できません。その分、病院薬剤師にとって、薬局と外来化学療法で連携し、連携充実加算を確実に算定することがより重視されると考えられます。
バイオ後続品の導入を促す加算が
がんのバイオ医薬品にも拡大
外来がん化学療法では、バイオ後続品の導入促進策も講じられています。「バイオ医薬品(生物学的製剤)」は、一部の分子標的薬に代表されるような、遺伝子組み換え技術などを用いて細胞などから産生されるたんぱく質由来の薬剤です。
分子サイズが大きく構造が複雑で不均一性があり、バイオ医薬品では先行品と全く同じものを製造することが難しいことから、特許が切れた後に発売されるものを、後発医薬品とは区別して「バイオ後続品(バイオシミラー)」と呼びます。
バイオ医薬品は注射剤がほとんどのため、薬局で扱う機会は少ないと思いますが、価格が高い分、バイオ後続品への切り替えによる医療費削減効果が期待されています。前回の改定では、患者にバイオ後続品の情報を提供し使用した場合に算定できる「バイオ後続品導入初期加算」が新設されました。
今改定ではその算定対象が、リツキシマブ製剤など一部の抗がん剤にも拡大されました。診療報酬の仕組みの影響もあり、外来がん化学療法ではまだバイオ後続品の導入があまり進んでいないため、病院薬剤師には今後そうした部分での関与もより求められていくでしょう。
図3は、医療機関と薬局との連携を評価した主な診療報酬です。今回の改定ではここまでに触れた項目以外にも、糖尿病のインスリン注射導入時などの指導とフォローアップを評価した「調剤後薬剤管理指導加算」の点数の引き上げなどがありました。
図3 薬薬連携を評価した主な診療報酬
※矢印の左側から始まる項目は医療機関が算定、右側から始まる項目は保険薬局が算定

今回新設された連携に関する点数や、地域支援体制加算の算定対象拡大などを考え合わせると、医療を受ける場所が多様化するなかで、薬局には医療機関などとの切れ目のない連携が、これまで以上に強く要請されていることがうかがえます。逆に言えば、そうした連携こそが薬局の役割を見える化し、地域のなかで存在感を発揮することにもつながると考えられます。
(参考資料)
◎厚生労働省「令和4年度診療報酬改定の概要」(全体版、調剤)」
◎厚生労働省「疑義解釈資料」(その1、その3)
◎厚生労働省告示「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(2022年3月4日)
◎厚生労働省「医科診療報酬点数表に関する事項」「調剤報酬点数表に関する事項」
※本記事は2022年4月7日までの疑義解釈を参考に執筆しています。
医療系出版社勤務後、2000年に独立。薬剤師としての知識を活かしつつ、医療分野・介護分野を中心に取材を行う。
著書『福祉・介護職のための病院・医療の仕組みまるわかりブック』
『イラストで理解するケアマネのための薬図鑑』(共著)など。
マイナビ薬剤師転職サポートの流れ
-

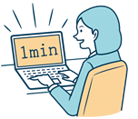
ご登録
ご登録は1分で完了!担当のキャリアアドバイザーからご連絡を差し上げます。
-


求人のご紹介
ご希望に合った求人をご紹介!求人のポイントなど、詳細もご説明いたします。
-

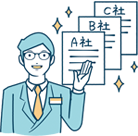
面接・条件交渉
面接対策をアドバイス!また、給与交渉や面接の日程調整等を代行いたします。
-


転職成功!!
入社日の調整や手続きなど、ご入社までサポートいたします。
その他の記事
-
 PICK UP
PICK UP2020年度診療報酬改定 在宅業務と薬局機能 調剤基本料見直しによる薬局への影響は?
-
 PICK UP
PICK UP常勤要件緩和で病院薬剤師に求められる役割
-
 PICK UP
PICK UP手厚くなった薬局の
「対人業務」評価の背景は? -
 PICK UP
PICK UP医療制度や薬機法との関係は?
“流れ”で考える2020年度診療報酬改定 -
 PICK UP
PICK UP薬剤服用歴の管理と
かかりつけ薬剤師機能 -
 PICK UP
PICK UP薬剤師の医師への疑義照会と
多剤併用(ポリファーマシー)対策 -
 PICK UP
PICK UP診療報酬改定で変わる薬剤師 在宅業務
同一建物居住者と単一建物診療患者 -
 PICK UP
PICK UP2018年度診療報酬改定でどう変わる?
薬剤師の現場 -
 PICK UP
PICK UP診療報酬改定で変わる薬剤師の転職市場
-
 PICK UP
PICK UP2016年度診療報酬改定概要と
医療機関・薬剤師への影響
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554
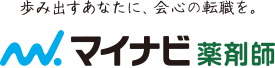






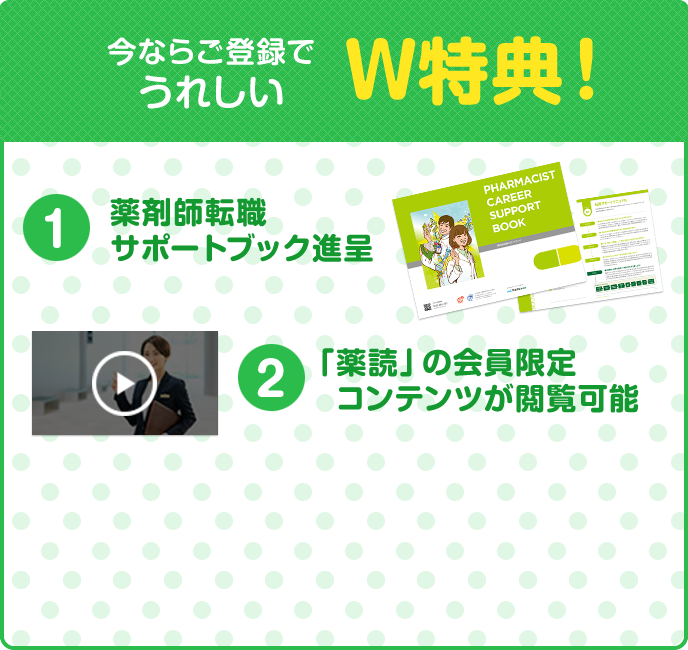
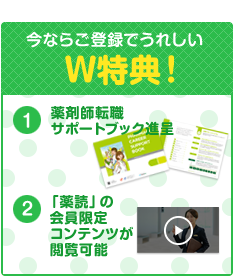
 はじめて転職される方へ
はじめて転職される方へ