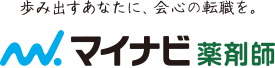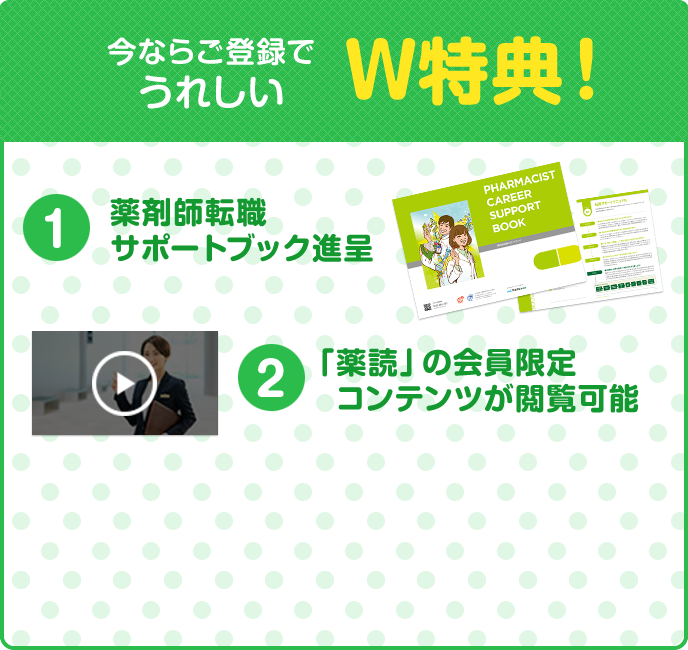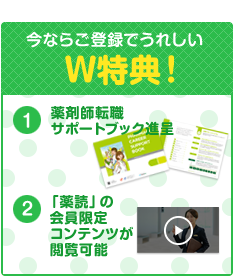災害時における薬剤師の役割とは?今後の課題について
 2011年に起こった東日本大震災の際、被災地では医師や看護師とチームを組み、調剤や診察のサポートなどを行う薬剤師の姿が見られました。また、それによって災害時における薬剤師の取り組みが広く知られることになりました。
2011年に起こった東日本大震災の際、被災地では医師や看護師とチームを組み、調剤や診察のサポートなどを行う薬剤師の姿が見られました。また、それによって災害時における薬剤師の取り組みが広く知られることになりました。
災害時は平時と違い、整った環境での活動は期待できません。そうした中で、薬剤師はどのような役割を果たすべきなのでしょうか。そして、いざというときのために、どのような備えをしておけばよいのでしょうか。
今回は、災害時に薬剤師に求められる役割や具体的な活動、日本の災害医療が抱える課題などについて解説します。
目次
1.日本での災害リスクとは
地震や台風、大雨……。日本では、毎年のように大規模な自然災害が起こっています。では、なぜ日本には自然災害が多いのでしょうか。日本における災害リスクは、主に日本列島の地形と気候変動に由来します。
日本は、世界の活火山の約1割が集中する火山列島であり、4つのプレート(※)の境界線上に位置しているため、常に地震や噴火の脅威にさらされています。日本の国土面積は世界の0.25%ほどにすぎませんが、世界中で発生するマグニチュード6以上の地震の約2割が日本とその周辺で発生しているのです。
※地球の表面を覆っている固い岩石層のこと。プレートとプレートの境界上で、それぞれが押し合ったり引っ張り合ったりすることで、内部にひずみが生じ地震が発生する。
また、日本は国土の7割が山地であるため、河川は急こう配で氾濫を起こしやすく、大雨が降ると洪水や土砂災害のリスクが高まります。
こうした地理的特徴に加えて、近年は気候変動によって局地的な豪雨に見舞われる地域も増えており、水害や土砂災害の被害はより甚大になっています。国土交通省の調査によれば、複数の自然災害リスクが重なる地域は、国土の約30%を占めており、全人口の67.5%が災害リスクに直面しているとされています。
さらに、2050年には日本の全人口の70%が、災害リスクにさらされるとの予測もあります。
2. 災害時における薬剤師の役割

先に紹介したように、被災地での薬剤師の支援活動が広く知られるようになったのは、東日本大震災がきっかけです。
このときの支援活動は、過去の災害時の支援と異なり被災県知事からの公的要請に基づいたものでした。
社団法人日本薬剤師会の「東日本大震災における活動報告書」によると、震災後には被災3県を除く44都道府県薬剤師会から、延べ8,378人(実人数2,062人)の薬剤師が被災地に出動し、支援活動を行ったと報告されています。
以下では、東日本大震災時に薬剤師が果たした役割や、災害時に救護所・避難所で薬剤師が行うべき活動について見ていきましょう。
2-1.救護所・避難所などでの服薬指導・薬の割り出し
被災地域における被災者の健康管理は、主に救護所や避難所で行われます。厚生労働省防災計画では、救護所や避難所において薬剤師が取り組むべきこととして、医薬品などの仕分け・管理、服薬指導などを挙げています。
その他、患者さんの使っていた薬の割り出しも、薬剤師の大事な役割です。災害時には、医療機関や薬局が被害を受けることもあるため、服用していた薬の割り出しを行い、適切な医療につなげる必要があります。
薬の名前を覚えていない患者さんがいた場合は、病気の名前、薬の色や形、服用時間といった情報の聞き取りを行うことで薬を特定します。被災直後の混乱した状況下では、「お薬手帳」が果たす役割も大きく、東日本大震災時も限られた医療資源の中からの医薬品の選択や、代替薬の提案に役立ったとされています。
2-2.医薬品使用に関する医師・看護師への助言
救護所や避難所で医療チームに参加した場合、薬剤師は医師、看護師に対して、医薬品使用に関する情報提供を行います。ただし、災害時は医療資源が限られているため、限られた医薬品の中から提案する場面が少なくありません。
それだけに、医師や看護師から医薬品に関する質問を受けたり、助言を求められたりする機会も多くなります。
2-3.医薬品などの仕分け・管理
東日本大震災後は、被災地の役所や災害拠点病院に、全国各地から医薬品支援物資が届きました。「救護所・避難所などでの服薬指導」でも触れたように、そうした医薬品の仕分け・管理は薬剤師の役割です。
具体的には、全国から支援物資として届く医薬品を薬効別に分類・整理し、どのような医薬品がどのくらいあるかなどの情報を取りまとめます。その中でも、規制医薬品の保管・管理に関しては、特に注意を払う必要があります。
2.4.医薬品などの供給
分類・仕分けされた医薬品は、各地の救護所・避難所に供給されます。避難所では、便秘薬や風邪薬などの市販薬の他、マスク、消毒キットといった衛生用品のセットを配布することもあります。
3.災害時における医療の課題
災害時における医療の目的は、限られた人員と医療資源を使って、一人でも多くの命を救うことです。災害時は、平時と違って人的にも物理的にも医療資源が限られるため、優先順位を意識して医療を提供する必要があります。
ここでは災害医療の課題や災害医療のあり方について、詳しく見ていきます。
3-1.医療機関全体の災害医療の対応能力強化
宮城県の東北大学病院では、東日本大震災の被災経験から、災害発生時に病院の機能を維持し、医療の提供を継続するための要素として以下のことを挙げています。
- 暖房機能が消失したことによる低体温症への対応
- エレベーターが停止した際の患者や医療器材、資材の搬送
- 固定電話、携帯電話、インターネットなどの通信手段
- 電気、ガス、水道などライフライン停止時の備え
- 非常用発電の燃料、医薬品、水、食料の十分な備蓄
東北大学病院では、これらの課題について宮城県内の医療機関にアンケートを行い、病院版「事業継続計画(Business Continuity Plan:BCP)」策定の必要性を提起しました。
病院版BCPとは、「企業における災害時の危機管理と対応策をまとめた計画書」を病院に置き換えたもので、「設備やライフラインの停止・人的リソースの不足などが起こった場合に、病院の機能維持に必要な手順を決めておくこと」と、「通常の方法が取れない場合の代替手段を複数用意しておくこと」の重要性を説いています。
そうした提言や、2016年の熊本地震における被害状況を受けて、厚生労働省は2019年に災害拠点病院の指定要件を改正。災害拠点病院として指定されている病院や今後指定される病院に、事業継続計画(BCP)の整備と、計画に基づく訓練の実施を求めました。
それによって、災害拠点病院におけるBCP対策の策定率は上がりましたが、一般病院や個人医院、クリニックでの対策は、いまだに追いついていないのが実情です。
災害はいつどこで起こるかわかりません。今後は、災害拠点病院以外の医療機関でも、BCPの策定や災害対策マニュアルを整備充実させ、いざというときに災害医療に対応できる体制を整える必要があるでしょう。
参照元:東北大学病院 高度救命救急センター/東日本大震災における診療活動の問題点と新たな災害対策の提言
参照元:厚生労働省/病院の業務継続計画(BCP)策定状況調査の結果
3-2.全地域での協力体制の構築
1995年の阪神・淡路大震災では、多くのけが人が十分な治療を受けられず、約500人が「防ぎ得た災害死」で亡くなったと考えられています。
その後、阪神・淡路大震災の教訓を生かすべく、各地の災害拠点病院に医療救護チームが誕生。2005年には、より機動力のある医療活動が全国規模でできるようにと、厚生労働省によってDMAT(Disaster Medical Assistance Team:災害派遣医療チーム)が組織されました。
しかし、東日本大震災では、DMATが想定した外傷による重症患者は少なく、避難所での感染症や慢性疾患の悪化など、内科的な医療ニーズが多くを占めるという状況が起こっています。また、広域災害だったことから、救護班が現地に到着するまでに時間がかかり、二次的な災害死も発生しました。
そのため東日本大震災以降は、DMATの活動内容に、現場での外傷による急性期医療だけでなく、内科的対応や救護班へのスムーズな引き継ぎが盛り込まれました。また、避難所での公衆衛生や健康管理までカバーするため、被災地外の医療機関との連携を図る災害医療コーディネーターのチームも、新たに創設されています。
DMATは、航空機やヘリコプターなどを用いた広域医療搬送でも、中心的な役割を担います。現在、広域医療搬送計画の実施を想定している災害は、「東海地震」「東南海・南海地震」「首都直下地震」という3つの大規模地震ですが、自衛隊との連携により計画外の災害時にも柔軟に対応できるよう検討が進められています。
3-3.地域包括ケアシステムと多種連携
阪神・淡路大震災以降、新潟県中越地震(2004年)、東日本大震災、熊本地震、そして2019年の台風19号と大災害が続き、その都度、災害に応じたさまざまな対策が検討・実施されています。しかし、被災者が避難所や復興住宅で不自由な生活を強いられる状況は変わらず、災害関連死も減る気配がありません。
災害関連死の主な原因は、適切な治療を受けられないことによる持病の悪化、悪環境によるストレス、車中泊でのエコノミークラス症候群、将来を悲観しての自殺や仮設住宅での衰弱による孤独死などです。
災害関連死を防ぐには、避難所や復興住宅にあっても適切な医療や介護、生活支援、介護予防サービスが提供され、身体的・精神的な負担を軽減できる環境が必要です。そのためには、自治体と医療・介護の専門家による、多職種多機関の連携が欠かせません。孤独死を防ぐという意味では、自治会、老人クラブ、NPOといった地域団体の役割も重要です。
それを踏まえるなら、災害関連死を防止する取り組みは、厚生労働省が推進する地域包括ケアシステムの骨格と一致するといってよいでしょう。
地域包括ケアシステムとは、自宅にいながら必要に応じて適切な医療や介護、生活支援、介護予防サービスなどを受けられる地域ネットワークのことで、中心となってサービスをコーディネートするのが地域包括支援センターです。
災害関連死を防ぐためにも、今後は地域包括ケアシステムを災害対策の中核に据え、地域包括支援センターと医療保健・介護の専門家、地域団体、そして公的機関が連携するためのインフラづくりが望まれます。
4. 災害時に求められる「災害薬事コーディネーター」とは
災害時は、医療ニーズに対して医療資源が圧倒的に少なくなると予測されますが、そうした状況においても、的確にニーズを把握し、医療が提供される必要があります。
そして、被災地域において適切な保健医療活動が行われるように、調整・助言・支援の役割を担うのが、都道府県が任命した「災害医療コーディネーター(医師)」です。厚生労働省は、災害医療コーディネーターを次のように定義しています。
「災害時に、都道府県並びに保健所及び市町村が保健医療活動の総合調整等を適切かつ円滑に行えるよう、保健医療調整本部並びに保健所及び市町村における保健医療活動の調整等を担う本部において、被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行うことを目的として、都道府県により任命された者」
また、災害時に災害医療コーディネーターを手助けし、医薬品に関するさまざまな要望や、医療救護活動に従事する薬剤師の調整を行う専門家のことを「災害薬事コーディネーター」といいます。災害薬事コーディネーターも都道府県が任命します。
災害薬事コーディネーターは、災害薬事に精通した薬剤師で、災害時の保険医療活動に必要な医薬品・医療材料の確保や供給、薬剤師の確保、災害医療コーディネーターとの連絡調整、被害状況の報告などの役割を担います。
災害薬事コーディネーターの養成は、都道府県ごとに行われているので、興味のある方は住まいのある地域の状況を確認してください。
参照元:厚生労働省/災害医療コーディネーター活動要領の概要
参照元:東京都 保険医療局/東京都災害薬事コーディネーター
5. まとめ
大地震や気候変動による水害、土砂災害といった自然災害が増加している一方で、災害医療も進化しており、以前よりも対応能力が高まっています。しかし、災害によってもたらされる被害のすべてに対応できるわけではありません。特に、災害発生後の関連死への取り組みには、まだ多くの課題が残ります。
そうした中、薬剤師は一人でも多くの方を災害関連死から救うため、調剤や服薬指導などを通じて適切な健康管理を行うことが大事です。
日本薬剤師会がまとめた「薬剤師のための災害対策マニュアル」では、災害時に果たすべき薬剤師の役割についてこう述べています。
「災害時に果たすべき薬剤師の役割は災害によりさまざまであり、個別の事情に応じた創意工夫・臨機応変な対応が必要である。平時から準備と研鑽を怠らず、いざというときには求められる薬剤師の職能を最大限発揮してほしい」
大規模災害のリスクは、私たちのすぐ近くにあります。みなさんもこの記事をきっかけに、防災や緊急時の対応について、見直してみてはいかがでしょうか。
毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報
おすすめの薬剤師求人一覧
転職準備のQ&A
薬剤師の職場のことに関するその他の記事
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554