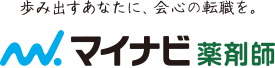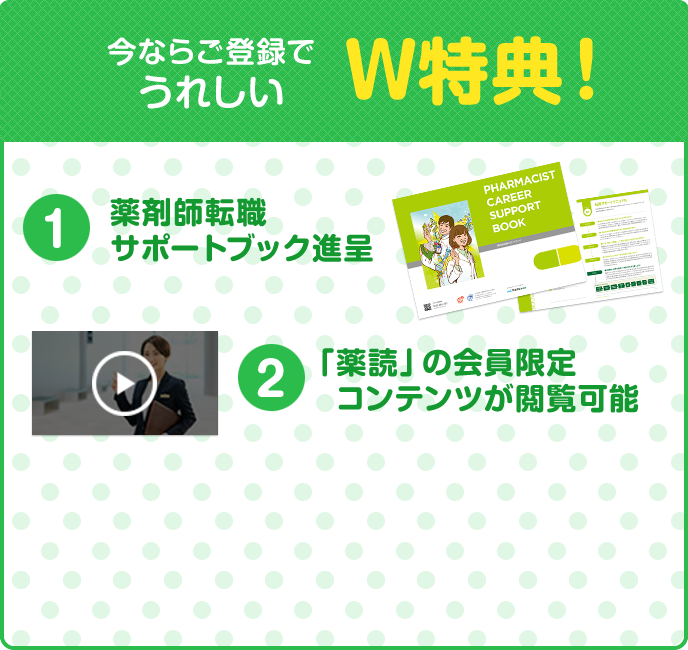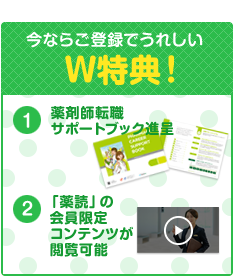大学病院の薬剤師に転職するには?人気理由・仕事内容・転職方法

大学病院は、医療施設でありながら研究・教育機関の側面も持つため、薬剤師としてスキルアップが目指せる職場です。最新医療を学べることからも、薬剤師に人気の勤務先となっていますが、残念ながらその求人は決して多くありません。
今回は、大学病院薬剤師が人気を集める理由や、大学病院への転職を希望する人が知っておきたいポイントについて解説します。
目次
1.大学病院の薬剤師の仕事内容

大学病院に勤務する場合、薬剤師は薬剤部に所属し、チームごとに決められた業務を担当します。病院によって名称や区分は異なりますが、一般的に調剤チーム、医薬品管理チーム、医薬品情報チーム、製剤チーム、病棟チーム、治験チームなどにわけられます。
チームはローテーションで交替することもあれば、複数のチームを兼務することもあります。大学病院に入った薬剤師は、まず先輩薬剤師から各チームの業務を学びながら、勤務することになるでしょう。
薬剤師としての業務の大半を占めるのが調剤業務ですが、大学病院の処方せんは、調剤を院内で行う「院内処方」と、処方せんを発行して調剤は行わない「院外処方」にわけられます。ただし、院外処方であっても調剤薬局とのやりとりが発生するため、薬剤師は両方の処方せんに関わる必要があります。
また、大学病院における医薬品の品目は年々増加しており、在庫管理や発注・納品業務、品質管理も、薬剤師の大事な業務の一つとなっています。特に、麻薬や覚せい剤原料、向精神薬の取り扱いには十分な注意が必要で、保管だけでなく使用量や使用残量、廃棄についても正確な記録が求められるでしょう。
そのほか、DI室(Drug Information)と呼ばれる部門に配属され、医薬品に関する情報の収集や管理、評価、提供を行うケースもあります。
1-1. 高いスキルが求められると同時に、やりがいのある臨床現場
近年は、院外処方が推進されていることから、薬剤師の仕事は入院患者さん向けのより専門的な調剤業務が中心となります。
また、大学病院はさまざまな疾患に対応しており、薬剤師は化学療法に用いる抗がん剤や緩和ケア用の麻酔剤など、数多くの医薬品を取り扱います。そのため、他の職場と比べて、薬剤師としての知識・技術を発揮する機会も多いでしょう。
病棟業務、では、個々の患者さんに対する服薬指導のほか、薬物療法プロトコールの設計、医師への処方提案なども行います。病棟ごとに担当薬剤師を設置していることが多いため、患者からの信頼も得やすく、やりがいのある業務となるでしょう。
加えて、大学病院ではチーム医療に参加することも少なくありません。チーム医療に携わる場合は、薬学的な助言や提案を求められるほか、治療計画への参加、安全性のモニタリングなども必要となるため、より高いレベルの知識・スキルが要求されます。
一方で、医師や看護師、理学療法士、臨床検査技師といった各分野のスペシャリストから、専門性の高い知識・スキルを学べるため、チーム医療に参加し臨床経験を積むことは、薬剤師としての成長につながるはずです。
2.大学病院薬剤師が人気の理由
大学病院は、薬剤師に人気の職場として知られています。一般病院や調剤薬局、ドラッグストア、医薬品メーカーなど、薬剤師が活躍できる職場は多くありますが、なぜ大学病院に人気が集まるのでしょうか? ここでは、その理由を考えてみましょう。
2-1. 最先端の医療に触れられる

大学病院に勤務するメリットの一つに、「最先端の医療に触れられる」という点が挙げられます。
大学病院では、治験や研究を通じて最新の医薬品、医療機器をチェックできるほか、調剤薬局では触れる機会がないような貴重な医薬品を取り扱うこともあります。、そうやって、最新医療に触れながら多くの臨床経験を積むことで、薬剤師としての専門性は一段と高まるでしょう。
2-2. 薬剤師としてスキルアップできる
病棟業務では、患者さんの状態を把握しながら調剤を行うため、高い実践力が身につきます。服薬指導の結果を受けて、医師に処方提案を行ったり、チーム医療の中で他職種に助言したりする機会も多く、業務を通じて薬剤師としてのスキルアップが図れるでしょう。
また、大学病院の中には、教育体制や研修が充実しているところが多く、薬学だけでなく医療全般の知識を身につける機会も少なくありません。
2-3. 生涯年収が高い傾向にある

大学病院で勤務を続け、薬剤部長などの役職につくことができれば、民間の調剤薬局で働くよりも多くの収入が期待できます。収入が安定しているほか、各種手当や退職金などの制度も充実しているため、生涯年収の水準も高めです。
2-4. 実践的な臨床経験が積める
より実践的な臨床経験が積めるのも、メリットの一つです。調剤薬局の場合、薬の処方意図は処方せんの情報から読み取るしかありません。しかし、大学病院では、患者さんの病歴や基礎疾患、病状の経過などの背景と照らし合わせながら調剤できるので、症状と薬のつながりが理解しやすくなります。
さらに、薬を処方した患者さんの経過を見て、薬の効果や適応をリアルタイムで評価できるのも大きな魅力です。
2-5. チーム医療に携われる

前述したように、チーム医療に関わる機会が多いのも、大学病院の大きなメリットです。薬剤師は医薬品の専門家として、がん治療や緩和ケア、経管栄養サポート、感染対策などに関わるほか、病棟業務やカンファレンスにも参加します。
現在は、薬物療法が高度化・複雑化しているほか、医薬品の種類も増加しているため、チーム医療における薬剤師の役割は、今後ますます大きくなるでしょう。
ちなみに、2012年の診療報酬改定で、「病棟薬剤業務実施加算」が創設されましたが、これは「医療機関の病棟などにおいて、薬剤師が医師などの負担軽減や薬物療法の有効性・安全性向上のために薬剤関連の業務を実施していること」を評価するものです。つまり、病棟業務に薬剤師が参加することの重要性を、国や医療機関が認めているわけです。
さらに、2024年の診療報酬改定では「病棟薬剤業務実施加算」が新設され、チーム医療の推進・薬物治療の質の向上を目指して、薬剤師の養成強化が図られることになりました。
参照元:厚生労働省/平成24年度診療報酬改定について
参照元:厚生労働省/令和6年度診療報酬改定について
3.大学病院の薬剤師の年収相場
大学病院の薬剤師の年収事情も気になるところです。大学病院勤務といっても、国公立大か私立大かによって若干異なるため、それぞれに平均年収を見ていきましょう。
国公立の大学病院の場合は、国家公務員給与表に基づいて初任給が定められています。薬剤師には医療職俸給表(二)が適用され、2024年時点の6年制薬剤師の初任給(2級15号俸)は平均で月額24万4400円です。各種手当や賞与を入れると、平均年収はおよそ350万円程度になるでしょう。
次に私立の大学病院ですが、こちらに関しては、病院ごとに給料が異なるので一概にはいえません。ただし、初任給の一般的な相場は、国公立病院薬剤師と比べて若干高い傾向にあるため、平均年収は370〜380万円程度と考えておくのがよいでしょう。
国公立と私立の病院薬剤師の初任給を比較すると、私立のほうがやや待遇がいいようにみえますが、国公立の場合は「定期昇給」といって、勤続年数に応じて年収が上がっていく仕組みです。そのため、長く勤めるほど収入がアップするでしょう。
参照元:人事院/ロ 医療職俸給表(二)
4.大学病院で働くデメリットを知っておこう
大学病院での仕事は、メリットばかりではありません。転職を検討する前に、デメリットについても確認しておきましょう。
4-1. 夜勤で不規則な生活に

多くの大学病院は、特定機能病院や地域医療支援病院などの認定施設となっており、夜間の救急外来を開設しています。薬剤師も救急対応に当たる必要があるため、シフト制で夜勤に入ることになるでしょう。
在籍している薬剤師の人数にもよりますが、救急対応や夜間業務への対応のために、勤務時間や日数が長くなることもあり、生活リズムが不規則になりやすいことを覚えておいてください。
ただし、労働基準法によって、午後10時~午前5時に就業した場合は、基本給に25%の賃金を上乗せすることが定められているため、夜勤や当直業務に入れば収入アップが見込めます。
大学病院勤務の薬剤師の夜勤・当直手当も、上記の規定に準じて支給されますが、手当の内容は病院ごとに異なるため、実際の金額については事前に調べておくとよいでしょう。
4-2. 業務範囲が広く毎日が忙しい

大学病院の薬剤師は、責任の重さもさることながら、広範囲の業務をカバーするため多忙になりがちです。
調剤業務を例に取ると、まず朝一番に入院患者さんのための調剤を行います。大学病院の本院であれば、入院患者数は数百人以上にのぼり、そのほとんどが点滴や投薬を受けるため、それらすべての準備と管理を担うことになります。
午前から夕方にかけては、外来や退院患者さんのために院内処方せんの対応を行います。大学病院では院外処方が主流になったとはいえ、院内処方がなくなったわけではありません。また、夕方以降は、手術や処置を終えた患者さんの処方せんにも対応します。
薬剤師はその他に、病棟関連の業務もこなさなければいけません。チーム医療に参加している場合は、医師や看護師などと病棟の回診を行ったり、合同カンファレンスや勉強会に参加したりすることも多く、多忙を極めるでしょう。
しかしそれらは、高い専門性を持つ薬剤師にしか行えない業務です。患者さんや医師などから薬に関するアドバイスを求められることも多いので、病院薬剤師の中には、「大変さよりもやりがいや充実感のほうが大きい」という人も少なくありません。
実際、さらなるスキルアップを目指して、研修や学会などにも積極的に参加する人もいます。
4-3.すぐには病棟業務に携われない場合がある
薬剤師の中には、「チーム医療に貢献したい」という理由から、大学病院を目指す方も多いでしょう。しかし、大きい病院の場合、数年経験を積んでからでないと病棟に上がれないケースも見られます。
早くから病棟業務に携われるイメージで転職すると、入職後にギャップが生じる可能性があるので、 キャリアプランについては面接で確認しておくのがよいでしょう。
5.大学病院への転職が難しい理由
実践的な臨床経験を積み、薬剤師としての専門スキルが磨ける大学病院は、非常に魅力的な職場です。しかし、大学病院への転職は決して簡単ではありません。なぜ大学病院への転職が難しいのか、その理由を見ていきましょう。
5-1. 大学病院の求人は新卒採用のみのところが多い

大学病院の求人は新卒採用がほとんどで、中途採用はあまり積極的に行われていません中途採用については、現職の薬剤師が退職した場合の欠員補充として行われることが多いため、募集があったときに、タイミングよく転職活動を行う必要があります。
5-2. 欠員補充の採用が多い
前述したように、大学病院が中途採用を行うのは、ほとんどが欠員を補充するケースです。出産や転居などの理由で薬剤師が不足した場合に限られるため、必然的に不定期の募集となります。
新卒採用とは異なり、事前に情報を得ることが難しいので、こまめに情報収集を行うことが大切です。
5-3. 応募が殺到するため倍率が高い
欠員補充などを目的とした募集は、採用人数が「1名」や「若干名」であるケースがほとんどです。しかし、狭き門であるにも関わらず、キャリアアップを目指して大学病院への転職を希望する人は多く、採用倍率は非常に高くなる傾向にあります。
この狭き門を突破するには、薬剤師として培ったスキルや経験をアピールし、他の応募者との差をつける工夫が必要でしょう。

限られた求人を見逃さないポイント
働きながら日々希望の求人があるか探すのは大変ですよね。転職エージェントに登録し希望を伝えておけば、希少な求人もキャッチしてお知らせしてくれるので、転職をより有利にすすめることができますよ。
6.大学病院に転職する際のポイント
転職するのが難しいとされている大学病院。それだけに、しっかりと計画を立て、対策を練って転職活動に臨むことが大切です。
ここでは、大学病院への転職を成功させるために、押さえておくべきポイントを紹介しましょう。

6-1. 国立・大手の病院にこだわらず範囲を広げる
国立病院や大手の大学病院は、そもそもの病院数が限られています。また、離職者も少ないため、中途採用の募集がかかる機会はさほど多くありません。大学病院を希望するなら、選択肢を私立大学にまで広げておくのがよいでしょう。
また国立病院であれば、各地に多くの分院や関連病院を抱えています。都市部での勤務にこだわらず、分院なども視野に入れて検討すれば、意外な求人が見つかる可能性があります。
6-2. 求人の多い慢性期病院に絞って転職活動を行う
高齢化が進む日本では、慢性期疾患を扱う病院が増加傾向にあります。
新設される病院は、求人の数が多めになるので、時間をかけずに転職を成功させたい方には狙い目かもしれません。慢性期病院の場合、患者さんとじっくり向き合うことができ、ワークライフバランスのとれた働き方ができるのが特徴です。
6-3. 求人情報のキャッチアップを欠かさない
転職を成功させるためには、求人情報をより早く、漏らさずに入手することが大切です。特に、欠員補充を目的とした求人は、いつ公開されるかわからない上に、応募期間が短い傾向があります。普段からアンテナを張り、情報収集を怠らないようにしましょう。
7.求人情報を見逃さない!「マイナビ薬剤師」への登録を

希望する病院への転職を成功させるためには、効率的かつすみやかに情報を収集することが大切です。「気づいたときには募集が終了していた」ということがないように、求人情報はこまめにチェックしておきましょう。
とはいえ、仕事をこなしながら、情報をチェックし続けるのはなかなか大変です。転職活動をスムーズに進めたいなら、転職エージェントを活用するのも一つの方法でしょう。
薬剤師専門の転職エージェントである「マイナビ薬剤師」では、常に最新の情報を入手し、転職希望者に寄り添ったサポートを展開しています。ちなみに、マイナビ薬剤師の転職サポートを利用すると、次の4つのメリットが得られます。
メリット1. 多くの求人情報を保持している
薬剤師の業界に精通したスタッフが、多くの求人情報をいち早く入手しています。若干名の応募や臨時募集など、見逃しやすい求人も漏らさずキャッチしているので、安心して転職活動に臨めます。
メリット2. プロのアドバイザーによる分析や希望に沿ったマッチング
プロのキャリアアドバイザーが、あなたのキャリアや魅力を客観的に分析し、希望に合った転職先を案内します。
過去のデータをもとに、業界の動向や実際の労働環境、職場文化なども把握しているので、転職してから「イメージと違った」というようなミスマッチも防げるでしょう。
メリット3. 応募書類の添削や面接対策も
キャリアアドバイザーは、通りやすい選考書類の書き方や、面接のポイントに関するアドバイスも行っています。応募が殺到する大学病院では、書類審査で他の応募者と差をつけることが大切です。適格なアドバイスを受けることで、転職活動を有利に進めましょう。
メリット4. 日程調整や交渉などもキャリアアドバイザーが代行
面接の日程調整はもちろん、手当や勤務条件、転職時期といった応募者本人からは切り出しにくいような要望についても、キャリアアドバイザーが交渉を代行します。
以上のように、マイナビ薬剤師に登録すれば、転職活動全般のサポートを受けながら転職に臨むことができます。まずは、マイナビ薬剤師に無料登録しておきましょう。
毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報
転職準備のQ&A
薬剤師の職場のことに関するその他の記事
※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。
※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。
「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554